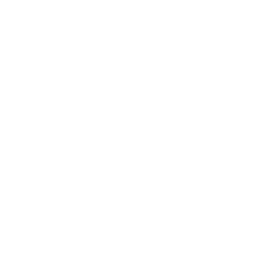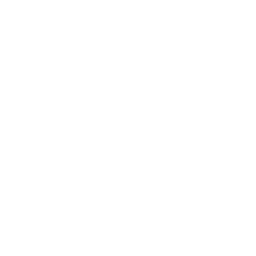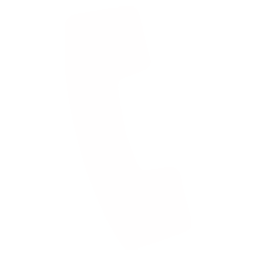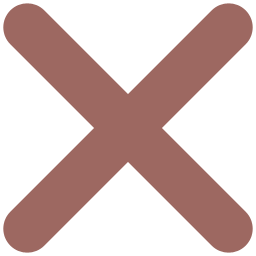遺言の効力
更新日:2022/10/17
遺言の効力
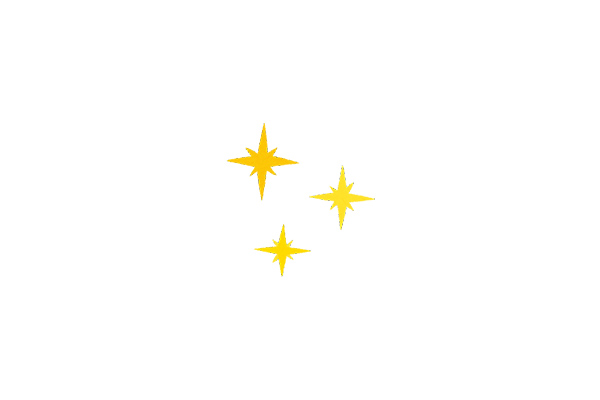
第1 遺言の効力の発生時期
1 遺言者の死亡時
遺言は、適法な方式を具備して遺言書が作成されたときに成立し、遺言者の死亡時にその効力を生じます。遺言が適法に成立していたとしても、遺言者が死亡するまでは効力は生じません。したがって、遺言書の中に、自身に有利な事柄が記載された第三者であっても、遺言者が死亡するまで何ら確定的な権利を取得しません。このことは、遺言者に遺言撤回の自由(遺言者はいつでも自由に成立済みの遺言を撤回することができるという遺言者の権利)が認められていることの裏返しです。
2 遺言事項に停止条件が付いていた場合
法は、遺言の中の一定の事項に停止条件を付すことも認めています。停止条件というのは、効力の発生不確定の将来の事情に掛らしめる類型の条件のことです。たとえば、「20●●年までに孫が●●大学の入試に合格した際は、当該孫に対し、遺産の中から●●円を贈与する。」という遺言の場合、孫が●●大学の入試に合格するか否かは将来の不確定事情に当たるため、停止条件付きの遺言事項となります。
このように停止条件が付された遺言事項がある場合、当該事項に関しては、停止条件が成就した場合に初めて効力を生じます。この場合、当該遺言事項によって利益を得る可能性のある者は、遺言者の死亡時に停止条件付の権利を取得し、将来の条件成就によって初めてその権利を現実に行使し得る法的地位に立つことになります。
3 遺言内容の実現のため一定の手続を要する場合
遺言事項によっては、遺言の効力を発生させるため遺言者の死後に一定の手続を要する場合があります。遺言による相続人の排除や排除の取消がこれに当たります。遺言によって相続人を廃除する場合、あるいは排除の取消を行う場合、遺言者の死亡だけでは足りず、後に遺言執行者等によって家庭裁判所に対して審判の申立てを行い、同裁判所の審判を得る必要があります。この場合、審判が確定するまで当該遺言事項の効力は生じず、審判が確定した際に遺言者死亡時に遡って当該遺言事項の効力が発生することとなります。
第2 遺言の無効・取消事由
1 民法総則の無効・取消事由の適用可能性
遺言の内容は、財産上の事項に関するものと身分上の事項(認知等)に関するものに分けることができますが、法は、この身分上の事項については、民法総則を理由とした取消しを認めていません。つまり、民法総則は、「錯誤」(勘違い)、「詐欺」、「強迫」に伴う意思表示は、表示者自らが事後にそれを取り消すことを認めていますが、遺言によって行った身分上の事項に関する意思表示については、この取消権を認めていないのです。もっとも、「錯誤」「詐欺」「強迫」等の事情の有無にかかわらず、認知が真実と合致しない場合、遺言者の相続人は「認知無効確認の訴え」を起こし、その有効性を争うことができます。
遺言内容のうち、財産上の事項に関するものには、民法総則の規定に基づく取消しが認められています。もっとも、取消権者は、遺言者ではなく遺言者の相続人とするのが通説です。遺言者自身は、錯誤や詐欺・強迫によって真意と異なる遺言を行った場合、事後、当該遺言を撤回するか、新たな遺言を作成して旧遺言を失効させることが可能だからです。
2 不倫関係にある者への遺贈を記した遺言と公序良俗違反
民法総則には、公序良俗に反する法律行為を無効とする規定があります(民法90条)。この事から、不倫関係にある者への遺贈を記した遺言が公序良俗違反として無効となるのではないかという議論があります。この点については、有名な最高裁判例があります。法律婚が事実上破綻した後に、不倫相手との半同棲の関係が公然と生じて7年ほど継続した段階で、同棲相手に対して男性が行った遺贈(遺言による贈与 判例のケースでは全財産の3分の1の包括遺贈であった)について、①その遺贈が専ら生計を遺言者に頼っていた相手方女性の生活保全を目的としたもので、不倫関係の維持継続を目的とするものでなく、②その遺言内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものでもなかったという理由から、公序良俗違反には当たらないと判示した事例です。
一般論としても、たとえ不倫相手への遺贈であっても、いわゆる重婚的内縁関係が認められる場合(つまり、不倫相手との間で事実上の婚姻関係が認められるような場合)、内縁として保護に値する範囲では公序良俗違反に当たらないとされています。問題は、内縁として保護されない領域での遺贈が公序良俗とされるかですが、この点は、目的の合理性(不倫関係の維持継続を目的とするものか否か)や手段の相当性(相続人の生活基盤への影響)によって個別に判断するというのが、判例を含む裁判実務の傾向と言えます。
3 遺言独自の無効事由
遺言独自の無効事由としては、以下のものが挙げられます。
①遺言能力の欠如
②方式要件の違反
③成年後見人を利する成年被後見人の遺言
これらの解説は、それぞれ該当の記事をご覧下さい。
第3 遺言の撤回
1 遺言撤回の自由
(1)遺言撤回の自由
遺言者は、自らが行った遺言を、生存中、いつでも何度でも自由に撤回することができます(遺言撤回の自由)。
(2)撤回権放棄の不可
民法は、遺言者による遺言撤回権の放棄を禁止しています。遺言撤回の自由の保障を貫徹しているのです。当然、第三者との間で遺言撤回権を放棄させる内容の契約を結んだとしても、その契約は、違法・無効なものとなります。
2 撤回の意思表示の方法 -遺言の方式に従うこと-
法は、遺言撤回の意思表示も、遺言の方式に従って行うことを要求しております。これは、遺言を成立させる時だけでなく、遺言を撤回させる場合においても厳しい方式性の要件を課すことで、遺言者の真意性を確保しようとする趣旨です。
ただし、撤回のための遺言方式は、先に為された遺言と異なる方式で行うのでも構いません。例えば、先に成立させた公正証書遺言を撤回する場合、撤回遺言は必ずしも公正証書遺言の方式による必要はなく、自筆証書遺言の方式によって行うことも認められています。
3 撤回擬制
撤回遺言(旧遺言を撤回する意思表示を遺言の方式で行うこと)以外にも、次のような場合には、法律上、遺言が撤回されたものとみなされます(このことを撤回擬制といいます。)。
①旧遺言と後の遺言が内容的に抵触する場合(抵触遺言)
②遺言の内容とその後の生前処分とが抵触する場合
③遺言者が故意に遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合
①は、先だって作成された遺言書ではAに自宅を相続させると記載していたものの、その後、別の遺言を作成し、そこにはBにこれを相続させると記載しているようなケースです。この場合、2つの遺言内容が抵触しますので、後の遺言を優先し、旧遺言の撤回が擬制されます。この遺言の「抵触」は、客観的に両立不能という場合に限られず、後の遺言が作成された趣旨等諸般の事情に照らし、前の遺言と両立させないという遺言者の意思が読み取れる場合まで含むとするのが判例です。
②は、遺言者が息子のAに自宅を相続させると記載した遺言書を作成したものの、その後、遺言者が第三者に対してその自宅を売却してしまったようなケースです。この売却行為は、遺言内容と抵触する生前処分として遺言の撤回が擬制されます。
③は、遺言者が息子のAに自宅を相続させると記載した遺言書を作成したものの、その後、Aとケンカして立腹し、その遺言書を破り捨てたといったケースです。ここでいう「故意」による「破棄」とは、遺言者が、遺言書であることを認識した上、これを破棄する意思で破棄することを意味します。物理的損傷のみならず、遺言書の文面を抹消して判読できないようにしたりする場合を含みます。判例では、遺言者が遺言書の文面全体に赤色ボールペンで斜線を引いた行為も、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言のすべての効力を失わせる意思の表れとみるのを相当として、「故意」による「破棄」に該当すると判断しています。他方、誤って遺言書にお茶をこぼして汚損したとしても、それは「故意」による「破棄」には該当しませんので、撤回擬制は生じません。
4 先行する遺言との一部抵触
先行して行われた遺言における遺言事項のうち一部についてのみ抵触行為が行われることがあります。この場合、抵触部分について撤回擬制が働くことは上記のとおりです。
問題は、抵触する部分を除いた残部の遺言の効力がどうなるかという点です。この点は、遺言者意思の解釈によって判断されることとなりますが、抵触部分に撤回擬制が生じてもなお遺言の残部が法的に成り立ちうる場合には、残部のみ有効と扱われるのが通常です。
5 撤回遺言等の撤回・取消しと旧遺言の復活の可否
(1)撤回遺言の撤回と旧遺言の有効性
遺言者には遺言自由の原則が認められています。このことは、撤回遺言(遺言を撤回する旨の意思表示が記載された遺言)に対しても適用され、遺言者は撤回遺言に対しても撤回することが可能です。
もっとも、撤回遺言によって失効した旧遺言は、たとえ後に撤回遺言自体が撤回されたとしても復活しないのが原則です。これは、撤回遺言を撤回する遺言者の意思に旧遺言の復活が含まれるかは不明であることが多く、また、遺言者が旧遺言の効力を復活させたい場合は新たに旧遺言と同内容の遺言を改めて行うことで達成し得るとの理由によります。
もっとも、こうした理由に照らし、撤回遺言の中に旧遺言を復活する旨の意思表示が行われている場合は、旧遺言の復活を認めるのが判例です。
(2)抵触行為の撤回・取消と旧遺言の有効性
撤回遺言に関する上記議論は、抵触行為による撤回擬制の場合も同様に当てはまります。
(3)撤回遺言等が錯誤・詐欺・強迫による場合
撤回遺言や抵触行為が錯誤・詐欺・強迫によって行われ、事後にこれが取り消される場合には、旧遺言は復活します。このようなケースでは、旧遺言の効力を復活させることが遺言者の意思であると法が考えているためです。
遺言についてご相談をされたい方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスにご連絡下さい。
初回相談は60分無料で、来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。まずはお電話でお問合せください。
0120-100-129
(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)