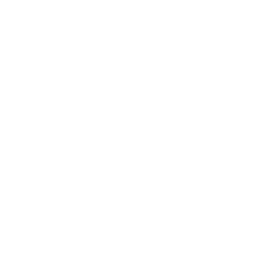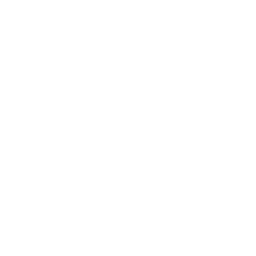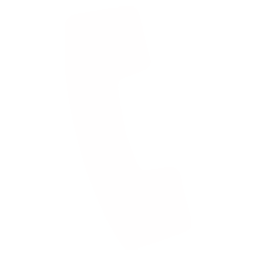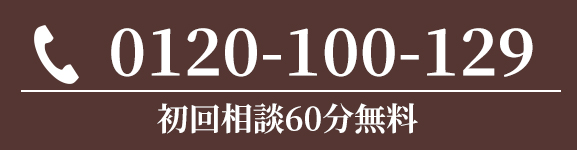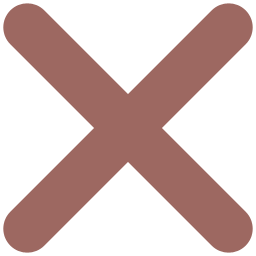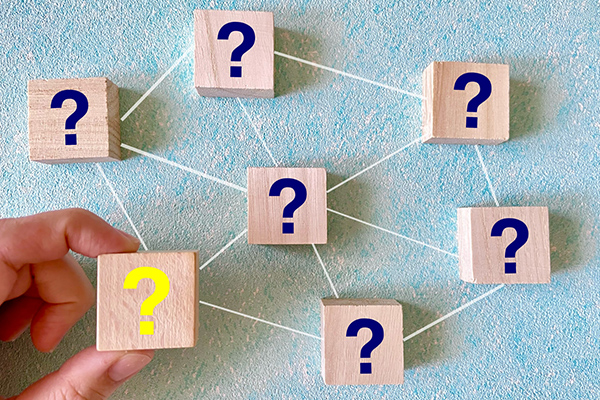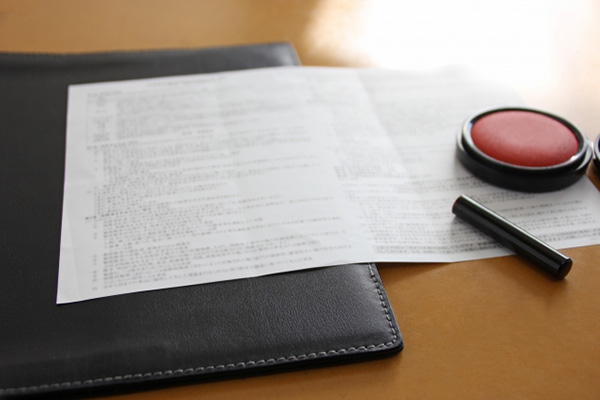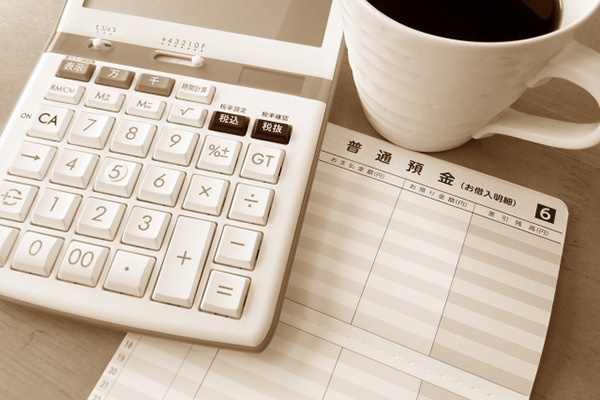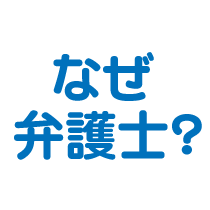生命保険金と遺産分割
更新日:2017/08/09
遺産分割の諸問題(2)生命保険金と遺産分割
2015.12.25 弁護士 茂木 佑介 ニュースレター24号掲載

「相続対策に生命保険を利用しませんか?」というキャッチコピーを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。皆様の大切な財産を次世代に繋いでいく方法として生命保険を利用するケースが多数ございます。では、「生命保険金」が遺産分割の場面でどのような扱いをされているのかご存知でしょうか。今回は、「生命保険金と遺産分割」というテーマをご説明させて頂きます。
そもそも、「生命保険契約」とは、特定の人の生死を保険事故とし、その保険事故の発生した場合に、保険者が保険金受取人に対し、約定の一定金額を支払うことを約し、保険契約者がこれに対し保険料の支払をもって酬いる契約のことを言います。
一見すると、生命保険金も被相続人の財産のように感じられる為、当然に遺産分割の対象に含まれるように思えます。しかし、保険契約者が自己を被保険者(被相続人)とし、相続人中の特定の者を保険金受取人と指定した場合、指定された者は「固有の権利」として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象とはなりません。 その結果、「会社の後継者となる長男に株式を譲渡する際の買い取り資金を準備してあげたい」、「二男が障害を抱えているので、生活費として援助してあげたい」、「長女が自分の介護を担ってくれたので、その恩に報いたい」などといった被相続人のご意向を、柔軟に叶えることが出来るようになります。
もっとも、生命保険金は、上述のとおり、被相続人の財産を不平等に分配する形になる為、生命保険契約において受取人と指定された一部の相続人が生命保険金を受領した場合、これが「特別受益」(なお、特別受益については本紙22号コラム「遺産分割の諸問題①~特別受益と寄与分~」をご参照ください)となるかが問題となります。
結論から申し上げますと、最高裁判所は、原則として「保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない(特別受益には当たらない)」という判断を示しています(最決平成16年10月29日・判例タイムズ173号199頁)。
ただし、上記判断において、最高裁判所は、同時に「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判断しており、一定の場合に特別受益に当たる場合があることを認めています。上記「特段の事情」の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断されることになります。
いずれにしても、生命保険金と遺産分割の問題は法律上の専門的な問題が複雑に絡んできます。今後、相続対策として生命保険を検討される方は、遺産分割案件を多数取り扱っている当事務所にご相談ください。
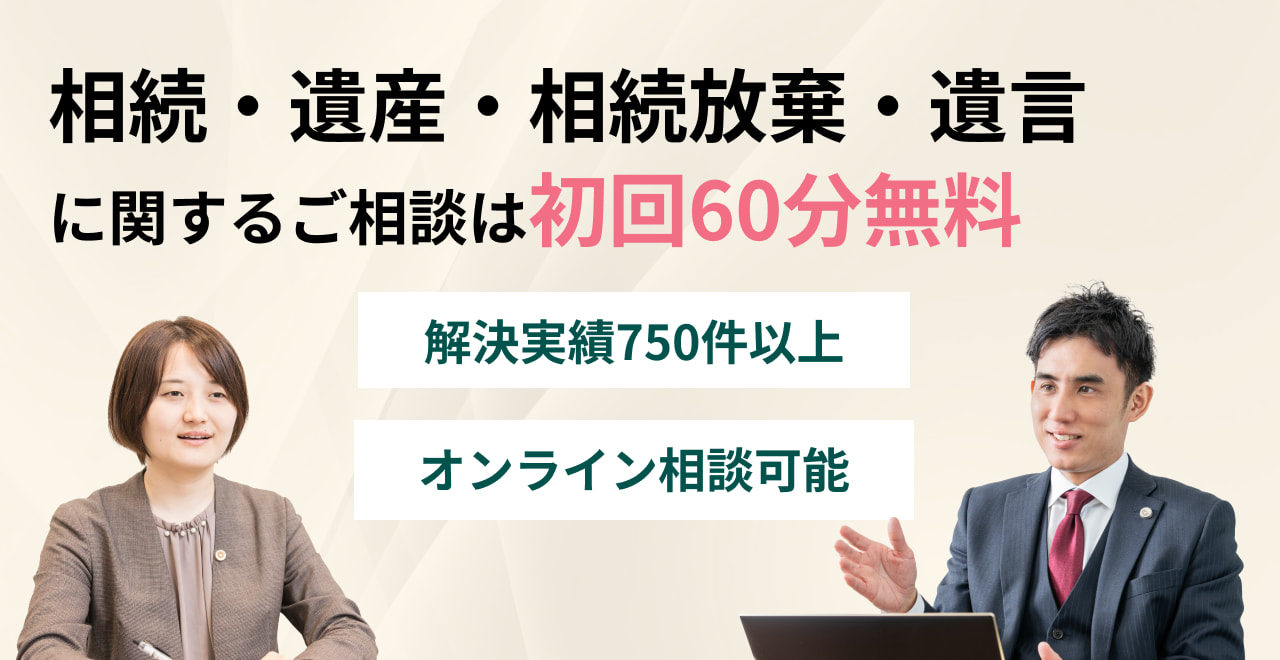
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。
関連するコラムはこちら
遺留分はいつまで請求できる?時効の基本と今からできる対策を徹底解説
相続の場面では、「長男が全財産を相続してしまった」「後妻だけが多く取得した」といった納得しづらいケースが少なくありません。法律上、一部の相続人には最低限の取り分が存在しますが、その権利を行使するには期限があります。期限を逃すと主張が通らず、もう取り返せない展開になりやすいです。 まずは「遺留分」とは何か、そして「いつまで主張できるか」を確認しましょう。 特に「1年」「10年」「5年」といった数字が重要になります。相続が開始して期間が経過している場合でも、まだ請求できる可能性はゼロではありません。早く判断して動くことで後々の後悔を減らせます。 以下の項目では、遺留分の基礎から請求期限、時効のしくみ、実際の交渉の進め方や内容証明の活用などをまとめます。法律の知識があまりない方でも読みやすいように意識しています。兄や後妻と正面から対立したくない人や、相続の手続きに時間を取れない人にとって、少しでも迷いをなくす参考になれば幸いです。 「遺留分って、いつまで請求できるの?」 「兄が全部相続したけど、本当に自分には何の権利もないの?」 そんな疑問を持った方に向けて、この記事では次のような内容をお伝えします。 遺留分を請求できる期限はいつまでか 「遺留分の侵害を知った時」とは何を基準にするのか 時効を止めるために必要な書類と正しい手続きの流れ 遺留分請求には法律で定められた消滅時効・除斥期間が存在し、請求できる期限が明確に決まっています。相続が始まってからの年数や、遺言を知ったタイミングによっては、もう請求できない可能性もあります。 とはいえ、「もうダメかも」とあきらめるのは早いかもしれません。判断の分かれ目になるポイントを押さえれば、自分の権利を守れるケースもあります。 家族と揉めたくないけど、不公平には納得できない。そう思っている方も多いですよね? この記事を読むことで、自分がまだ遺留分を請求できるのかが見えてきます。そして、今すぐ取るべき行動もはっきりしてきます。 読み終えるころには、「損をしないための一歩」を踏み出せるようになっているはずです。 遺留分請求の期限はいつまで?時効の起算点・注意点・今すぐ取るべき対策を徹底解説をしますので、ぜひ、最後まで読んでみてください。 遺留分とは?相続人の権利として知っておきたい基礎知識 遺産の配分では、被相続人が自由に決められるだけでなく、特定の相続人に最低限保証される取り分があります。これを遺留分と呼びます。例えば「亡くなった父が遺言書で長男だけに家や預金を全て譲ると書いている」ときでも、ほかの相続人に遺留分が認められる場合があります。 遺留分が認められる相続人とは まず誰がその権利を持つかを押さえます。 配偶者 子ども(実子・養子も含む) 孫などの直系卑属(子どもが先に亡くなっている場合) 父母などの直系尊属(子どもや孫がいない場合) 兄弟姉妹には遺留分はありません。例えば「自分は次男だが、後妻が全部を持って行った」といった場面でも、配偶者や子どもであれば主張できる可能性があります。 遺留分侵害額請求と減殺請求の違い 以前は「遺留分減殺請求」という制度があり、財産そのものを取り戻す方法が認められていました。法改正にて「遺留分侵害額請求」に移行し、侵害された分を金銭で取り返す手続きとなりました。不動産が絡む問題や第三者に渡った財産があっても、金銭を支払ってもらう形で解決しやすくなっています。 遺留分は「金銭請求中心」へ|法改正で何が変わったか? 2019年の民法改正で「減殺請求」から「侵害額請求」に移り、財産の直接返還より金銭補償が優先されるようになりました。不動産や株式などを巡る複雑な争いが簡略化しやすくなりましたが、遺留分の請求に期限がある点は変わりません。相続が始まって長期間が経つと「もう手遅れだった」という事態になりやすいです。 まず確認!遺留分の請求期限を整理|早見表とフローチャート付き 権利があっても期限を越えると請求できなくなります。以下のポイントを押さえましょう。 【早見表】あなたの遺留分はまだ請求できる? チェック内容 期限 注意点 親が亡くなった日からどれほど経過しているか 10年 相続開始日から10年過ぎると権利が消える 侵害を知ってからどれほど経過しているか 1年 遺留分が侵害されていると気づいて1年過ぎると請求できない 交渉後の金銭債権の時効 5年 和解や判決後に支払いが滞ると5年の消滅時効が進むことがある 【チャート式】請求期限の判断フロー 被相続人が亡くなった日はいつか 10年を超えているなら難しい 10年以内ならば、侵害を知った日を確認 知った日から1年を過ぎていないか 1年以内なら請求の余地あり 相続が始まって5年以上経っていても、侵害を具体的に知ったのが最近なら、まだ1年以内に収まる可能性があります。 判断に迷ったらどうすればいい? 戸籍謄本で被相続人の死亡日を正確に確かめる 遺言書やメモ、メールの送受信でいつ侵害を把握したかを確認する 法律相談で具体的な状況を伝えて、時効との兼ね合いを見てもらう 期限を思い込みで判断して諦める人もいます。詳しい資料をそろえて検討し、手遅れになる前に行動するほうが安心です。 遺留分請求には3つの時効がある|1年・10年・5年の違いを正しく理解 1年と10年に加えて、請求後に発生する5年の時効も意識したほうが安全です。 1年の消滅時効|「遺留分の侵害を知ったとき」からカウント 「兄がすべての遺産を相続した」と最近になって相続開始および遺留分侵害の事実を知った場合、その日から1年以内に行動しなければ時効が完成します。例えば父の死後3年経って初めて遺言書を見つけた際は、そこから1年以内に請求しないとアウトです。内容証明を送るなど、早めの形で主張しないと時効が進行します。 10年の除斥期間|「相続開始日」から起算 相続が始まった日から10年経ったら、遺留分はもう主張しづらいです。侵害を知ったタイミングが遅くても関係ありません。「親が亡くなってもうすぐ10年」と感じるなら急いだほうがいいです。 5年の金銭債権時効|請求後に生じる権利の時効 遺留分侵害額請求は金銭支払いを求める構造になっています。調停や裁判で金額が決まったあと、実際の支払いが行われないまま5年が経過することで、金銭債権が時効を迎える可能性があります。合意書や公正証書を作成して、滞納が起きたら再度請求の手順を踏むなど、定期的な管理が大切です。 時効ルールは法改正でどう変わった?過去との違いも解説 2019年の民法改正で「減殺請求」から「侵害額請求」に切り替わり、金銭請求が原則になりました。ただし、1年・10年という基本的な時間制限は前からあまり変わりません。実際には「侵害を知った日」がいつかをめぐって対立する場合が多いです。主観的な認識ではなく、客観的な証拠によって判断されることがあるので注意しましょう。 「時効の起算点」はいつ?|よくある誤解と実務判断の違い 1年の消滅時効は「侵害を知ったとき」からですが、その起算点がどこになるかで争いが起こります。 「知ったとき」の判断基準と注意点 相手から遺言書の内容や生前贈与の事実を知らされた日が基準になる場合が多いです。口頭で聞いただけだったり、知らされていないのに「勝手に気づいていたはず」と思われたりすると問題になります。メールの送受信や書面があると、時点をはっきり示しやすいです。 遺言の存在を知らなかった場合はどう扱われる? 兄が遺言書を保管しており、弟が気づかずに何年も過ぎた事例もあります。その場合でも、裁判では「本当に知らなかったのか」を厳しく見られます。実家から郵便物が届いていたかどうか、近所から連絡がなかったかなど、具体的な事情によっては「知ったとみなされる」展開もあるため要注意です。 起算点を証明するための資料とは(戸籍・通知書など) 被相続人の死亡日を示す戸籍謄本 遺言書の検認手続きの書面 口座凍結の連絡や遺産分割協議書のコピー 内容証明郵便の控え このような資料があると、いつから1年を数え始めるかを確定しやすく、実際の争いでは証拠として決め手になりやすいです。 よくある質問(FAQ)で疑問を先回り解決 相続が絡む問い合わせの中で、頻出する質問をまとめます。 口頭で伝えただけでも請求の意思表示になる? 法律上は口頭でも意思表示になります。けれど、後から「言ったのか言わなかったのか」で食い違う恐れが高いです。内容証明で送ると、発送日や内容がはっきり証明されます。時効中断を確実に狙うなら、書面を使うほうが無難です。 相手の住所がわからないときはどうする? 戸籍の附票で現住所を調べる 家庭裁判所で調停を申し立て、住民票を明らかにする 弁護士や役所を通じて情報を探す 住所が分からないままだと内容証明も送れません。期限が迫っているなら、まずは所在地の特定を急ぎましょう。 一度請求すればもう時効は止まるのか? 内容証明で請求すれば1年の消滅時効が中断される可能性があります。とはいえ、その後の交渉が何も進まず長期間放置すると再び問題が起きる場合もあります。交渉や合意の進み具合によって状況は変わりやすいです。 時効を過ぎてから請求された場合の対処法 「既に10年過ぎている」「1年を超えている」などの指摘がなされたら、まず本当に時効が完成しているか確認してください。起算点を誤解しているケースもあります。書類を突き合わせて明確化したうえで、必要に応じて専門家へ相談するのが安全です。 時効が絡んだ実際のトラブル事例と回避のポイント 現場では、時効のせいで権利を失ったり、思わぬ論点で対立したりする事例が見られます。 請求後に時効が進行していたケース 内容証明で請求して安心したものの、その後の交渉が停滞していたために追加の時効が完成してしまった事例があります。金銭を受け取るまで時間が空くと、5年の債権時効が進んでしまう恐れがあるからです。定期的に合意や支払いの状況を確認し、逃げられないようにしておくほうがいいです。 「遺言無効」の主張でも時効が止まらなかった事例 遺言無効を争っているあいだ、遺留分の請求を先延ばししていて時効を迎えた人もいます。無効かどうかは別問題で、遺留分の手続きはきちんと期限内に進めないとアウトになりやすいです。遺言自体を否定する場合でも、侵害額請求を並行して検討するほうが危険を減らせます。 後妻 vs 子ども…よくある対立構造 後妻が親の近くで介護していたケースで「財産管理を任され、父の預金を長い間自由に使っていた」といったトラブルが起こりがちです。放置しているうちに10年が経過すれば、権利を失う一方です。あまり感情を出したくないなら、弁護士を介してスムーズに協議を進めたほうが建設的です。 家族関係を壊さずに請求する方法はある? 文面を穏やかに書いた内容証明を使う 直接連絡を取りにくいなら、弁護士の名義で送る 金銭だけを請求する形なので、共有名義になる恐れが減る 親族内でもめたくないときは、冷静な書類のやり取りが有効です。 時効を止める正しい方法|内容証明郵便の書き方と注意点 時効対策としては、内容証明郵便で請求を通知しておく形が代表的です。郵便局の仕組みで書面の内容と発送日を証明してくれるため、言い逃れを抑えやすいです。 内容証明郵便の基本と送付方法 郵便局の窓口で「内容証明」を依頼する 同文を三通作成して押印(相手用・郵便局保管用・差出人保管用) 配達証明を付ければ相手が受け取った日も確認できる 文面は法律用語で固める必要はありません。いつ、誰に、何を請求するかをはっきり示すと伝わりやすいです。 請求先・財産・金額を明確にする書き方 宛名と住所を正しく書く どの財産が対象か(不動産や預貯金、株式など) 計算根拠(遺留分割合や評価額の内訳) 曖昧にせず、どれほどの金額を求めているかをきちんと提示しないと交渉が進まないです。 不適切な内容は無効扱いに?失敗しないためのチェックリスト 脅迫的な表現にしない 宛名や日付、請求内容に誤りがないかを再確認 署名捺印を忘れない 書面の不備でトラブルを招くと時間を浪費しやすいです。事前に下書きを作ってチェックするほうが安心です。 複数の請求先がいる場合のポイント整理 例えば親が再婚しており、後妻とその子どもが相続人になっているときは複数宛の請求が考えられます。それぞれに内容証明を送るか、代表者を決めて一括で送る形もあります。相続財産の全体像や法定相続分を把握したうえで、誰が何をどれだけ負担するのかを洗い出してから動くのがスムーズです。 遺留分請求の実務的な流れ|交渉から裁判までの全ステップ 全体像を把握しておくと、どの段階でどんな動きをするか計画を立てやすいです。 ステップ1:内容証明での意思表示 まず郵送で「遺留分を請求する」という事実を伝えます。相手が応じるなら、そのまま和解へ進む場合もあります。無視されたり拒否されたら、次の段階へ進行します。 ステップ2:当事者間の交渉 電話や文書のやり取りで金額や支払い方法を交渉しなくてはいけません。話し合いが困難な場合や、感情的となる場合には弁護士を入れて冷静に整理すると進展が見込めます。日ごろ忙しい人は無理に直接交渉せず、早期に依頼をしましょう。 ステップ3:合意書・和解書の締結 話し合いがまとまったら、書面化して署名捺印します。公正証書にすると相手が履行しない場合に強制執行がしやすいです。支払い時期や分割条件を具体的に定めておくと安心です。 ステップ4:調停・訴訟の申し立て 話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停や裁判所での訴訟に進みます。時間と費用はかかりますが、第三者が入って解決策を探すかたちなので、平行線を脱するには有効です。時効が切れる前に申し立てる必要があるため、余裕がないなら早めに検討してください。 弁護士に相談すべきタイミングと判断基準 自力で進めるか、専門家に任せるかで迷う方は多いです。費用との兼ね合いもあるため、状況を踏まえて決めましょう。 「時効ギリギリかも」と思ったら相談を急ぐべき理由 期限が近い段階で慌てると、書類作成や相手の住所調べなどに手間取ります。弁護士なら対応手順を素早く指示できるため、時効が完成する前に間に合わせやすいです。独力で遅れると取り返しがつかない恐れがあるので注意してください。 費用と対応範囲の目安|すべて任せたい場合の考え方 弁護士費用は請求金額や事件の内容によって変わります。着手金や成功報酬を合わせると負担はある程度かかりますが、得られる遺留分のほうが上回るなら検討に値します。裁判や調停の手配、書面作成、相手への連絡などを一括で頼めるのが利点です。 法律初心者でも安心して相談できる事務所選びのコツ 相続分野を扱う実績の多い専門家を探す 初回相談が無料の事務所を候補にする 電話やメール相談だけでなく、直接面談で丁寧に説明してもらう 見積りを先に出してもらい、費用を明確化する 疑問を率直に伝えられる弁護士なら、相続や遺留分が初めての人でも安心しやすいです。 自分の請求が通るか?を事前に見極めるには 戸籍や遺産目録があると計算が進みやすいです。さらに、相続開始日や侵害を知ったときの把握時点を明らかにしておけば、弁護士が時効との兼ね合いをスムーズに判断します。「請求できるか微妙」と思っても、専門家の視点では可能性があるかもしれません。迷ったら早めに確認を進めましょう。 まとめ|遺留分を請求するなら「今すぐ動く」が鉄則です 相続分の不公平を解消したい人は、期限を過ぎる前に着手するのが要です。周囲に遠慮しているうちに10年が過ぎると、遺留分は消えます。 「迷っているうちに時効」は実際によくある話 「後妻と口論は嫌だ」「兄と絶縁は困る」と思い、先延ばしにしていると手遅れになりやすいです。あとで「あのとき請求しておけばよかった」と後悔する例が多々あります。 請求の可否と期限はまず確認することから 相続が始まった日と、侵害を知ったタイミングを確実に把握して、1年や10年に該当しないかを最優先でチェックしてください。戸籍謄本や遺言関連の書面を集めるところから着手しましょう。 不安な場合は早めの相談で後悔しない選択を 家族との衝突が心配でも、期限切れになるともう取り返せません。逆に、初動をきちんとすれば家族関係を深刻にこじらせずに解決できる可能性があります。迷いがある方は、できるだけ早く弁護士などの相続専門家に相談し、自分の権利を守る最適な方法を確認しましょう。 この記事のまとめ 遺留分の請求には、「知った時から1年」「相続開始から10年」「請求後の金銭債権は5年」の3つの期限があります。 「知った時」とは、相続開始と遺留分侵害の両方を知った日を基準に判断されます。 内容証明郵便で意思表示を残すことで、時効を止めることが可能です。 時効が成立しているか不安な場合は、早めに確認・相談するのが安全です。 行動のすすめ 「まだ間に合うかも」と感じた方は、今すぐ時系列を整理して、請求の可否を確かめてみてください。不安があれば弁護士に相談することも検討しましょう。証拠の準備や書類の書き方についても、早めの対処がトラブルを防ぐ鍵になります。 さいごに 遺留分侵害額請求は、法律で認められた正当な権利です。気まずさや迷いがあっても、一歩踏み出すことで損を防ぐことができます。自分の立場や気持ちに折り合いをつけるためにも、行動するタイミングを逃さないようにしましょう。
2025.07.09
new
遺産分割と相続税の完全ガイド|未分割申告・修正申告・節税まで徹底解説
「相続税の申告期限まであと三か月なのに兄弟と連絡が取れない…どうしたらいい?」「未分割のまま申告したら税金を払いすぎないか心配」と悩んでいませんか。 この記事でわかること 未分割申告を期限内に済ませる五つの手順 修正申告・更正の請求で税金を取り戻す流れ 控除と特例を逃さず分割をまとめるコツ 結論としては、まず相続税の申告期限を厳守し仮申告を行い、遺産分割成立後に特例適用を回復するのが賢明です。これにより延滞税や無申告加算税を回避しつつ、控除や特例の恩恵を最大限活かせます。 家事や仕事で忙しい中、相続まで抱えるのは大変ですよね? この記事を読むことで、必要な書類やスケジュールがひと目でわかり、不安が減りスムーズに手続きを進められます。 【2025年最新版】遺産分割と相続税の完全ガイド|未分割申告・修正申告・節税対策までわかりやすく解説します。 1章 遺産分割と相続税の全体像を3分で把握 申告・納付までのタイムライン(死亡日→10か月)とペナルティ早見表 死亡日(0日)…相続開始 7日以内…死亡届を提出 4か月以内…準確定申告(個人の所得税) 10か月以内…相続税の申告・納付 10か月+1日以降…延滞税(年2.4~9.6% ※毎年国税庁告示により変動) 無申告の場合…無申告加算税5~20% ポイント:遺産分割がまとまらなくても、10か月という「時計」は止まりません。まずは期限を死守し、後から修正・更正で調整するのが王道です。 申告・納付までの流れ 死亡日を起点に10か月で相続税の申告と納付が完結しなければ延滞税の対象になります。延滞税率は年2.4〜9.6%で毎月加算されます。無申告の状態が続くと無申告加算税(5〜20%)も課されます。期限を越えた申告が「税額は同じでも不利益だけ増やす」仕組みを理解しましょう。 最初の二週間で戸籍収集と財産リスト作成に着手した家族は、期限内申告をほぼ達成しています。逆に一か月以上放置した家族は、相続人の意思疎通に時間を奪われがちです。タイムラインを可視化し、各タスクを逆算配置することで迷いが減ります。 基礎控除と法定相続分 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します(相続税法21条の3)。配偶者と子二人なら4,800万円が課税ラインです。課税対象額が基礎控除を下回れば申告義務も納税義務も生じません。 法定相続分は民法900条に定められています。 配偶者のみ:100% 配偶者と子:配偶者2分の1・子2分の1 子のみ:子全員で均等 配偶者と直系尊属:配偶者3分の2・尊属3分の1 遺産分割が長引く五つの要因 相続財産の全体像が把握できず評価が遅れる 相続人の所在不明や連絡不通 不動産・自社株など分割困難な資産が多い 生前贈与や名義預金の処理が不明瞭 介護負担の偏りや長男・長女への遺産配分不満など感情的対立 親族が調停に持ち込む前に、期間を区切った協議とタスク管理表の共有を勧めます。 遺産分割とは?協議の流れと三つの方法 現物分割:そのまま引き継ぐ。評価差が出やすい。 代償分割:取得者が他相続人へ金銭で補填する。資金計画が鍵。 換価分割:売却して現金で按分。不動産売却益に課税。 現物分割よりも代償分割や換価分割の方が相続税の課税額を抑えられるケースが多いです。節税の可否は控除適用状況によるため、弁護士・税理士との事前試算を強く推奨します。 2章 まずは期限を守る!未分割申告と仮納税の完全手順 STEP1 課税価格の仮計算 戸籍一式と財産目録を基に法定相続分で案分した金額を出す。評価は路線価・倍率・残高証明・株価平均など公的資料に限定し、将来の更正へ備えて保存する。 STEP2 配偶者控除・小規模宅地等特例など相続税控除・特例の適用可否を整理 配偶者控除や小規模宅地等特例は分割完了が条件になるため、未分割申告では使えない。適用予定の控除を列挙し、「後日回復」欄を付けておくと修正計算が楽になる。 STEP3 必要書類をミニマムで準備 相続税申告書第一表 財産評価明細書 戸籍謄本一式 相続人代表者指定届 書類不足で受理が遅れると延滞税が加算されます。遺産分割協議書は未完成でも申告書自体は提出可能です。 STEP4 納税資金の確保 現金納付:預金の解約が最速 延納:5年(利子税1.6%)または10年(同3.6%) 物納:国庫が受け入れる資産に限る 延納利子は国税通則法完納基準割合に連動し、2024年以降上昇傾向にある。 STEP5 税務署へ申告・納付 提出先は被相続人住所地を管轄する税務署です。電子申告も対応していますが署名用電子証明書の取得に十日ほど要します。郵送申告の場合は消印日が提出日扱いとなります。 未分割申告のメリット・デメリット メリット デメリット 期限内申告で加算税を回避 控除・特例は後日回復 納税資金を先に確保できる 修正・更正の手続きが増える 3章 遺産分割成立後に行う修正申告・更正の請求 判断フローチャート 仮納税額より本来税額が高い→修正申告 仮納税額より本来税額が低い→更正の請求 期限・書類・手数料 区分 期限 主な書類 手数料 修正申告 法定申告期限から5年 修正申告書・計算明細書 0円 更正の請求 同左 更正の請求書・証拠資料 0円 小規模宅地等特例と配偶者控除の回復 相続税法69条の4で「申告期限後3年以内に分割した宅地」に限り特例を遡及適用できます。配偶者控除は同法19条の2が根拠となります。分割協議書原本及び不動産の登記事項証明書等を添付し、税務署の審査を経て相続税の還付金が振り込まれます。 4章 遺産分割パターン別の節税&資産最適化プラン 三つの分割方法の税務比較 現物分割:登録免許税と不動産取得税が個別に発生 代償分割:譲渡所得税が発生しない反面、贈与税の二重課税に注意 換価分割:譲渡所得税15.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)が課税 評価・控除テクニック 路線価評価と倍率方式を比較し低い方を採用する 非上場株は類似業種比準価額または純資産価額で試算し、議決権調整を施す 取得費加算で相続税を譲渡所得の取得費へ加算し、課税所得を圧縮する 二次相続シミュレーション 配分 一次納税額 二次納税額 総額 配偶者60%・子40% 減少 増加 やや増 配偶者40%・子60% 中程度 中程度 最適 子100% 増加 0円 増 数字はモデルケース。配偶者の生活費と子のライフプランを加味して決定してください。 5章 必要書類・チェックリスト・スケジュール逆算表 協議書が不要になる四条件 相続人が一人 遺産が預貯金のみ 公正証書遺言に沿って分割 法定相続分で分ける意思が一致 提出書類チェックリスト 相続税申告書第一表 財産評価明細書 遺産分割協議書 印鑑証明書(相続人全員) 戸籍謄本一式 ガントチャート運用 相続税申告の進行管理には、ガントチャート形式のタスク管理表を活用すると効果的です。PDFに色分けしたタスク表を配置し、期限別で赤→橙→緑に変化させると進捗が直感的に追えます。 6章 トラブルを防ぐ交渉・調停マニュアル 連絡不通・精神障害相続人への対応 内容証明郵便で相続協議の交渉期限を通知し、返答が無い場合は、家庭裁判所への調停申立てを検討します。精神障害が認定された相続人には、後見人や保佐人の選任申立てを進めます。遺産分割調停に発展した場合、本人能力を補完し手続きを進める効果があります。 調停・審判の概要 申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 平均所要時間は、調停の場合は6〜12か月、審判の場合はプラス3〜6か月です。 寄与分・特別受益が争点になった場合の整理手順 医療費の領収書、介護日誌、送金の履歴などを数値化した資料を用意した 各相続人へ送付し、認否を議事録に残した 結果を調停申立書や主張書面にて主張し、調停調書へ反映した 7章 ケーススタディで学ぶリアルな対処法 ケース 財産情報不明×連絡拒否 叔父の遺産で通帳を持つ代襲相続人が情報開示を拒否した。法定相続分で未分割申告し、家庭裁判所経由で金融機関に照会をした。その結果、残高が判明し、修正申告を実施した。延滞税は発生しなかった。 8章 よくある質問 未分割申告後に更正の請求はいつまで? 原則相続税の申告期限から5年ですが、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内の「更正の請求」という別の時計も動きます。 配偶者控除が使えなかった場合の救済策は? 3年以内の分割特例を活用し、更正の請求で還付を受けます。 税務調査で否認されやすいポイントは? 名義預金、過小評価、不記載資産など。証拠書類の網羅的な保存が防波堤になります。 9章 まとめ|期限内申告+後日修正で“損しない相続”を実現 10か月の申告期限を守れば延滞税と無申告加算税を防げる 控除や特例は後からでも回復可能 分割方法と二次相続まで見据えた設計が節税の核心 記録保存と速やかな専門家相談がトラブル防止の近道 相続手続きは期限と段取りがすべて。相続税申告期限内の対応と遺産分割の適切な進行管理が、家族の資産と安心を守る第一歩です。ぜひチェックリストを活用し、家族ごとの工程表を作成されてみてください。
2025.07.09
new
相続土地国庫帰属制度とは?条件と注意点を弁護士が解説
1. 相続土地国庫帰属制度とは? 相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地の所有権や共有持分を、一定の要件のもとに国庫へ帰属させる制度です。この制度は、山林や原野などの資産価値が低い土地が「負の遺産」として放置され、所有者不明土地が増える事態を防ぐ目的で導入されました。法務大臣(法務局)の審査・承認を受け、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することで、当該土地を国庫へ帰属させることができます。 10年分の土地管理費相当額と聞くと負担が大きく感じられるかもしれませんが、田畑や原野は面積にかかわらず20万円、森林については面積に応じて算定され、例えば1000㎡ほどの広さがある場合、約48万円となります。 2. 国庫に帰属させられない土地の条件 国庫に帰属させることができない土地として、以下のような条件が挙げられています。 • 建物が存在する土地 • 担保権等が設定されている土地 • 一定の勾配・高さの崖がある土地 これらの条件に該当する場合、本制度を利用することはできません。 3. 遺産分割における相続土地国庫帰属制度の活用 本制度を活用することで、遺産分割における選択肢が増えます。特に、資産価値が低く管理が難しい森林などの土地は、遺産分割の際に紛争の原因となることが多くありました。 従来は、誰も取得を希望しない土地を共有名義で相続登記することで問題を先送りするケースが見られました。しかし、本制度を利用すれば、相続財産から負担金を支出して問題を解決することが可能になります。 また、本制度は法施行前に相続等によって取得した土地も対象となります。そのため、土地の帰属をめぐって遺産分割協議が進んでいない場合でも、本制度を活用することで解決を図ることができる可能性があります。 4. 相続土地国庫帰属制度を利用する際の注意点 本制度のメリットを述べてきましたが、注意が必要な点もあります。 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産を取得した相続人等は、取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられます。正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 相続登記の義務化は遡及適用されるため、相続未了の土地を所有している場合は、特に注意が必要です。 5. まとめ 相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の増加という社会問題への対応として制定されました。資産価値の低い土地の処分が可能になる一方で、相続登記の義務化により、手続きを怠ることはリスクとなる点も認識しておく必要があります。制度の内容を理解し、適切に活用することが重要です。
2025.02.03
new
相続の考え方
生を受けた人間全員にとって唯一公平に与えられているのは、「死」という概念だと思います。人間の世界は、法という目に見えない“磁場”に縛られており、法律の定める条件に触れることで「権利」や「義務」といった目に見えない概念が変動しますが(通常「権利変動」と呼びます。)、人の「死」もまた、法が定める権利変動原因の一つです。 人は「死」によって、権利・義務の一切を失い、他方、その配偶者や子が、死者(相続される人という意味で「被相続人」と呼ばれます。)の権利・義務の一切をそのまま引き受けることになります(「そのまま」という点を指して、「包括承継」と呼ばれます。)。こうした「死」によって生じる権利変動を「相続」と呼びます。 相続は、人の「死」によって発生します。「相続人」という法が定める相続資格者が相続を原因として被相続人の財産(権利・義務)を取得するのですが、誰が相続人の地位に就けるかは、法が細かく規定を置いています(配偶者は常に相続人となりますが、①子・②直系尊属・③兄弟姉妹は、①~③の順で優劣が付けられており、劣後者は優先者不存在のときでなければ相続人となれません。)。また、相続人は必ずしも1人ではないため、人数と性質(配偶者なのか、子なのか、直系尊属なのか、兄弟姉妹なのか)によって遺産の取得割合(相続分)が変わります。 以上のとおり、人が亡くなった場合、その死者の遺産の分配を決めるため、まずは戸籍を集めて相続人が誰なのかを確定し、その後に、各法定相続人の相続分を確認することとなります。次に、この法定相続人の間で死者(被相続人)の遺産をどうやって分割するかを話し合わなければなりません。これが「遺産分割協議」という手続です。遺産分割協議は、必ずしも裁判所等の機関を通じる必要はなく、私的に行えば有効となります。 ただし、私的な話合いでは話がまとまらず物事が決まらないこともよくあります。そうしたケースでは、家庭裁判所に対して遺産分割調停や遺産分割審判を申立て、問題解決のために裁判所の力を借りることができます。 遺産分割協議を経なければ、具体的にどの財産を誰が相続するかが確定しないため、預金を銀行から引き出すことや、法務局で不動産の移転登記を行うことができません。遺産分割協議を行わず、物事をほったらかしにしていると、預金が凍結されたままとなり、古い不動産登記が残ったままとなりますが、そうこうしているうちに、相続人が一人また一人と亡くなり、相続の連鎖によって関係者が複雑多数化し、問題の解決が困難となりがちです。 ある程度の財産をお持ちの方がお亡くなりになった際は、放置せずに速やかに必要な調査や分割協議を進める必要があるのです。
2019.04.28
new
相続と生命保険
弁護士の茂木です。 先月、2回程、保険代理店様向けに相続に関するセミナーをさせて頂きました。 遺言や遺留分の話から、特別受益や寄与分のお話まで、幅広くさせて頂きました。 特に、今回は生命保険を取り扱っている方が相当数いらっしゃいましたので、相続と生命保険の関係についてもお話させて頂きました。 生命保険は遺産相続の対象となるのか? 答えはNOです。 生命保険はあくまで保険契約に基づく固有の権利として受取人に指定されている者が保険請求権を行使することが出来ます。 この取扱いを利用して、保険代理人側においても色々と営業に生かすことが出来るようです。 内容が気になる方がいらっしゃれば、当事務所までご連絡下さい。
2015.06.01
new
遺留分
弁護士の茂木です。 突然ですが「遺留分」という言葉をご存知ですか。 遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です 簡単にいうと、被相続人が遺言等によってAという相続人に全ての遺産を相続すると定めていたとしても、Bという相続人は一定の割合について遺産から遺留分を承継することが出来るという制度です。 被相続人が亡くなった後、遺言を開けてみてビックリ仰天、「自分には何も相続させないことになっている。」そんなときは慌てず、遺留分の請求をする方法が考えられます。 自分の相続分が全く無いと思ってしまっている方は、まずは一度当事務所にご相談下さい。
2015.03.18
new
寄与分
弁護士の茂木です。 前回は相続に関して「特別受益」という点を御説明させて頂きました。今回は「寄与分」について御説明させて頂きます。 「自分は親の近くにいて最後まで親の面倒を見てきたんだから、他の相続人よりも多く取り分があるはずだ。」 このような御相談を受けることがあります。法律上は「寄与分」の主張にあたると考えられます。 民法904条の2第1項は寄与分について以下のとおり定めています。 「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」 法律上、寄与分の主張が認められる為には「特別な寄与」である必要があります。 「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があるとされています。 つまり、単に身内として介護しているだけでは足りないと判断される傾向にあります。 遺産分割手続きにおいて寄与分を主張される場合、あるいは相手方が寄与分を主張してきている場合は、一度、当事務所に御相談に来られてはいかがでしょうか。
2015.03.03
new
特別受益
弁護士の茂木です。 遺産相続の問題を取り扱う際、よく問題となるのが 「相手方が被相続人の預貯金等を、被相続人の生前に勝手に引き出している」 という問題です。 遺産分割協議や遺産分割調停においては、このような引出行為がいわゆる「特別受益」に当たると主張することが多いです。 しかし、特別受益は、法律上、 「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」ことが必要となり、これらに該当しない場合は特別受益と判断されません。 実際、裁判所において特別受益の主張を行ったとしても、余程の証拠や、遺産の総額と比べて極端に不公平な取り扱いが為されていない限り、特別受益の主張は認められない傾向にあります。 最終的に、このような使途不明金については遺産分割調停ではなく、不当利得返還請求訴訟で争わざるを得なくなりますが、証拠が不十分な場合が多く、困難な闘いを強いられることが多いです。 後々、このような争いにならない為にも、被相続人の生前にしっかりと意思を確認し、事前に遺言等を準備しておくなどの供えをしておくことをお勧めします。 弁護士法人グレイスでは相続についても集中的に取り扱う家事チームがございます。 ご心配な点がある際はいつでもお電話ください。
2015.02.12
new
遺産分割の諸問題(8)預貯金は遺産分割の対象となるのか
さて、今回は番外編です。2014年12月号の家事コラム「遺産分割と遺言」~事前の準備が大切です~の回で、「預貯金等の金銭債権は、遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に法廷相続分に応じて帰属するとされており(判例)、遺産分割の対象財産とはなりません」と記載させていただいたことを覚えていますか。 全国ニュースや新聞(全国紙)でも取り扱われていた為、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この度、上述の判例(以下「旧判例」といいます)が最高裁判所において変更されました(最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定、以下「新判例」といいます)。 新判例は以下のように述べています。 「遺産分割の仕組みは、被相続人の権利義務の承継に当たり共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、一般的には、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく、また、遺産分割手続を行う実務上の観点からは、現金のように評価の不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在する」。そして、「預貯金は、預金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産である」。このような「各種預貯金債権の内容及び性質をみると、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」。 そもそも、旧判例による「預貯金が遺産分割の対象とならない」という取り扱いの方が、一般の方には理解し難いところだったのではないでしょうか。多くの方の場合、不動産を除けば預貯金が相続財産の多くを占めることとなり、預貯金を遺産分割の対象としないのであれば、一体何を分割すれば良いのかということになりがちです。通常は、相続人全員が、預貯金を遺産分割の対象とすることに同意の上、相続人間の調整をしていくのですが、稀に同意が得られない場合、預貯金を遺産分割の対象から外し、その余の遺産についてのみ分割協議をしていくこととなります。 特に旧判例では、共同相続人の1人が、被相続人から生前に多額の生前贈与を受け取っていたとしても、同相続人が預貯金を遺産分割の対象とすることに同意しなければ、法定相続分に応じた預貯金を当然に取得することができます。その結果、他の相続人からすると、著しく不公平な状況になるのみならず、同じ被相続人の財産でありながら、預貯金とそれ以外の遺産で取り扱いや手続が異なることとなり、過大な負担を強いられることとなります。 この点、新判例によれば、そのような状況下でも、当然に預貯金が遺産分割の対象となる為、上述の事例でも、場合によっては生前に多額の贈与を受け取っていた相続人は、預貯金を一切受け取れないといった処理も柔軟に取られることとなります。 以上のとおり、新判例は今後の遺産分割実務の進め方を大きく変えていくことになる画期的なものとなっております。遺産分割を有利に進めていく為には、このような変わりゆく判例の情報を常に仕入れ、アップデートしていくことが不可欠です。 預貯金の遺産分割でお悩みの方は、最新の判例事情にも明るい当事務所に一度ご相談ください。
2017.01.25
new
遺産分割の諸問題(7)実際の遺産分割協議の進め方②
さて、前回から実際の遺産分割協議の進め方についてお話させていただいております。前回は、裁判所を利用せずに当事者同士、又は弁護士を通じて遺産分割協議を行っていく方法についてお話させていただきました。 一般的に裁判所に申立てをすることは心理的なハードルも高く、出来ることなら裁判所を利用せずに穏便に協議で話をまとめたいと考えられている方が殆どでしょう。もちろん、当事者が少なく、かつ、当事者がいずれも協力的である場合は協議でまとまる可能性も高く、比較的迅速に解決することもあります。 しかし、実際には協議で行う場合は、相続人の人数に関わらず、相続人全員が協議内容に合意し、遺産分割協議書に署名捺印をしなければ解決にいたりません。例えば、20人の相続人の内、19人が同意していたとしても、最後の1人が反対しているような場合は協議がまとまらないことになってしまいます。このような場合は、いたずらに時間が経過することとなり、時にはその間に相続人の誰かが亡くなることで更に相続人が増えていくといった事態も考えられます。 その為、相続人が多い場合や、相続人の一部が非協力的である場合などは、早々に遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。遺産分割調停は、他の調停と同様、調停委員を通じて裁判所で行うお話合いです。しかし、お話合いが成立する見込みの無い場合は、それまでに提出された資料等に基づき、裁判所が「審判」という形で最終的な解決方法を提示されます。その為、調停を行ったにもかかわらず、何も決まらなかったという事態は殆ど生じません。多くの遺産分割に関わる問題は、このような遺産分割調停・審判の中で解決されていくことになります。 もっとも、何点か遺産分割調停・審判の中でも解決できない問題があるので注意が必要です。典型的なのは、使途不明金がある場合です。相続人の内の誰かが被相続人が亡くなる前後に預貯金等を引き出していた場合は、「不当利得返還請求訴訟」という形で通常の民事訴訟の中で解決を図らなければなりません。 また、遺言が作成されていた場合は、状況に応じていくつかの訴訟を使い分ける必要があります。認知症等によって意識が不明瞭な際に作られた遺言がある場合は「遺言無効確認訴訟」を、遺言無効を争うことは難しいが遺言で遺留分が侵害されている場合は「遺留分減殺請求訴訟」を提起しなければいけません。その他、遺言で不動産の相続が共有となっている場合は「共有物分割訴訟」という訴訟を提起することになります。 以上のように、当事者間の協議のみによって遺産分割が解決しなかった場合、多種多様な手段を検討し、状況に応じて最も適切な手段を選んでいかなければなりません。その為、非常に高度な専門知識と経験が不可欠となります。 当事務所では常時多数の遺産分割案件を扱っており、多くのノウハウが蓄積されております。当事者間での遺産分割協議に限界を感じられた方は一度当事務所にご相談ください。
2016.11.25
new