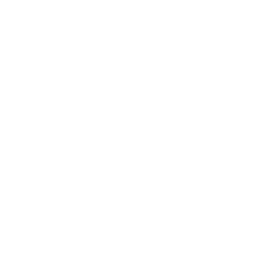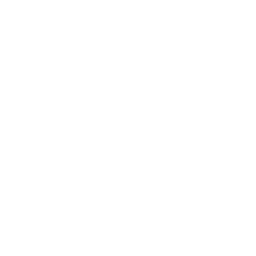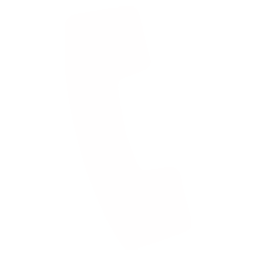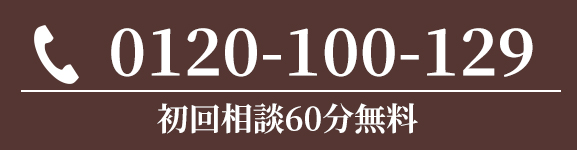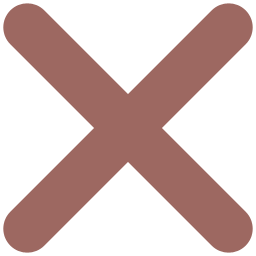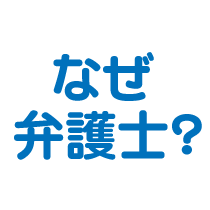相続放棄の前後でしてはいけないこととは?葬式代・遺産の処分・隠蔽等などの注意点について弁護士が解説
更新日:2025/01/22
1.相続放棄とは?概要を理解しよう
相続放棄という制度をご存じでしょうか?
相続放棄とは、ご家族が亡くなられた際に、相続財産も借金も含めて全ての相続権を放棄することができる制度です。例えば、生前に多額の借金を抱えている方が亡くなった際には、相続放棄をすることで、この借金を相続してしまう事態を回避することができます。逆にいえば、このような場合には、相続放棄をしなければ、自動的に相続人が借金も相続することとなってしまいます。
多くの方が誤解をされているのですが、相続放棄は、家庭裁判所にその申述の申立てをしなければ効力を生じません。ご家族が亡くなられた際に、他の親族に「私は相続放棄します。」と宣言しても、法的な効力は生じないのです。相続放棄が許される期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされていますから、自分が相続放棄を完了したものと誤解したままにならないよう、ご留意ください。
ちなみに、相続放棄を管轄するのは、被相続人が亡くなられた際の住所地を管轄する家庭裁判所となります。家族が遠く離れた地元に暮らしている場合などには、提出先の裁判所を間違えることのないよう、ご注意ください。
2.相続放棄前後にやってはいけないこと、注意すべきこと
さて、相続放棄の概要は以上のとおりですが、相続放棄前後にやってはいけないことを以下のとおりご紹介いたします。民法上、これらの行為があると、相続放棄がそもそもできなくなってしまう可能性がありますから、特にご注意ください(民法921条)。
2-1.相続の意思がないのに相続放棄の手続を忘れる
第一に、相続の意思がないのに相続放棄の手続を忘れることがあってはなりません。
上述したとおり、相続放棄期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています。この期間制限は厳しく、若干の例外的な場面を除いて認められません。例えば「相続放棄があったことを知らなかったため遅れた。」といった理由では相続放棄期間が伸長されることはほとんどないでしょう。
このため、亡くなったご家族に借金があるなどの理由で相続の意思がないのであれば、相続放棄手続を忘れずに行わなければなりません。相続放棄をするべきか悩んだ場合には、早急に弁護士にご相談ください。
2-2.相続財産の処分
第二に、相続財産の処分をすることがあってはなりません。ここでいう「処分」とは、文字通りの意味の廃棄等の処分のほか、売却・譲渡・贈与なども含みます。
相続放棄をする場合には、相続人としての地位を失いますから、プラスの資産もマイナスの負債もどちらも取得することができなくなります。このように、亡くなった方の相続財産に対する権利も義務も負わなくなる以上は、相続財産の処分をする権利もありません。
もし、相続放棄手続の前に相続財産を処分してしまった場合には、相続を承認したものとして、相続放棄が認められなくなる可能性があります。また、相続放棄手続の後に相続財産を処分してしまった場合には、他の相続人に権利がある財産を勝手に処分してしまうことになりますから、窃盗・器物損壊・横領などの犯罪が成立する可能性があります。いずれにせよ、相続放棄をするのであれば、相続放棄前後に、相続放棄を処分してしまってはいけないのです。
2-3.相続財産の隠蔽・消費
第三に、相続財産の隠蔽・消費もしてはいけません。
上記のとおり、相続放棄をする場合には、相続財産に対する権利も義務も負わなくなります。これにもかかわらず、相続財産の隠蔽・消費をすると、やはり相続放棄前であればその後の相続放棄ができなくなる可能性があり、相続放棄後であれば犯罪が成立する可能性があります。
相続放棄をするかもしれないなとお悩みの場合には、亡くなったご家族の財産に一切手を触れず、何もしない方が無難なのです。結果的に相続放棄をしないで相続をする選択をとるにしても、慎重な対応をして損はないでしょうから、相続財産を隠蔽・消費してはならないということを念頭に置いておきましょう。
3.相続放棄前後にやってはいけないことの具体例
相続財産の処分といっても、その具体的なイメージは湧きにくいものです。以下では、相続財産の処分に該当しうる行為を具体的に挙げてご説明します。相続放棄について検討中のうちは、以下の各行為はいずれも行ってはならないので、ご注意ください。
3-1.預金の引き出し
亡くなったご家族の預金を無闇に引き出すことは、してはいけません。預金をおろして利用(=処分)した行為が相続財産の処分とみなされる可能性があります。預金を解約したり名義変更したりする行為も、相続財産の処分と見られるかもしれませんから、亡くなったご家族の預金には何もしない方が良いです。
万が一、既にご家族の預金を引き出してしまった場合には、そのお金を利用(=処分)することなく、保管しておきましょう。このようにすることで、相続財産の処分自体は未了であると説明できるようにしておくことが有用です。
3-2.衣類や家具・家電、日用品を処分(遺品整理)
また、衣類や家具・家電、日用品といった財産を処分することも、してはいけません。遺品整理・形見分けも、場合によっては相続財産の処分に該当すると捉えられうるので注意が必要です。
ちなみに、遺品整理・形見分けについては、対象となった遺産が財産的価値を否定されている場合には「相続財産の処分」に該当しないと判断された裁判例もあります。特に形見分けをお考えの場合には、まずは対象となる遺産の評価額を算出することをお勧めします。
3-3.携帯を解約
亡くなったご家族名義の携帯電話・スマートフォンを解約することも、相続財産を処分したものと扱われる可能性があるので要注意です。携帯電話を利用する権利を喪失させる行為にあたるため、相続財産の処分と捉えられかねないのです。
確かに、携帯電話を解約することで新たな負債が生じることを防ぐことはできますが、携帯電話を解約した行為が「相続財産の処分」に当たらないと明確に判断した先例もないので、用心するに超したことはないでしょう。相続放棄しないことを決定されたのちであれば各種契約の解除・解約が許容されますので、それまでは何にも触れないことが重要です。
3-4.入院費用の支払い
亡くなったご家族の入院費用を支払う場合には、注意が必要です。
亡くなったご家族の債務を、その方の財産(つまり相続財産)から支出してしまうと、相続財産の処分をしたことになり、以後、相続放棄ができなくなる可能性があるためです。どうしても入院費用を支払うよう求められてしまったとしても、相続財産ではなく、ご自身の資産から立て替えて支払うなど、亡くなったご家族の財産を支出しない工夫が必要となるでしょう。
入院費用に限らず、他の債務を返済する場合にも、同様に亡くなったご家族の財産を利用することのないよう、ご注意ください。
3-5.不動産の解体や売却
亡くなったご家族の名義の不動産の解体や売却をすると、相続財産を処分したものと扱われますので、これもしてはいけない行為となります。
特にご実家の状態・築年数・老朽化の程度などから、ご実家の居住者がいなくなったためにその解体をお考えになる方は多いです。しかしながら、やはり相続放棄をする以上は、亡くなったご家族の名義の財産を取り壊したり売ったりすることはできません。
倒壊のおそれがある場合にブロック塀を補修する、ぼろぼろの屋根を補修するなど、建物の「保存行為」に当たる行為は行えますので、どうしてもご心配な方は、相続放棄との関係でどこまでの行為が許容されるのか、一度弁護士までご相談ください。
3-6.賃貸アパートの解約
亡くなったご家族名義の賃貸アパートの解約もできません。これは、亡くなったご家族が有する「賃借権(=アパートを借りる権利)」を失う行為であって、相続財産の放棄に当たると指摘される可能性があるからです。
大家さんに対する罪悪感が芽生えるかもしれませんが、相続放棄を検討中である以上は、こちらからの解約申入れは控えましょう。結果として、大家さん側から賃料不払いを理由に明渡請求を受けるのを待つこととなります。
なお、賃貸アパートの賃料が未払いで溜まってしまっている場合も、上記入院費用の支払いと同様に、亡くなったご家族の相続財産から支払をしないよう、ご注意ください。
3-7.常識的な範囲を超えた金額の葬儀・墓石の支払い
葬儀を執り行ったり、墓石を購入したりすることは、日本国の慣習上広く認められている行為ですので、先例においても、常識的な金額の範囲内の費用であれば、相続財産からの支出をしても「相続財産の処分」には該当しないと判断されることがあります。
しかしながら、常識的な範囲を超えた金額の葬儀・墓石の支払いをした場合には、相続財産の処分が認められ、相続放棄できなくなってしまうことがあります。仏壇や仏具の購入費用についても、同じことがいえます。法律上の判断が絡む問題ですので、ご不安でしたら、一度弁護士にご相談されると良いでしょう。
3-8.財産に含まれる債権の債務者に対する支払い催告
相続財産に含まれる債権の債務者に対する支払いの催告をするだけであれば、相続財産の処分行為には当たらないといえるでしょう。しかしながら、催告を超えて、債権の取立てや実際の回収までしてしまうと、相続財産の処分に該当する可能性が生じますので、ご注意ください。
それではどのような行為が「催告」で、どのような行為が「取立て」かといえば、法的に相当程度難しい判断を要求されるでしょう。このため、相続財産に債権があり、その債権の取扱いに悩まれた場合には、早期に弁護士にご相談されるべきといえます。
4.まとめ:相続放棄の前後で注意すべきことを再確認
さて、以上のとおり、相続放棄の前後でしてはいけないことなどの注意点についてご説明しました。
再度整理しますと、
- ① 相続放棄手続は家庭裁判所に対して行わなければ効力を生じないことを忘れず、必ず手続をとる
- ② 相続財産の処分と捉えられる可能性のある行動は一切取らない
特に、亡くなったご家族の契約関係を解除したり、遺品整理をしたりすることは控える - ③ 相続財産を隠蔽したり消費したりする行動は厳に慎む
といった点に注意が必要です。中でも、相続財産の処分と捉えられる可能性のある行動は多岐にわたりますので、慎重な判断が要求されます。
相続放棄をするべきかお悩みの方は、拙速な判断で行動を起こすことなく、法律専門家である弁護士に一度ご相談いただくべきでしょう。当事務所には、相続問題や相続放棄になれた弁護士が多数在籍しています。ご家族をなくされたばかりの状況で大変な中ではありますが、予想外の債務を相続してしまうことのないよう、早期に当事務所へご相談ください。
あなたからのご相談を心よりお待ちしております。
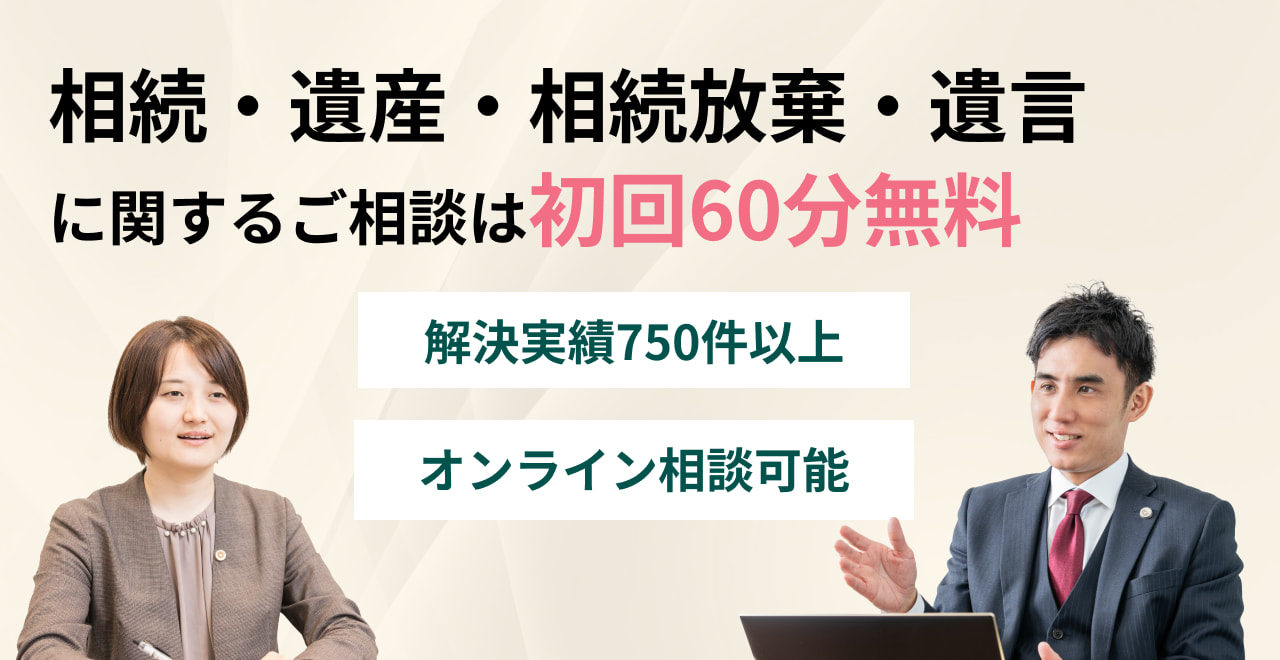
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。