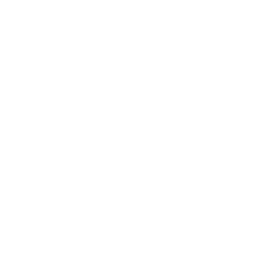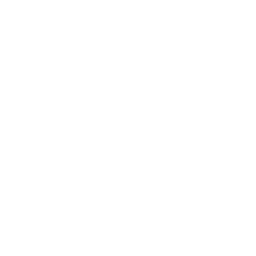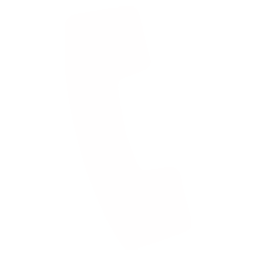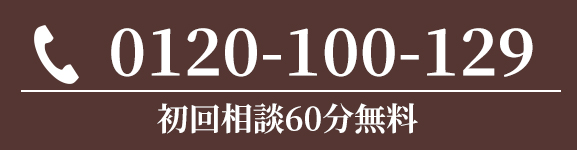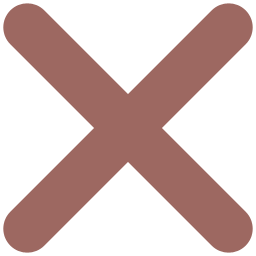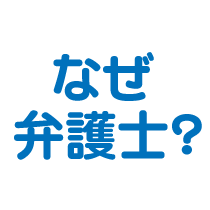携帯を解約してしまったら相続放棄できない?NG行為や対応方法について解説
更新日:2025/01/31
1.故人の携帯を解約してしまったら相続放棄できない?
亡くなった故人の携帯電話料金が、故人の口座から引きおとし続けられている……。
こんな事態はよく起こりがちです。しかしながら、ここであなたが気を利かせて携帯電話の解約手続を取ってしまってはいけません。携帯電話の解約手続をとると、その後、相続放棄ができなくなる可能性があります。
このため、仮に携帯電話の解約手続をとるのでしたら、その前に相続放棄手続を取る必要があるのか、故人に借金がなかったかを確認しておくことが必須となります。このような確認・検討を怠って軽率に故人の携帯電話を解約してしまわないようにご注意ください。
2.相続放棄ができなくなる条件
ちなみに、相続放棄ができなくなる条件としては、相続財産の処分・隠蔽・消費をすることが挙げられます。故人の財産(これを遺産、相続財産と呼びます。)を処分したり隠蔽したりすると、一方で故人の財産を取得しながら、他方で故人の借金を免れるということを許さないため、相続放棄ができなくなるのです。ちなみに、故人の財産を処分する行為を、法律上は「単純承認」と呼びます。相続することを単純に承認する行為とみなされてしまうということですね。
これらの相続放棄ができなくなる行為としては、例えば、
- ① 携帯電話の解約手続をとる
- ② 借家の解約をする
- ③ その他の契約を解除する
といった契約上の地位を喪失させるような処分を含みます。このように、携帯電話解約以外にも、各種の契約を終了させる際には、これに先だって借金の有無・相続放棄の必要性について検討をしておく必要があります。
3.携帯も法律上は相続財産として扱われる
携帯電話の契約者としての地位(携帯電話の契約名義人としての地位)も、電話回線を保有する権利を含むため、相続財産として扱われることに注意が必要です。このため、携帯を解約すると「相続財産を処分した」ものとして相続放棄ができなくなってしまうリスクが生じるのです。
携帯電話の解約であったとしても、これを実際に行う前に、相続放棄の必要性について弁護士に相談しておくと良いでしょう。
それでは、相続放棄について検討することもなく携帯電話を解約してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。この場合には、ご自身の行動が「相続財産を処分する」行為ではなく、むしろ相続財産を守るための行為であったと説明する必要があるでしょう。
つまり、携帯電話料金の引き落とし等がされ続けることで相続財産の価値が減少することを防ぐため(相続財産を保存するため)に、携帯電話の解約をしたという説明が必要となるのです。もし携帯電話を解約してしまったあとで相続放棄をする必要があったとお気付きになられた場合には、早急に弁護士にご相談をいただき、この点について裁判所を説得する理屈を構築できるか、ご検討ください。
4.携帯の名義変更をしても相続放棄できない?
ちなみに、携帯電話の名義変更をした場合には、「相続財産を処分した」ことに該当して相続放棄できなくなってしまうのでしょうか。この場合にも、同様に相続放棄ができなくなってしまう可能性がありますから、慎重な検討が必要です。
携帯電話を名義変更した場合、故人が有していた財産(携帯電話本体に価値がある場合もありますし、携帯電話の電話回線利用権に価値がある場合もあります。)を勝手に取得・処分したとみられるリスクがあるのです。この場合には、遺産を相続する意思を表明したものと扱われてしまいますから、以後、相続放棄ができなくなってしまいます。
5.携帯の未払金の支払いはどうする?
相続放棄をする場合には、携帯電話の未払金の支払いをしてはいけません。むしろ、相続放棄をする以上は故人の債務を支払う必要が無いのです。携帯電話の未払金を故人の財産から支出して支払った場合には、かえって「相続財産を処分した」として相続放棄することができなくなる可能性が高いので、ご注意ください。
ちなみに、どうしても携帯電話の未払金が気になってしまい、その支払いをしたいということでしたら、ご自身の財産から支払うこととなります。こうすることで、相続財産ではない財産によって支払いをしたこととなり、のちに「相続財産を処分した」と指摘されることが無くなります。
とはいえ、相続放棄をする以上は、あなたが故人の債務を負担する義務を負うことはなくなりますから、携帯電話料金を支払う必要はありません。そもそも携帯電話会社も、携帯電話の料金が2~3か月程度支払われない状態が続けば、携帯電話の契約を解除してくれますから、問題はありません。携帯電話会社に対して丁寧な対応をとりたい場合には、相続放棄をした後で家庭裁判所から発行される相続放棄申述受理通知書という証明証を携帯電話会社に送付する対応ととられると良いでしょう。
6.携帯の解約手続・方法
相続放棄した旨を携帯電話会社に通知したあとも、故人の携帯電話宛てに連絡が来る、故人の携帯電話会社の担当者から連絡が来る、といった形で、お困りになる方もいらっしゃいます。このような場合には、相続放棄後に携帯電話を解約することができます。
相続放棄後に故人の携帯電話を解約する場合には、①故人が既に亡くなっていること、②あなたが故人の相続人であること、③あなたが故人の相続について相続放棄をしていることを示した上で、携帯電話会社にSIMカードを返還することになることが多いです。この場合には、上記の①~③を示すために、
- ① 故人の除籍謄本、死亡診断書など
- ② あなたの身分証明書、故人との親族関係が分かる戸籍謄本類
- ③ 相続放棄申述受理通知書
を準備するよう指示されることが一般的なようです。
こういった資料を用意して携帯電話会社に連絡することで、相続放棄後に携帯電話の解約手続を行うことができますので、ご安心の上、相続放棄手続をとっていただければと思います。
7.相続放棄をするときの注意点
さて、以上の携帯電話解約の問題に加え、相続放棄するときの注意点をご説明しておきます。
① 必ず、家庭裁判所に対して相続放棄手続を行う
この点について誤解されている方が非常に多いですが、相続放棄手続は、家庭裁判所に対して申立書を提出することで、初めて法的に有効なものとして扱われます。つまり、相続人・親族間で「私は相続放棄したから遺産はいらない。」と述べたり書面を作成したりしても、相続放棄をしたとは認められないのです。
② 携帯電話の解約など、故人の相続財産の処分・隠蔽・消費をしない
また、上述してきましたとおり、故人の相続財産の処分・隠蔽・消費を行った場合にも、相続放棄はできなくなります。特に携帯電話に関してはいえば、携帯電話の解約、携帯電話の名義変更、携帯電話料金を故人の相続財産(遺産)から支払うといった行為は、いずれも相続放棄が認められなくなる可能性のある行為ですから、行わないようにしましょう。
③ 故人に債務がないだろうと決めつけない
れは相続放棄するときというよりは、相続放棄が必要かどうか検討する際の注意点となります。故人に債務・借金がないだろうと油断してしまって相続放棄を行わなかったところ、後から多額の借金が発覚したというご相談には、我々弁護士はよく出くわすところです。
相続放棄の手続をとる期間制限は厳しく、自分のための相続が始まったことを知った時、つまり、自分が相続の権利を有する人が亡くなったと知った時から、3か月以内とされています。「あの人は生活が安定していたから。」と慢心することなく、故人の死後は、故人宛ての郵便物等に注意しましょう。弁護士にご相談いただければ、借金の有無について調べる手段のアドバイスを得られるでしょうから、遠慮せずにご相談をご検討ください。
8.まとめ
以上のとおり、携帯電話を解約してしまったら相続放棄ができないのか、という点についてご説明をして、相続放棄一般の注意点もお伝えしました。
故人が亡くなられてしまうと、最初は通夜・葬儀・四十九日と、各種法要が続き、親族・知人等への挨拶などに追われるでしょう。このような中で、携帯電話等の故人の契約を、「料金を払わないといけなくなるから。」と気にして解除・解約されるご親族は多くいらっしゃいます。しかしながら、この時、一歩立ち止まって、「相続放棄が必要かもしれない。」、「もしかしたら、多額の借金があるかもしれない。」とお考えいただき、一度弁護士等へのご相談をいただければと思います。
当事務所では、相続放棄をお考えの方から、携帯電話解約後の相続放棄の可否についてお悩みの方まで、相続放棄について幅広いご相談に対応しております。一人でお悩みにならずに、一度当事務所までご相談いただけますと幸いです。
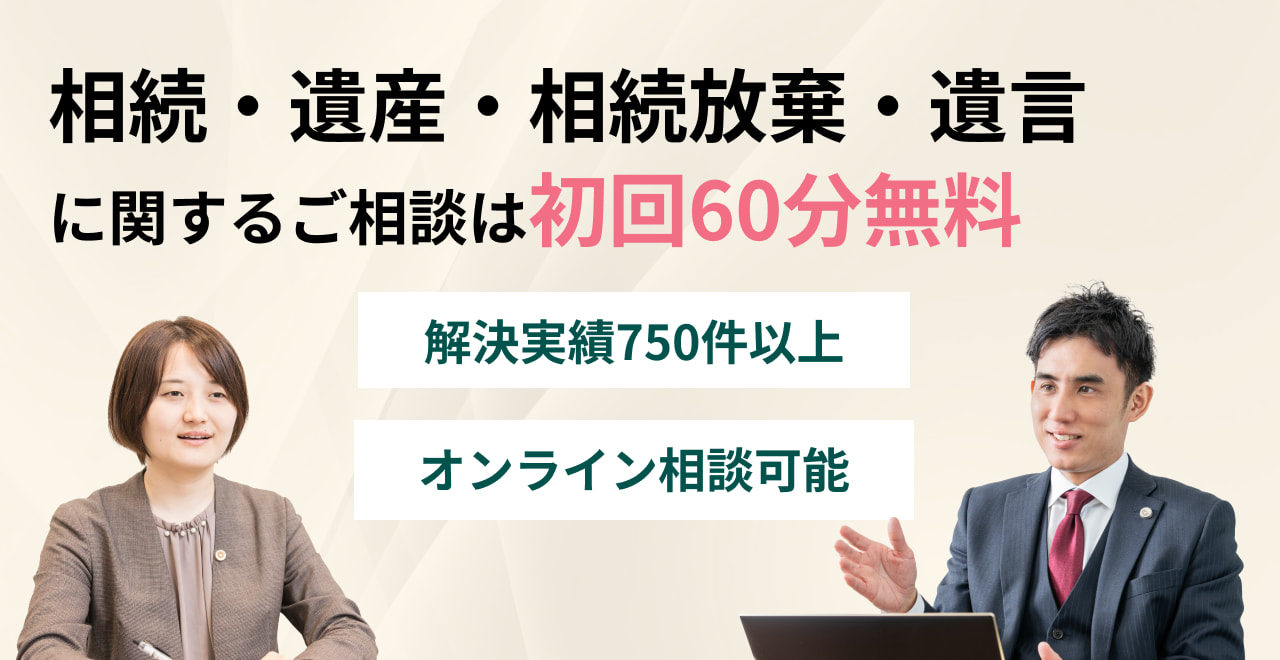
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。