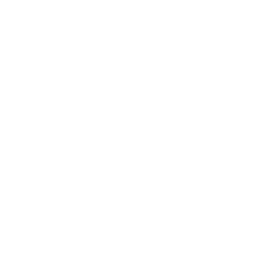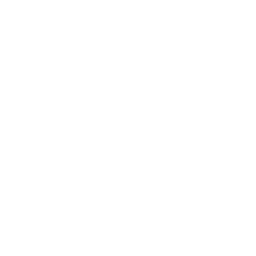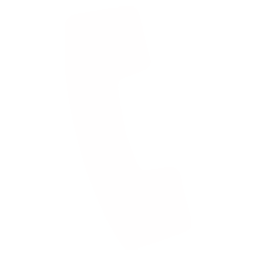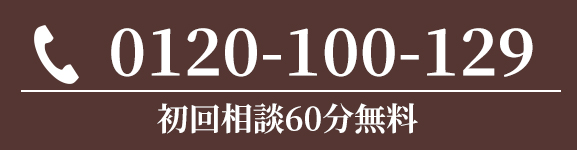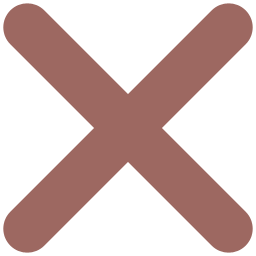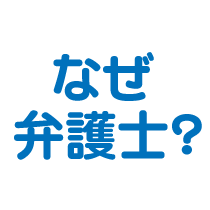遺産から葬儀代を支払っても相続放棄はできる!注意点とできないケースについて弁護士が解説
更新日:2025/03/03
遺産から葬儀代を支払っても相続放棄できる
亡くなった家族に借金があって相続放棄をしたいけど、お通夜・お葬式の費用はどこから支払えば良いのか。
入院中の家族に借金があるようだけど、死後、相続放棄できるだろうか。
ご家族の借金問題にお悩みの方は、そのご家族が体調を崩された際などに、こういった問題に直面します。相続放棄は、概要としては、ご家族が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする手続で、相続財産についての権利を失う反面、ご家族の借金・借財・債務の負担も免れることができます。但し、相続放棄する前にご家族の相続財産を処分した場合には、相続放棄が認められなくなってしまう場合があります。
このため、ご家族の葬儀費用をご家族の遺産・相続財産から支払っても相続放棄ができるものか、問題となるのです。結論から申し上げますと、葬儀費用を遺産から支払っても相続放棄できますが、例外があることに注意が必要です。以下、注意点と、葬儀費用を遺産から支払ったら相続放棄ができなくなるケースについてご紹介します。
遺産から支払える葬儀費用
故人の遺産から葬儀費用を支払ったとしても、それは日本社会における一般常識からすれば、自然なことといえます。このため、裁判所は、葬儀費用を相続財産から支払ったとしても、その費用が一般的な範囲であって不相当に高額でない限りは、「相続財産を処分した」ものと扱わない傾向にあります。
このため、一般的な範囲でお通夜・お葬式を実施してその費用を支出する場合には、遺産から支払ったとしても相続放棄できるといえます。ここでいう葬儀費用とは、一般に故人を弔うために必要とされる費用を指しますから、例えばご遺体の運搬費用や火葬費用、お寺・お坊さんへの心付け・戒名料なども含まれると考えられるでしょう。
なお、仏壇・墓石等の故人の仏具に当たるものの購入費用を遺産から支出したとしても、葬儀費用同様に一般的・常識的な範囲であれば、相続放棄ができるとする裁判例もあります。
遺産から支払えない葬儀費用
このため、逆に一般的・常識的な範囲を超えるような高額な費用を要する葬儀を実施する場合には、その葬儀費用は遺産ではなく、喪主などの名義の財産から支出するべきです。喪主などに葬儀費用負担の余裕がない場合で、相続放棄をする可能性があるのであれば、身分相応の妥当な範囲の葬儀に留めるべきといえます。
とはいっても、それではどの程度の規模・金額の葬儀費用を遺産から支出したら相続放棄ができなくなるのかという点について、明確に定めた法律や裁判例はありません。この点についてお悩みの場合には、ぜひ、弁護士のご助言を受けてください。葬儀の常識的な規模感は、地域の慣習やご家族の人数によっても変動するでしょうから、ご自身の実態を踏まえたアドバイスを専門家から受けると良いでしょう。
但し、遺産から支払うことが常識的に許容されるのは「葬儀」のために必要な費用に限られますから、初七日・四十九日にかかる費用や、墓地自体の購入費用などは、やはり喪主の負担とすべきでしょう。
遺産を故人の銀行口座から引き出す場合
ちなみに、遺産から葬儀費用を支出する場合には、故人が現金を保管していたものでない限り、故人の銀行口座から金銭を引き出す必要があります。この場合、のちに争いにならないように、相続人全員の許可を得てから引き出す方が無難といえます。
故人名義の銀行口座から金銭を引き出す方法は、概ね以下の2つとなります。
遺産分割前の相続預金の払戻制度(民法909条の2)を用いる
まず、遺産分割前の相続預金の払戻制度があります。
これは、故人名義の銀行口座に関して、銀行窓口で、遺産分割協議が成立する前に一部の預金の引き出しを行える制度です。引き出せる金額が、亡くなった方の死亡時の預金残高に、引き出す人の法定相続分を掛け、更に3分の1した金額(但し、上限額は150万円)に限られますが、遺産分割前であっても、そして他の相続人の同意がなかったとしても引き出しが可能となります。
必要書類がある程度多くなりますが、それらを揃えて申請すれば、数週間から1か月ほどの期間で引き出しができます。
なお、この方法によって引き出した額よりも葬儀費用の方が低かった場合、遺産から引き出した金銭が余ることとなります。この余った金銭を自己のために使用してしまうと「相続財産の処分」に当たって相続放棄ができなくなるので、ご注意ください。
家庭裁判所に払戻しの許可を求める申立てをする
次に、家庭裁判所に払戻しの許可を求める申立てをする方法もあります。
こちらは、遺産分割調停・審判の申立てをしていることが条件になりますので、ご家族において遺産分割協議がなされている場合に行える制度となります。但し、遺産分割調停をしているということは、遺産の分割について争いが生じているということですから、相続放棄を考えるような事例ではあまり活用の機会がない方法ともいえます。
遺産から葬儀代を支払う場合の注意点
さて、それでは、遺産から葬儀代を支払う場合の注意点をご説明いたします。これらの注意点に留意しておくことで、遺産から葬儀代を支払っても相続放棄ができる可能性を高めておくべきです。
領収書や明細書を残しておく
まず、必ず葬儀費用・葬儀に関連する費用について、領収書・明細書を保管しておきましょう。
葬儀費用・葬儀に関連する費用について領収書・明細書を保管しておかないと、実際に遺産を何にどれだけ支出したのか分からなくなってしまい、場合によっては遺産を自己のために処分したのではないかという疑いをかけられてしまうかもしれません。このような事態にならないように、葬儀費用等に用いた領収書・明細書は、必ず保管しておくように注意しましょう。
熟慮期間を経過しない
次に、熟慮期間を経過しないようにもご注意ください。
熟慮期間とは、故人が亡くなったこと・自分が故人の相続を受ける立場にあることを知ってから3か月となります。この期間中しか、相続放棄はできません。このため、葬儀費用を支払うための手続も、この期間内に行っておく方が良いといえます。
四十九日が経過した時点で、死後1か月半以上が経過していることになりますから、あっという間に3か月間は経過します。相続放棄ができなくなることのないよう、ご注意ください。
相続財産を処分しない
また、当然ながら、相続財産を処分、つまり自分のために利用したり売却したりしないように注意することも必要となります。
特に、上述したとおり、遺産から葬儀費用を支払ったのち、余った遺産を自分で使ってしまうことのないように注意しましょう。余った金銭は、例えば封筒にいれて保管しておく、他の相続人に渡して引き継ぐなど、自分自身の財産と区別できるようにしましょう。
葬儀費用に注意していたのに、他の事情で相続放棄ができなくなってしまうことのないようにお気を付けください。
隠蔽しない
もちろん、相続財産を隠蔽・隠匿してしまっても、相続放棄ができなくなります。このような行為をとることも、当然お控えください。相続放棄をするのであれば、遺産・相続財産には一切の権利がないと考えておく方が良いでしょう。
相続放棄ができないケース
以上のとおりですので、相続放棄ができないケースについて整理すると、
- ① 一般的・常識的な範囲を超える葬儀費用を遺産から支出した場合
- ② 遺産から支出した葬儀費用の明細の記録がなく、遺産を葬儀費用にしか用いていないと説明できない場合
- ③ 遺産から葬儀費用に充てる以上に、余った金銭を自己のために利用してしまった場合
ということができます。葬儀費用を遺産から支出し、その後に相続放棄をする場合には、これらのケースに当たることのないよう、細心の注意を払う必要があります。
ご心配なことがあった場合には、相続放棄ができなくなることのないよう、法律の専門家である弁護士にご相談をいただくことをお勧めいたします。
まとめ
さて、相続財産から葬儀費用を支払って相続放棄する場合の注意点と相続放棄ができないケースについてご紹介しました。故人に借金がある場合、特にその金額が大きい場合には、相続放棄ができなくなることは致命的な問題となります。
相続放棄をお考えの場合には、実際に葬儀費用を遺産から支出する前に、弁護士にご相談ください。当事務所は、相続放棄を含めた相続問題に精通した弁護士が複数在籍する事務所となります。あなたからのご相談に丁寧に対応しますので、ぜひご相談ください。
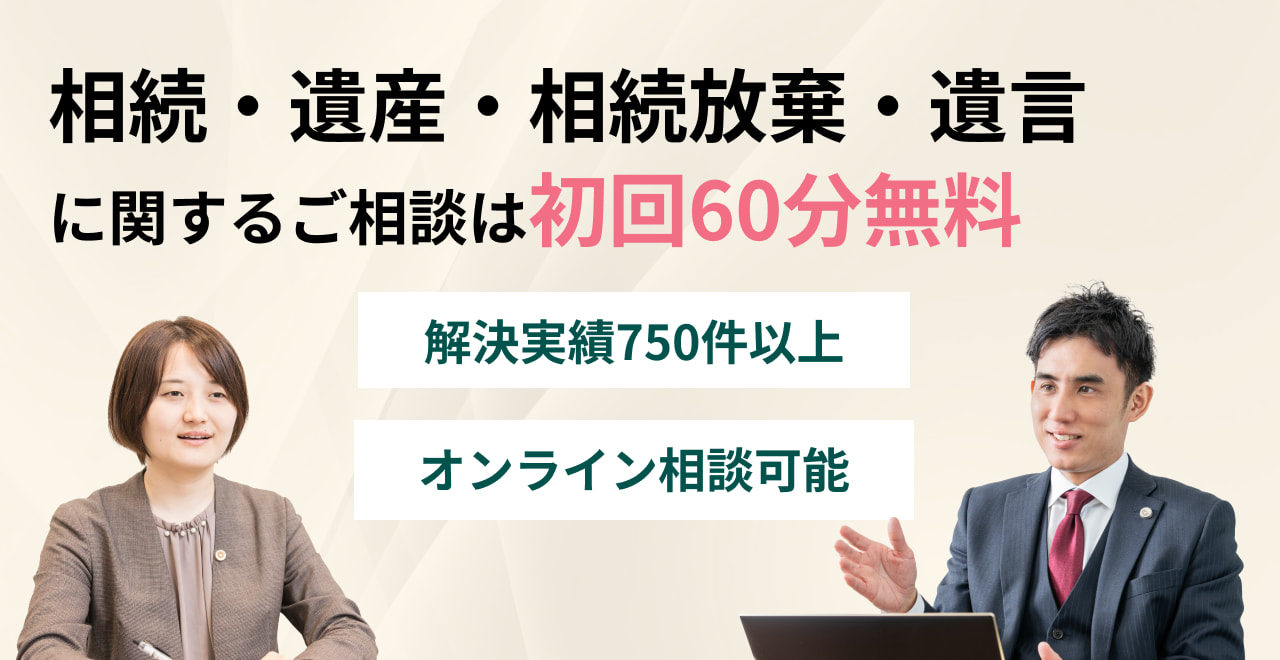
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。