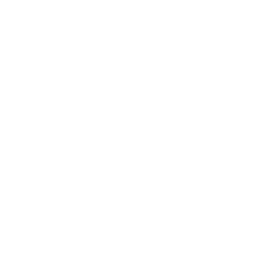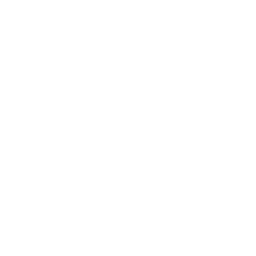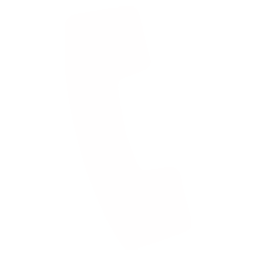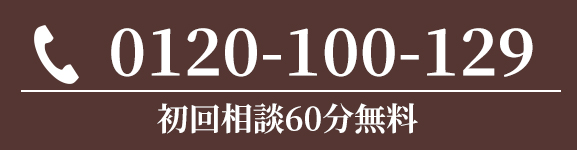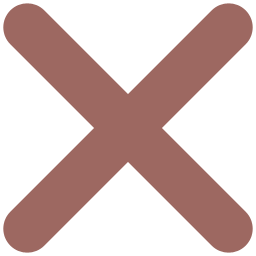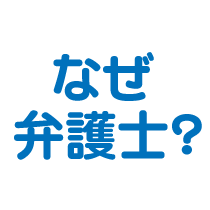生前の相続放棄はできない|事前にできる対応・手続きについて弁護士が解説
更新日:2025/03/03
生前の相続放棄は無効
相続放棄手続については、多くの方が誤解して誤った手続を取られることが多いので、正確な理解が必要となります。以下では、生前の相続放棄が無効であることをご説明した上で、事前(つまり生前)にできる対応・手続について解説していきます。
相続放棄とは
そもそも相続放棄とは、故人の遺産(残された資産)よりも債務の方が多いなど、故人に多額の借金がある場合に、故人の相続人の立場を放棄する手続を指します。故人の借金を相続することを避けるために、相続放棄手続を活用される方は多くいらっしゃいます。
注意しなければならない点として、故人の資産を相続することもできなくなる点が挙げられます。故人が不動産等をお持ちであったとしても、株式等の有価証券をお持ちであったとしても、それらを相続することができなくなりますので、相続放棄前には慎重な検討が必要となります。
また、相続放棄前に、遺産・相続財産の処分を行うと、以後相続放棄ができなくなる点にも注意が必要です。相続財産の処分をしてしまうと、対外的には相続放棄をする意思がないと表明することとなりますし、本来相続することのできない遺産に手を出すことをも意味します。相続放棄する可能性が少しでもある場合には、相続財産を自ら利用することのないように留意しましょう。
生前の相続放棄は無効となる理由
こういった相続放棄をするためには、ご家族が亡くなったあとに、亡くなったご家族の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述」という手続を取る必要があります。この点について誤解される方が多いのです。
例えば、「他の相続人に、私は相続放棄すると伝えたから大丈夫。遺産分割協議書にも、相続放棄すると書いた。」などとご説明しながら法律相談にいらっしゃる方がいます。この方は、他の家族に対して相続放棄する旨の表明をすれば相続放棄ができるものと誤解されています。しかしながら、これでは有効な相続放棄がなされたとはいえません。あくまでも、本人の死後、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をしなければなりません。
それでは、なぜ生前の相続放棄は無効となるのでしょうか?
それは、上記のとおり、相続放棄が「資産の相続もできなくなる制度」であるからです。生前の相続放棄が認められてしまうと、相続人間で、ご家族が亡くなる前に相続放棄を強要するような行為がなされてしまう危険があります。特にご家族の資産状況を正しく把握しないままに相続放棄を強要される事態があっては、相続人の平等性が崩れてしまいます。あくまでも故人の死後、相続人個々が慎重に検討した上で相続放棄をすることができるように、法律は生前の相続放棄を認めていないのです。
生前にできる相続放棄に変わる対策方法と注意点
生前に相続放棄することはできませんが、生前にできる相続放棄に似た手続はありますので、それらのご説明をいたします。これらの手続には一長一短ありますので、ご家族で内容をご検討いただいて、ニーズに沿うものをご選択いただくと良いでしょう。
遺留分の放棄を行う
まず、遺留分の放棄を行うことがあり得ます。
遺留分とは、相続人(ただし、兄弟姉妹を除きます。)に最低限保障されている相続割合を指します。仮に故人が遺言を残していて、ある相続人に全く相続しないことと指定していたとしても、法律上、法定相続分の半分までは、最低保障額が残ることとなります。このため、遺言や生前贈与によって遺留分の最低保障額を受け取ることができなくなった相続人は、遺産を受け取った相続人に対して、遺留分侵害額の支払を請求することができます。
この遺留分を生前に放棄することで、遺言を残すだけである相続人への相続が全くなされない状況を作ることができます。
遺留分の放棄は、遺留分を有することになる予定の方が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の許可をもらうことで認められます。申立てに要する費用は、数千円程度となります。
但し、相続放棄同様の効果をもたらす重大な手続ですので、裁判所の許可には、遺留分を放棄する正当な理由が必要となります。
遺言書を作成する
次に、遺言書を作成することが考えられます。
遺言書を作成しておけば、遺言を作成した方が亡くなった後に、故人の遺産を誰が相続するか決定することができますので、特定の相続人への相続がなされないようにすることができます。但し、債権者に不測の事態を招くことのないよう、負債の相続先を遺言で特定することはできないので、注意が必要です。
遺言書は、故人が生前に作成する必要があります。遺言の代表的なものとしては、大まかに、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、文字通り自らの直筆にて作成する遺言です。法律上有効な自筆証書遺言とする場合には、日付・氏名を書いて押印するなど、様々な作法を守る必要がある上に、故人の死後、自筆証書遺言の内容を家庭裁判所で確認してもらう手続(検認といいます。)が必要となりますので、弁護士としては、あまりお勧めする機会がありません。
もう片方の公正証書遺言は、遺産の金額によって多少の費用がかかるものの、公証役場(公証センター)において公証人の立会いのもとに作成されるため、のちに無効となるリスクを大きく減らすことができます。弁護士としては、リスクの少ない公正証書遺言の作成をお勧めします。なお、当事務所では公正証書遺言作成のご依頼も多く承っておりますので、ご興味のある方はこちらもご覧ください。
推定相続人の廃除の申立てを行う
次に、推定相続人の廃除の申立てについてもご案内します。
かなり稀な制度ではありますが、相続人が「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき」や、「その他の著しい非行があったとき」には、相続人の立場を失わせる請求ができます(民法892条)。もちろん、これらの事実については、証拠を準備しておく必要があります。
この手続は、被相続人の方が、生前に自分の相続について検討した上で、家庭裁判所に申立てを行って進めることとなります。ただ、虐待を行うような相続人を相手にする手続ですので、生前に自分で手続を行う以外に、遺言によって推定相続人から廃除する旨の意思表示を行い、遺言執行者を指定しておくことで、死後、遺言執行者に故人に成り代わってもらい、家庭裁判所に廃除の申立てを請求してもらうこともできます。おそろしく感じる相手と自ら争うまでの必然性はないといえます。
この手続は、裁判所に請求を認めてもらうだけの証拠を集められるかが決め手となる手続であるといえるでしょう。
生前贈与を行う
また、遺言は死後に無効とされるリスクがあることから、生前贈与を行うことも手段として考えられます。
生前贈与は、被相続人の方が、生前に相続人等に自己の資産を贈与することを指します。生前贈与をすることで自己の遺産を減らしてしまえば、事実上特定の相続人を相続手続から排除することができます。
但し、生前贈与をする場合には、贈与税・相続時精算課税などの税率・税制度に留意する必要があります。生前贈与を実行に移す前に、必ず税理士への相談・確認をするべきといえるでしょう。
生命保険の利用をする
その他、相続放棄類似の手段として、生命保険の利用も考えられます。
生命保険は、保険会社との保険契約に基づき、契約者の死後、保険金受取人に指定した方が保険金支払を受けることができる制度です。死亡保険金はあくまでも「保険契約」に基づいて支払われるものであるので、遺産総額と比較してあまりに多額の生命保険金でなければ、原則として遺産分割協議の対象からは外れます。このため、生命保険を利用して生前贈与・遺言による相続と同様の効果を狙う方もいらっしゃるのです。
また、相続税対策として生命保険を利用される方もいらっしゃいます。
債務整理を行う
最後に、生前に債務整理を行っておく手続もご紹介します。
相続放棄を検討される際には、通常、亡くなられた後の負債の処理についてお悩みであるはずです。この点について、生前に整理をして悩みを払拭するために債務整理を行うことが考えられるのです。
債務整理は、借金を抱えている方ご自身が、弁護士等に依頼して行う手続となります。通常は、借金のうち利息・遅延損害金の一部をカットした上で、3~5年程度の期間での分割払いをすることで各債権者と和解していく制度となります。
この手続を取ることで、月の借金返済額を抑えて相続人の負担を軽減させておくということもご検討ください。特に、事前に相続人になられる予定の方の収支状況(月額どの程度の返済が可能か)も見ながら和解交渉を進めることができれば、相続人となるご家族にも無理のない返済額を設定できるでしょう。
相続放棄のメリット・デメリット
以上のような手続と比較すると、相続放棄のメリット・デメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
相続放棄のメリット
- 故人の負債を負う可能性を完全になくすことができる
- 費用が安く済む
- 相続人個人の判断のみで実現できる
- 遺産分割協議など遺産に関する争いに関わらなくてよくなる
相続放棄のデメリット
- 故人の生前には手続をとれず、期間制限も厳しい
- 故人の財産に関する一切の権利を失う
- 多くの資料を集めなければ手続が取れない
これらのメリット・デメリットのどの点を重視するべきかは、弁護士に相談してから決めていくべきです。ぜひ、お悩みの際には、弁護士にご相談ください。
相続放棄の手続の流れ
相続放棄は、以下のような手続で流れていきます。必要となる書類が多いので、専門家である弁護士に手続を依頼してしまった方が良いでしょう。
① 裁判所への申述書の作成
※添付資料として、故人の除籍謄本、誰が相続人なのか示すための各種戸籍類などを集める必要があります。この手続が煩雑であるとお考えの方が多い傾向にあります。
② 裁判所による書類審査
③ 裁判所から相続放棄の申述をした本人への問い合わせ
※郵送で、本当に相続放棄する意思を有しているのか問い合わせる書面が届きますので、これを裁判所に返送することとなります。
④ 相続放棄の申述の受理
上記④まで進みますと、家庭裁判所で相続放棄受理証明書を発行してもらえるようになります。この書類を持っておくことで、のちに故人の債権者から返済を求められた際に、ご自身が相続人ではないことを示すことができます。
相続放棄の期限
ちなみに相続放棄は、故人が亡くなり、自分のために相続が開始したと知った時から3か月以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄の申述が認められなくなりますから、ご注意ください。特に借金がある場合には、故人の死後早急に相続放棄が必要か検討する必要があります。
まとめ
さて、以上のとおり、生前の相続放棄ができないことと、相続放棄以外の生前にできる手続についてご説明しました。
当事務所では、相続放棄についてのご相談を多く受けております。相続放棄についてお悩み・ご検討をされている方は、相続放棄以外の選択肢も含めたご提案をいたしますので、お早めに当事務所にご相談ください。もちろん、ご本人がお亡くなりになる前のご相談もお請けしております。
あなたからのご相談を、心待ちにしております。
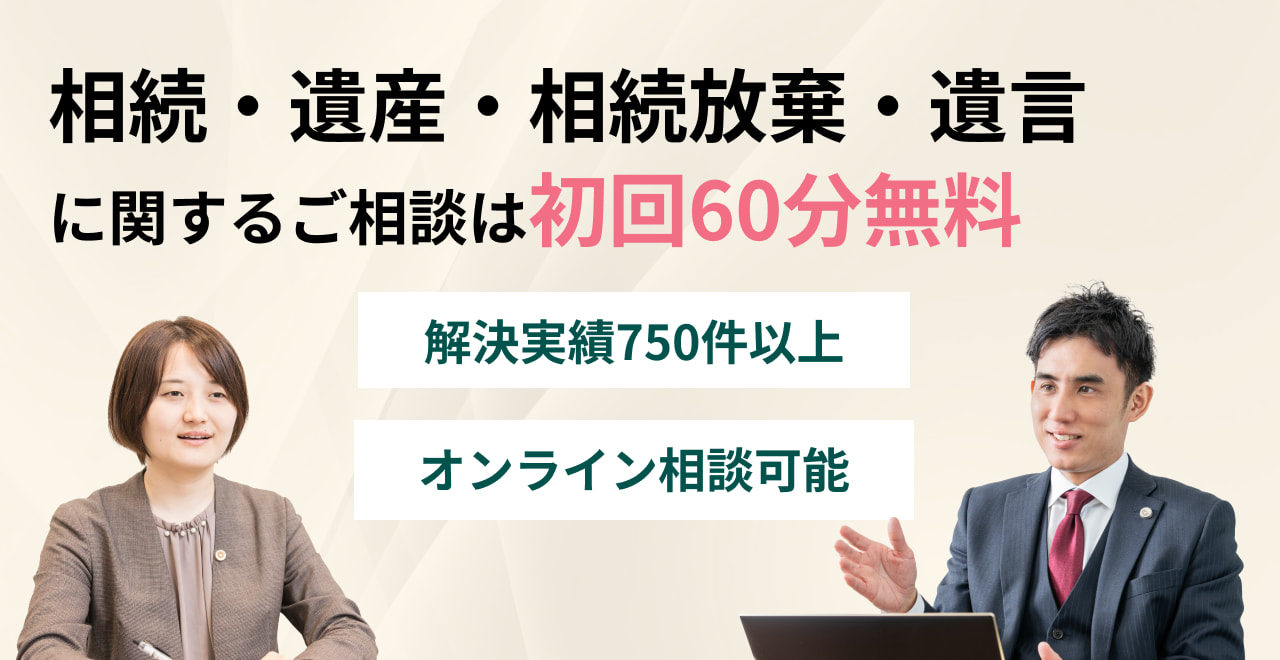
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。