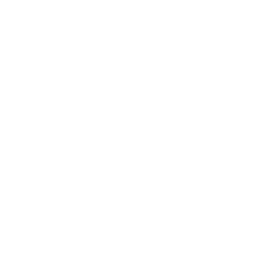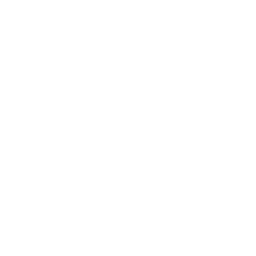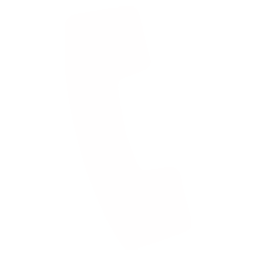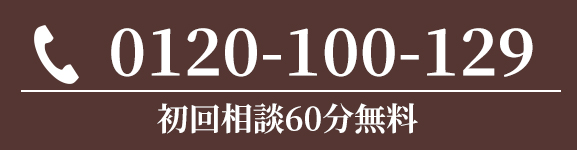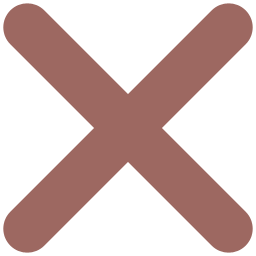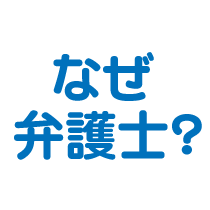認知症の家族がいる場合の相続放棄について弁護士が解説
更新日:2025/06/11
認知症の家族は相続放棄できる?
高齢の親に借金があるので、親の死後には相続放棄をするつもりである。
そんな場合に、あなたのご兄弟に認知症が進んでしまった方がいたら、どうすれば良いのでしょうか?
実は、こんな内容にお悩みの方が、結構多くいらっしゃいます。
認知症の方は、認知症の程度にもよりますが、相続放棄を単独で行うことはできません。これは、相続放棄をするかどうかの判断をするだけの判断能力・認知能力がなければ、法律上相続放棄の申述ができないからです。判断能力を欠いた人が行った相続放棄は、無効となります。
また、認知症の方が相続人にいる場合には、遺産分割協議を簡単に行うこともできません。やはり相続放棄同様に、遺産をどのように分割するか理解して判断するだけの判断能力・認知能力がないと、遺産分割協議の意思表示をすることができないためです。遺産分割協議も、認知症で意思能力を欠く人がいた場合には、無効となってしまいます。
このように、認知症の相続人がいる場合には、相続放棄にせよ、遺産分割協議にせよ、簡単にはこれを執り行うことができなくなってしまうという問題・リスクが生じます。以下では、認知症の家族がいる場合の相続放棄について解説していきます。
認知症の相続人が相続放棄をする際の注意点
認知症の相続人が相続放棄をする場合には、まずは相続人の認知症の程度、判断能力・認知能力がどの程度減退している状態なのかを調べておく必要があります。ここでは、医師の診察・判断を得る必要があるでしょう。医師による判断能力・認知能力についての診断を得て初めて、金銭的な意思決定・意思表示をできる状態か否かが判明するといえます。
その後、認知症の程度がどの程度であれば相続放棄や遺産分割ができるかという点については、最終的に裁判官が法的視点から判断することとなります。相続放棄が可能か否か、つまり、自身が相続する権利を包括的に放棄するべきか判断可能かどうかという点について、裁判官が資料を踏まえて判断することとなるのです。
このため、医師の診断書を得た段階で、法律専門家である弁護士に相談して助言を得ることが有用といえます。
仮に認知症が一定程度進行していて、相続放棄や遺産分割を自ら行うことができない場合には、認知症の相続人に成年後見人等の後見人を付ける必要があります。成年後見人等をつけるためには、認知症のご家族の居住地を管轄する家庭裁判所に対して成年後見開始審判申立てをすることとなります。
この後見人がいないままに認知症が進行した相続人に相続放棄・遺産分割をさせることは控えた方が良いでしょう。
成年後見制度とは?
ちなみに、成年後見制度とはどのようなものなのでしょうか?
成年後見制度には、①成年後見人、②保佐人、③補助人という3類型があり、認知症等の判断能力・認知能力が低下した状態であったり、病気・怪我によって意識不明の状態であったりするなど、精神上の疾患によって事理弁識能力(物事を理解して適切な判断をする能力)に問題を生じている場合には、家庭裁判所に対し、問題の程度に応じて上記3類型のいずれかの制度利用を開始するよう求めることができます。
この申立てによって後見人が選任された場合、後見人が本人の代わりに相続放棄や遺産分割などの意思表示を行うことができるようになります。
成年後見等の開始審判の申立てを受けた家庭裁判所は、認知症のご家族に成年後見人を付けることとなります。このとき、裁判所は、ご親族か、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)を後見人に選任することとなります。
後見人がつく事案の約8割の事案では、ご親族が後見人となってその方の財産管理・身上監護(簡単にいえば、その面倒を見ること)を担当することとなりますが、本人が流動資産を多く保有している場合や、相続放棄・遺産分割といった法的問題がある場合には、専門家後見人として弁護士が選任されることとなります。
これは、親族が後見人になって本人の資産を横領してしまったり、相続放棄・遺産分割において本人ではなく自己に有利な判断をしてしまったりすることを防ぐためです。
特に、後見人が、本人と後見人の利益が衝突する行為(利益相反〔そうはん〕行為といいます。)を行うことは禁止されています。後見人もご家族で相続人であった場合には、本人の代わりに相続放棄をしたり、自己の相続分を後見人に渡す内容の遺産分割協議をしたり、後見人の思いのままにできてしまいます。
このようなことのないように、中立的な第三者かつ法律専門家である弁護士が後見人に選ばれることとなるのです。成年後見制度は、あくまでもご本人を守るための制度であるといえます。
このように、判断能力・認知能力が低下した方自身を守りながらその意思決定・意思表示支援を行う制度が、成年後見制度となります。
後見人を立てないことのデメリット
相続放棄や遺産分割が問題となる場合、認知症のご家族がいるのに後見人を立てないでいると、以下のようなデメリットがあります。
① 遺産分割協議ができない・進まない
まず、遺産分割協議自体ができなかったり、進まなかったりします。認知症のご家族がいる場合には、そのご家族が遺産分割協議に必要な意思決定・意思表示をすることができませんから、どの遺産を誰が取得するのかという協議自体ができません。もちろん、認知症のご家族に相続放棄をして相続人から外れてもらうこともできません。
特に遺産に不動産がある場合には、不動産の相続登記手続時に、司法書士による本人の意向確認がなされますから、認知症であることを隠して遺産分割協議を進めることはできません。
そうすると、遺産を誰も有効活用できないままに時間が経過することとなってしまいます。
② 遺産の処分ができない
また、認知症のご家族が相続放棄をできない以上は、遺産・相続財産の処分には慎重にならざるを得ません。
そもそも相続放棄は、一部でも相続財産を処分した人は行うことができない手続です。このため、外部から見て誰が相続財産を処分したか分からない状態にすること、例えば亡くなったご家族の預貯金口座からお金を引き出すことや、遺品の整理を行うことは、認知症のご家族による相続財産の処分とみられ得る行為ですので、控えざるを得ないでしょう。
このように、のちに相続放棄の効力が争われるといった紛争を避けるための注意を要することとなります。
認知症の相続人がいる場合の対策
ちなみに、そもそも認知症の相続人がいる場合には、成年後見人をつける以外に対応・対策は取れないのかというと、そうではありません。ご家族が亡くなって相続が始まってから成年後見人を立てるのではなく、ご家族の生前から取れる対策もありますので、ご参考にしてください。
① 遺言書を作成する
まずは、事前に遺言書を作成しておくことが考えられます。事前に遺言書を作成しておき、遺産を誰に渡すか決めておくことができれば、認知症のご家族がいる中で遺産分割協議ができない・終わらないといった問題に困ることは避けられるでしょう。
ここでは、死後に遺言の有効性に疑義を抱かれないように、公正証書遺言を作成したりするなど、弁護士の助言・協力を得た方が無難です。
但し、法律上、被相続人が抱えていた借金・債務を誰が引き継ぐかは遺言では指定できませんので、借金を抱えた方の相続時には、遺言があったとしても、認知症のご家族による相続放棄が必要となりますから注意が必要です。
② 家族信託制度などを利用する
次に、家族信託制度などを利用して、生前にご自身の財産をご家族に分けてしまうことも考えられます。遺言を作成するのと同様に、事前に遺産を誰に渡すか決めてしまうことで、ご自身が亡くなった後の遺産分割協議ができない・終わらないという問題を回避できます。
但し、この場合にも、遺言と同様に、被相続人が抱えた方の相続時には、認知症のご家族による相続放棄は必要となりますから、ご注意ください。
③ 任意後見制度を用いる
また、ご家族の認知症がそこまで進んでいない場合であれば、認知症の程度が悪化する前に任意後見制度を用いることも考えられます。任意後見制度とは、判断能力・認知能力に問題を生じてから家庭裁判所に後見人を選任してもらうのではなく、事前に自分で後見人を選んでおく制度をいいます。
任意後見制度を利用するには、自分で選んだ後見人との間で、公正証書による任意後見契約を締結する必要があります。公正証書とは、公証役場(公証センター)において公証人という専門家に立ち会ってもらいながら作成する書面を指します。
公正証書による任意後見契約書を作成しておくことで、本人が自らの意思で後見人を選任したことを証明することとなります。
事前に弁護士を後見人に指定しておくことができれば、家庭裁判所にランダムに選ばれる弁護士よりも、身近で信用できる弁護士に、ご自身の相続放棄・遺産分割の判断を任せることができますし、また、被相続人の死亡後に速やかにこれらの意思表示を行うことができます。
まとめ
以上のとおり、認知症の家族がいる場合の相続放棄について解説しました。認知症のご家族がいる場合には、安易に相続放棄をすることなく、後見人を立てる、生前から任意後見契約の準備をするなどの対策を取ることが必須となります。ご自身・ご家族のみで対策を取ることが難しい分野ですから、お悩みの場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談をいただくことをご検討ください。
当事務所では、相続放棄にお悩みの方からのご相談・ご依頼を多く扱っています。また、認知症のご家族がいる場合など、一定の困難が伴う特殊事例にも取り組んでいる実績があります。相続放棄についてお悩みの方は、当事務所までお問い合わせください。当事務所では、あなたからのご相談をお待ちしております。
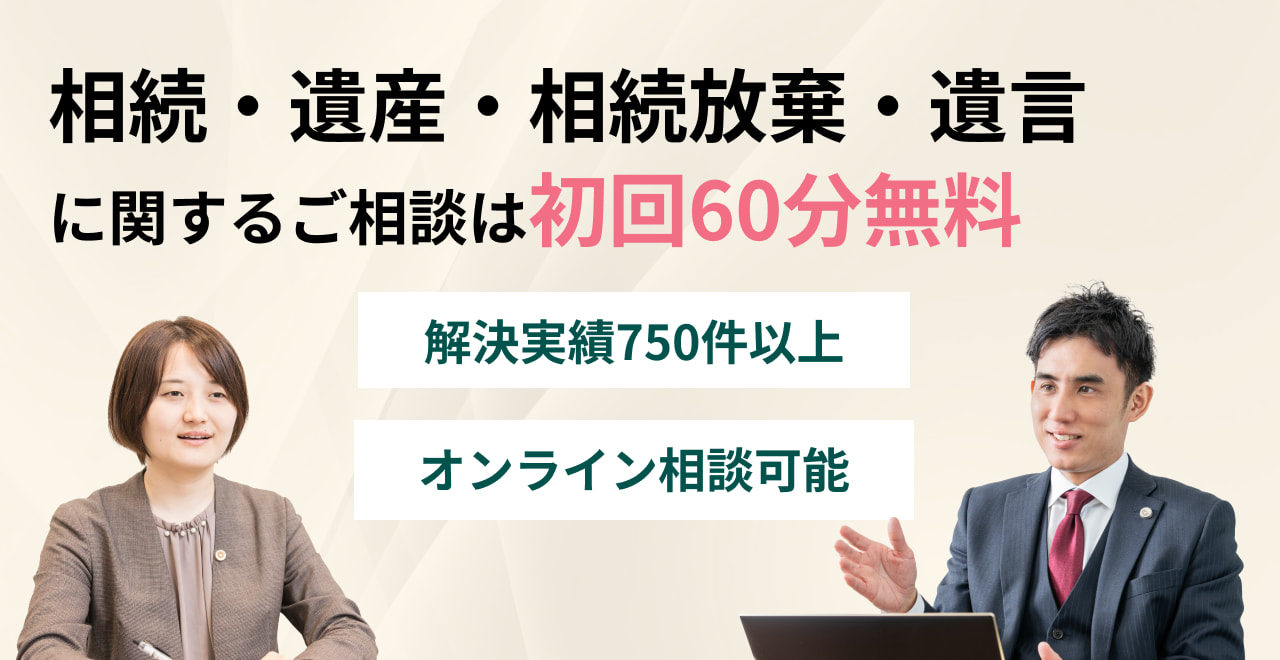
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。