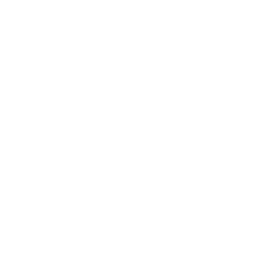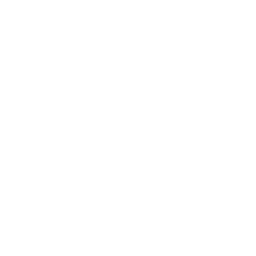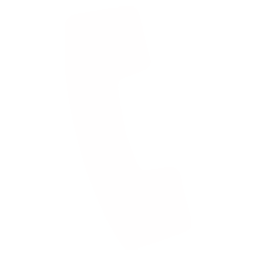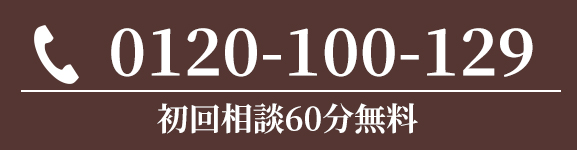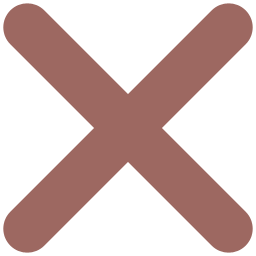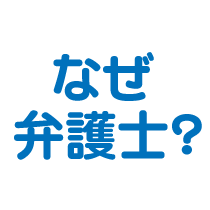相続放棄の期間はいつまで?手続きの流れから期限を過ぎたケースまでわかりやすく解説
更新日:2025/08/06
「借金のある親の財産を相続するか迷っているけれど、何から調べればいい?」
「期限を知らずに放棄できなくなるのは困る」
この記事でわかる三つのポイント
- 相続放棄と三か月の期間の基本
- 期限が近いときの対策
- 専門家に頼むかどうか判断する基準
結論として、相続放棄は「3か月以内」の準備が重要です。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続を行う必要があります(民法915条1項)。この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされるため、放棄できなくなるおそれがあります。
とはいえ、実際の手続には戸籍の収集や申述書の記載、書類の不備への対応など、一定の時間と手間がかかるのが実情です。特に、平日はフルタイムで働いている方にとっては、3か月の期間があっという間に過ぎてしまうこともあります。
そのため、相続放棄を検討している場合は、できるだけ早い段階で準備を始め、必要書類の収集や専門家への相談を行うことが大切です。
この記事を読むと、期限の考え方と進め方がつかめて安心につながります。
最後まで読んでみてください。
相続放棄の期限はいつまで?
相続放棄には、「3か月以内」という法定の期限(熟慮期間)が設けられています。この期間を過ぎてしまうと、遺産だけでなく借金もすべて引き継ぐ「単純承認」と見なされるおそれがあるため、正確な理解と早めの対応が不可欠です。
以下では、熟慮期間の起算点、計算方法、3か月という期限が設けられている理由、法的根拠まで詳しく解説します。
相続の開始を知った日から3ヶ月が熟慮期間
「死亡日」ではなく「死亡を知った日」が起算点
相続放棄の熟慮期間は、被相続人が亡くなった日ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」(民法第915条1項)起算するため、「その死亡を知った日」から数えます。
たとえば、疎遠だった親族の死を後から知ったような場合、その通知を受けた日が起算点となります。ただし、死亡を知っていたにもかかわらず放置していた場合、後日その知識を否定するのは困難です。
- 例:3月10日に親の死亡を知らされた場合 → 6月10日が相続放棄の期限
なお、家庭裁判所が期日に閉庁している(土日祝日など)場合でも、期日前に申述書が正式に受理されている必要があります。期限後の提出は原則認められません。
3ヶ月の具体的な計算方法
熟慮期間の数え方は「暦による3か月後の同日」が基本です。
- 例:3月10日 → 6月10日が期限
月末が起算日で翌月に該当日がない場合(例:1月31日→4月30日)、その月の末日が期限
この期限までに、相続放棄の申述書が家庭裁判所に「提出され、正式に受理される」必要があります。余裕を持ったスケジュール管理が大切です。
なぜ3ヶ月の期限が定められているのか
債権者・相続人双方の不確実性を早期に解消するため
故人が借金を残して亡くなった場合、相続人が放棄するのか承認するのか不明確なままでは、債権者側も対応できません。また、他の相続人や関係者にも混乱が生じます。
こうしたトラブルを防ぐため、法律は一定期間内に意思表示を求めており、それが「3か月の熟慮期間」です。
この期間中に判断を迫ることで、利害関係者全体の法的安定性を確保する狙いがあります。
法的根拠(民法上の規定や判例)
民法第915条第1項では、次のように規定されています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認または放棄をしなければならない」
裁判例でも、期限を過ぎた後の相続放棄については原則として認められていません。ただし、次のような例外も一部存在します。
- 死亡を知ることが困難だった場合
- 熟慮期間の伸長申立が認められた場合
しかしながら、いずれも例外的な扱いであり、厳格に運用されると考えるべきです。
3ヶ月以内に必ず行うべきこと
財産・負債の調査の重要性
相続放棄の判断をするには、被相続人にどのくらいの負債があるか、どのくらいの財産があるかを調べる必要があります。
例えば預貯金、貸金業者からの借入、不動産の有無などをリストアップするとわかりやすいです。
調査方法の例
- 預金通帳やローン契約書などの書類を家の中から探す
- 不動産があるなら登記情報を照会
- クレジットカードの明細を確認
- 税金の督促状や公共料金の督促状をチェック
家庭裁判所への申述書提出が期限内完了の鍵
調査と並行して、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を早めに入手して記載を進めることがおすすめです。
申述書は裁判所のサイトからダウンロードできるため、自宅で印刷して記入可能です。
必要な書類として、被相続人との続柄を示す戸籍一式や住民票除票などが挙げられます。期限内に申述書の提出を終えると、裁判所から照会書が届く流れになります。
書類不備や書き方ミスがあると、追加の提出が求められる場合があるため、締切間際だと焦りが生じやすいです。
迷っているときでも、まずは申述書だけ先に出す方策があります。そのあたりは後述の「相続放棄の期限が迫っているときの対処法」で解説します。
相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?
3ヶ月の熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。知らずに過ぎてしまう人もいますが、その場合は借金を含めた相続を受け入れる形となりやすいです。
例外的に、やむを得ない理由があると認められる可能性はありますが、あくまで少数です。期限をきちんと守るのが基本と考えて動きましょう。
原則は相続承認(単純承認)になる
「相続放棄の期限を知らなかった」は基本的に通用しない
相続放棄の仕組みを知らずに3ヶ月を過ぎるケースは珍しくありません。
しかし裁判所は「無知だった」という理由を大目に見ない傾向があります。法律上は期限を厳守するのが前提です。
放棄の意思があったと主張しても、提出が間に合わなければ単純承認とみなされるリスクが大きいです。
借金返済の義務が発生する場合も
期限切れによって単純承認になると、被相続人の貸付やローンなどをすべて引き継ぐことになります。消費者金融や銀行から請求がくる展開になれば、相続人が返済を負う流れです。
知らなかったでは済まされず、大きな負担が発生します。事情によっては別の親族が立て替えてくれる場合もあるかもしれませんが、法的には相続人に支払う義務が課せられます。
やむを得ない事由がある場合の例外(熟慮期間経過後)
期限後に多額の借金が見つかったケース
調査してもわからなかった借金が、熟慮期間終了後に判明した場合、改めて相続放棄を申し立てられる可能性があります。
「期間の起算点が後ろにずれる」とみなすかどうかは、家庭裁判所の判断次第です。
ただし簡単には通らないケースが多いです。自分が知らなかっただけでは認められない場合が多く、客観的にやむを得ないと判断される資料が要ります。督促状が来る前に調べればわかったのに放置していた、という状況なら却下されやすいです。
再転相続(先順位の相続放棄により自分が相続人になった場合)
親からの相続を放棄した結果、別の家族が相続人になり、さらにその人も亡くなったために自分が新たに相続人となる展開があるかもしれません。こうした形を再転相続と呼ぶケースがあります。
この場合は、あらためて「相続を知ったとき」から3ヶ月を数えることになる可能性が考えられます。タイミングを誤ると期限がずれてしまうため、慎重な確認が必要です。
判例・実例から見る認められる可能性と限界
期限後の相続放棄が通るかどうかは、判例や実例を見ても厳しい面が強いです。
相続の開始を認識していたのに、放置していた事実があると許可は難しいです。
やむを得ない理由を裏づける証拠の収集もかなり手間がかかります。
したがって、熟慮期間内に対応を終えるのが王道と言えます。先送りをせず、3ヶ月の間にしっかり書類を提出しましょう。
相続放棄の期限が迫っているときの対処法
気づいたら残り数週間しかない、という状態でも諦める必要はありません。
申述書だけを先に出す方法や熟慮期間の伸長申立を考えてみましょう。ただし後回しにしてしまうとさらに時間が減るので、早急な行動が大事です。
相続放棄申述書だけを先に提出する方法
とりあえず申述書を出して期限を確保
書類収集に手間取っていて期限に間に合うか心配なときは、申述書を先行して提出しておく手段があります。申述書には最低限の情報を記載し、添付できない戸籍などは後日送付する形です。裁判所から指示があれば、不足書類を追送できます。あくまで期限内に「放棄の意思」を届けることを優先する意味合いがあります。
ただし、必要書類があまりに欠けていると、実質却下されるケースもあるため、ある程度は揃えておくほうがよいです。加えて、提出済みの書面を補正する際のやり取りにも時間がかかります。
後から不足書類を追送する際の注意点
不足分を後出しする場合は、裁判所から催促の連絡があるかどうか注視してください。
期限後に送付しても「意思表示が間に合わなかった」と判断されると却下される恐れがあります。送付時には記載漏れがないよう慎重に確認しましょう。郵送する場合は配達記録を残す方法が安心です。
熟慮期間(3ヶ月)の伸長申立てをする方法
伸長が認められる条件と認められない場合
調査がどうしても長引いているとき、家庭裁判所に「熟慮期間を延ばしてほしい」と申立てるやり方があります。ただし認められるハードルは高いです。
たとえば「被相続人の財産が海外にあり調査に時間がかかる」「他の相続人との連絡が難しく、正確な金銭情報を集められていない」など明確な理由があれば通る可能性があるようです。
一方、ただ「仕事が忙しくて準備できなかった」という理由だけだと伸長は難しいです。詳しい書類や証明を添えて申立をする必要があります。
申立書の書き方・必要書類
伸長申立にも専用の書面があって、家庭裁判所の様式を用意するのが一般的です。理由欄には、どんな事情で調査に支障が出ているかを説明しましょう。
例えば「海外在住の相続人が書類を出すのに時間が必要」「被相続人が海外資産をもっていた形跡があり確認が進んでいない」などを詳しく伝える形です。
受理されたとしても伸長期間はさほど長くはならない可能性があります。あくまで緊急避難的な手段です。
自分でやる?専門家に依頼する?費用と手間の比較
相続放棄は自分ひとりで進めることもできますが、「3ヶ月」という期限を考えた際、書類の準備や戸籍の取得に時間がかかる点や、記入ミスのリスクも考慮しましょう。対して専門家に任せる場合は費用がかかりますが、手続きの漏れやミスが減る利点があります。状況によってどちらを選ぶかは異なります。
自力で手続きを進める場合のポイント
必要書類の取得先や取得費用
- 戸籍は本籍地の役所に郵送請求または窓口請求
- 住民票除票は死亡時の住所地で発行
- 1通あたり数百円の手数料がかかる場合が多い
書類が多いと発行手数料が負担になるかもしれません。往復の郵送費も考えると、数千円程度にはなる可能性があります。遠方に住んでいる場合はさらに時間がかかるので、早めの対応が望ましいです。
仕事が忙しい人でもスムーズに進めるコツ(郵送・休日活用など)
平日昼間に役所へ行く時間がとりづらい場合は、郵送請求を活用できます。具体的には以下の手順が考えられます。
- 役所のホームページから戸籍請求の用紙をダウンロード
- 必要事項を記入し、手数料分の定額小為替か郵便小為替を同封
- 返信用封筒を入れて郵送
休日に必要書類を揃えて郵便局へ行けば、平日に職場を抜ける必要が少なくなります。締切までのカウントダウンがあることを念頭に、無理なく段取りを進めましょう。
弁護士・司法書士に依頼するメリット・デメリット
書類作成代行・法的アドバイスの安心感
専門家へ頼むと、書類の記載漏れや起算日の計算をサポートしてもらえます。法律的なトラブルになりそうなとき、弁護士なら交渉にも対応しやすいです。
期限間近で自力の準備が間に合わない場合や、負債が大きく家族と争いになりそうな場合は、専門家を検討すると負担を減らせます。ただし費用負担が生じる点を踏まえて自分の予算と照らし合わせる形が求められます。
相続放棄の期限に関するQ&A
最後に、よくある質問をまとめます。期限をめぐる疑問は多いです。自分と似た疑問がある人は参照してみてください。
3ヶ月を過ぎてしまったのですが借金の存在を今知りました。放棄は可能?
原則として、相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内」に行わなければなりません。しかし、やむを得ない事情により借金の存在を後から知った場合には、その時点を起算日と見なす余地があります。
たとえば、遺産がプラスだと思い込んでいたところ、後から多額の債務が発覚した場合などが該当し得ます。
ただし、「調査を怠っていた」「確認可能だったのに放置していた」など、自己の落ち度があると判断されれば、放棄は認められにくい傾向があります。
裁判所に対しては、以下のような資料を用いて「借金を知り得なかった合理的な理由」を説明する必要があります。
- 被相続人の郵便物や督促状の不存在
- 金融機関との取引履歴の欠如
- 税理士・司法書士等の証明書や調査結果
不安な場合は、相続に詳しい弁護士や司法書士に相談し、事情説明と証拠収集のサポートを受けるのが適切です。
相続人が複数いる場合の熟慮期間はどうなる?
相続人が複数いる場合でも、熟慮期間(3か月)は各人ごとに個別にカウントされます。たとえば、兄がすでに相続放棄をしていたとしても、それによって妹も自動的に放棄したことにはなりません。
妹自身が、自分の起算日をもとに、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
申述受理後に借金が新たに見つかった場合、追加で放棄する必要はある?
家庭裁判所で相続放棄の申述が正式に受理された後に、被相続人の新たな債務が判明した場合でも、追加で放棄を行う必要はありません。
相続放棄は、被相続人のすべての財産・債務を包括的に放棄する効力を持つため、受理された時点でその後に判明する負債にも原則として責任を負いません。
まとめ|早めの情報収集でトラブルを防ごう
相続放棄は期限との戦いともいえます。3ヶ月という区切りが過ぎると、借金を抱える状況になってしまう危険があります。相続放棄を考えるなら、書類の収集や家庭裁判所への申述をサッと進める動きが望ましいです。
3ヶ月という期限は意外と短い
熟慮期間の3ヶ月は長いようで短いです。被相続人が亡くなったときは葬儀などでバタバタしがちで、気づくと期限間近になっている例が多いです。
平日は仕事で忙しく、役所に行けず戸籍集めが間に合わなかったという声も聞かれます。そうならないために、葬儀後になるべく早い段階で行動してください。
自分の事情に合わせた方法を選択する
「戸籍収集くらいなら自力でできる」という人は、郵送やインターネットをフル活用して書類をそろえるとよいでしょう。
相続人同士で話がまとまらず困っているとか、複数の借金が同時に存在していて複雑など複合的な問題がある場合は、弁護士を検討する選択もあります。状況に合わせて方法を見きわめる動きが必要です。
将来に備えて家族・親族との情報共有も大切
親や親族と疎遠だと、死亡の連絡が遅れたり、借金や資産に関する情報が伝わらなかったりするケースがあります。慌てて期限を迎える可能性があります。
普段から最低限の情報共有があると、実際に相続が始まったときにスムーズに動けます。家族や兄弟と話す際に、「もしものときに備えて連絡手段を確保しよう」と提案するだけでも変わるでしょう。
相続放棄で悩んでいる方は、まず期限を意識しながら書類収集や申述書の記入を進めてみましょう。定められた期間内に家庭裁判所へ申立を行うだけでも、リスク軽減が期待できます。もし財産の調査が間に合わないなら、熟慮期間の伸長申立など追加の方法を視野に入れてください。
当事務所では、借金問題や相続放棄に関する相談を受け付けています。専門家の知識を活用しながら適切な選択をしたいと考える方は、ぜひご連絡ください。
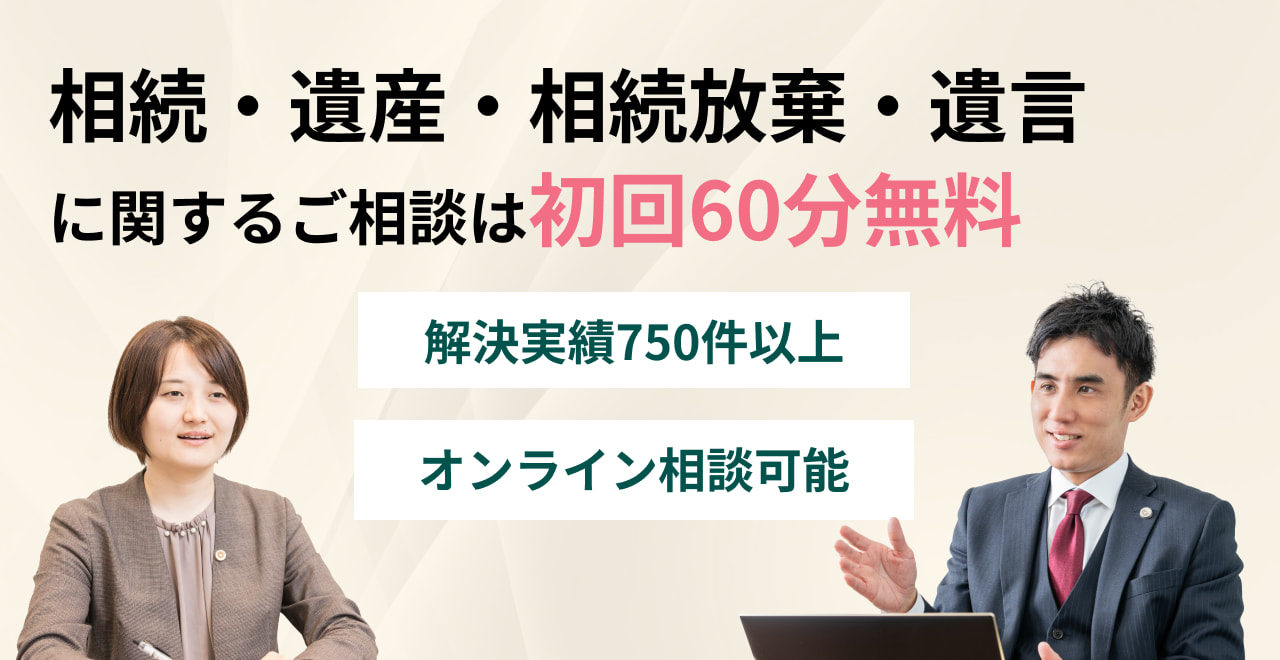
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。