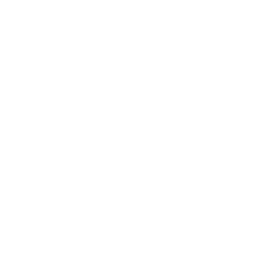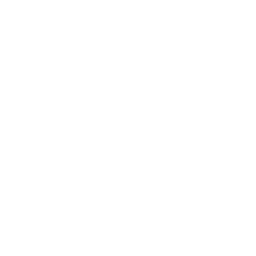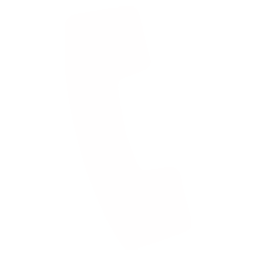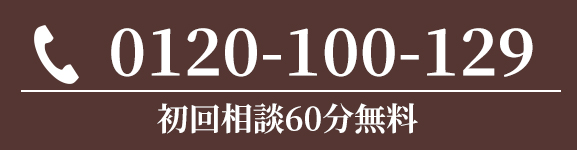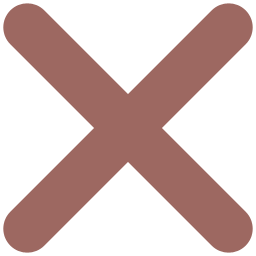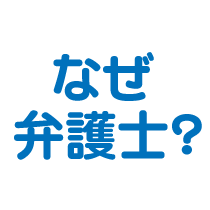相続放棄した空き家の管理義務は残る?【2023年法改正対応】知らないと危険な義務の判断基準と免れる方法を徹底解説
更新日:2025/11/12
「相続放棄すれば、価値のない空き家の問題は終わりだと思ってたのに…」
「管理義務が残るって本当?もし台風で家が壊れたら、私が責任を負うの?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、以下の内容がわかります。
- ・あなたが管理義務を負うかどうかの判断基準
- ・管理義務を放置した場合の最悪のリスク
- ・管理義務から完全に解放されるための具体的な方法
2023年4月の民法改正により、相続放棄をした場合の空き家の管理義務についての取扱いが見直されました。
改正後は、相続放棄をしてその家に実際に住んでいない(占有していない)場合には、原則として管理義務を負わないことになりました。
これまでの制度では、「放棄しても責任が残るのでは?」といった曖昧さがあり、相続人に大きな負担となっていました。
しかし、法改正によって誰が責任を負うのかが明確になったのです。
とはいえ、「自分の場合はどちらに当てはまるのか」「何か手続きをしておく必要があるのか」など、判断に迷う方も少なくありません。
この記事を読むことで、あなたが管理義務を負うのかどうかが明確になり、将来の不安を解消するための具体的な行動がわかります。
さっそく、新しいルールの中身から確認していきましょう。
第1章:【結論】2023年民法改正で空き家の管理義務はこう変わった!
2023年4月1日に施行された民法改正により、相続放棄をした後の空き家の管理義務についてのルールが明確になりました。
改正後は、相続放棄をした人が**「その財産を実際に使ったり、管理したりしている(現に占有している)」場合に限って**、管理義務を負うことになっています。
つまり、相続放棄をした人がその空き家を事実上支配していない限り、原則として管理や保存の責任を負う必要はありません。
このように「現に占有している」という具体的な基準を設けたことで、相続放棄をした人が過度な負担を負わされることを防ぐ狙いがあります。
改正前は、相続放棄をした人の管理責任があいまいで、思わぬ負担を強いられるケースもありました。
たとえば、相続人が全員放棄した場合、最後に放棄した人が遺産を管理し続けなければならないとされることがあり、被相続人と疎遠で遠方に住む人でも、空き家の管理を求められる可能性がありました。
法改正の全容について、重要な変更点を以下にまとめます。
-
①義務を負う人の明確化:「現に占有」
改正後の民法第940条第1項では、以下のように義務を負う主体が明確化されました。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
-
②呼称の変更:「管理義務」から「保存義務」へ
条文の見出しも改正前の「管理義務」から改正後は「保存義務」へと変更されました。この呼称変更は実質的な義務内容を変えるものではなく、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存しなければならない」との法律表現に合わせ、より適切な用語に見直したものです。
-
③呼称の変更:「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へ
「相続財産管理人」と呼ばれていたものも「相続財産清算人」に変更されました。これは、その人の役割が相続財産の清算である点を明確にするための変更です(改正民法952条)。
2023年の法改正によって責任を負う人の条件が明確になり、「現に占有している相続放棄者のみが管理(保存)義務を負う」ことがはっきり示されました。
これにより、遠方に住んでいて空き家と関わりがない相続放棄者は、原則として管理義務を負わないことが法律上明確になっています。
第2章:【自己診断】あなたが管理義務を負うかの判断基準「現に占有」とは?
あなたが管理義務を負うかどうかの判断基準である「現に占有」とは、対象の空き家を事実上支配・管理している状態を指します。
これは法律上の権利(所有権など)があるかどうかとは別で、その物を現実にコントロールしている客観的な状態を意味します。
2-1. 解説:「現に占有」とは、財産を事実上支配している状態
「現に占有」とは、端的に言えば、その物を実際に管理下に置いている状態です。
例えば、被相続人の家に相続人が住んでいる場合、その相続人はその家を現に占有しているといえます。
この場合、その相続人が相続放棄をしても、引き続きその家を保存(適切に維持)する義務を負います。
なお、「占有」には自分で物を所持・管理する直接占有だけでなく、他人を通じて支配する間接占有も含まれます。
例えば、空き家を他人に賃貸している場合、借主が直接占有者ですが貸主であるあなたは間接占有者となります。
そのため、自分が住んでいなくても人に貸している空き家であれば、事実上その空き家を支配しているとみなされ、「現に占有」に該当し得る点に注意が必要です。
この「現に占有」という判断基準はまだ新しく、判例の蓄積が十分とはいえません。
最終的には個別事情に応じて判断されるため、「自分の場合は占有に当たるのか?」と迷ったら専門家に相談することをおすすめします。
2-2.【ケース別】これは「占有」にあたる?チェックリスト
ご自身の関わり方が「現に占有」に該当するかの目安として、以下のケースをチェックしてみましょう。
-
実家の鍵を持っているだけ
→ この事情のみからは、占有とは言い難い可能性が高いです。
鍵を持っているだけでは直ちに事実上支配しているとは言えません。
ただし、鍵を預かって自由に出入りできる状況で他に管理する人もいないような場合は、状況次第で評価が変わる可能性もあります。
-
定期的に掃除や草むしりをしていた
→ 占有と評価される可能性があります。
空き家の維持管理に積極的に関与していると、事実上の支配、つまり「現に占有」していると判断される可能性があります。
-
空き家に自分の私物を置いている
→ 占有と評価される可能性は高いです。
自分の物を継続的に置いている行為は、その場所を支配的に利用している証拠と見なされやすいでしょう。
-
被相続人と同居していた
→ 明確に「現に占有」に該当します。
亡くなった親と同じ家に住んでいた相続人が相続放棄した場合、その家には引き続き住んでいるわけですから、「現に占有している財産」として管理(保存)義務を負うことになります。
2-3. 自分が「最後に相続放棄した人」かどうかの確認方法
管理義務は、相続放棄者全員が負うわけではなく、最後に残った相続放棄者に集中します。
ここで「最後に残った」とは、相続権が次順位に移らなくなった段階で、現に占有している相続放棄者がいる場合を指します。
相続には以下の法定順位があります(民法887条~889条)。
- 第1順位:子(子が死亡している場合は孫など直系卑属)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)
例えば、第1順位の子全員が相続放棄すると、相続権は第2順位の父母に移ります。
父母も放棄すると、第3順位の兄弟姉妹へと権利が移転します。
そして最終的に相続人となる人がいなくなった時点で、相続財産清算人の選任がされない限り、最後に放棄をした相続人(その人が財産を現に占有していた場合)に管理義務が生じます。
したがって、ご自身が「最終順位の相続人」であり、かつ最後に放棄した者に該当するかを確認することが重要です。
戸籍謄本などで相続人の範囲や放棄状況を確認し、自分以外に相続人が残っていないかを調べましょう。自分が「最後の相続放棄者」にあたり、なおかつ前述の「現に占有」に該当するなら、管理義務を負う可能性が高いということになります。
第3章:管理義務が残る場合に放置した場合の全リスク
相続放棄後もあなたが空き家の管理(保存)義務を負う場合、その義務を怠ると損害賠償請求、行政からの介入、近隣トラブルや犯罪誘発という深刻なリスクに直面します。
3-1.【リスク①】損害賠償請求:最も怖い金銭的リスク
管理義務を怠った結果、空き家が原因で第三者に損害を与えてしまった場合、管理者(保存義務者)として損害賠償責任を問われる可能性があります。これは民法第717条の土地工作物責任や不法行為責任の問題です。
具体的な事例
例えば、老朽化した空き家の屋根瓦が台風で飛ばされ、隣家の太陽光パネルを直撃して壊してしまったとします。
修理に50万円かかった場合、隣家から50万円の損害賠償を請求される可能性があります。
民法717条では、建物など土地の工作物の占有者(事実上支配している人)がその瑕疵(管理不備)によって他人に被害を与えた場合、まず占有者が責任を負うと定められています。
相続放棄者であっても「現に占有」している以上はこの占有者に該当し、第三者に対して賠償責任を問われうる点に注意が必要です。
3-2.【リスク②】行政からの介入:特定空き家指定と行政代執行
管理不全な空き家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、行政指導の対象となります。行政からの措置は段階的に強まります。
- 助言・指導:まず、市区町村など自治体から「適切に管理してください」という助言や指導が行われます。
- 勧告:「特定空家等」に指定され、改善勧告が出されます。この時点で固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍になる可能性があります。
- 命令:勧告にも従わない場合、改善命令が出されます。命令に違反すると、50万円以下の過料が科される可能性があります。
- 行政代執行:命令にも従わない最終段階では、自治体自らが建物の解体などを行い、その費用(一般的に100万円以上)を後で所有者等に請求します。
このように、行政の介入を無視し続ければ税負担の急増や罰金、強制執行による高額請求という経済的リスクが発生します。
3-3.【リスク③】近隣トラブルと犯罪誘発:平穏な生活への脅威
管理されていない空き家は、地域社会にも悪影響を及ぼします。
- 景観の悪化:庭の雑草が生い茂り、建物が荒れ放題になれば景観を損ねます。
- 衛生上の問題:害虫や害獣が発生しやすく、悪臭の原因にもなります。
- 犯罪の温床:不法侵入者に占拠されたり、放火や不法投棄に利用されたりする恐れがあります。
これらの問題は、近隣からのクレームに直結し、平穏な生活を脅かす要因となります。
第4章:【完全版】空き家の管理義務から解放されるための全手法
万一、あなたが相続放棄後も空き家の管理(保存)義務を負うことになった場合、その責任から合法的に解放される方法がいくつか存在します。
4-1.【王道かつ確実】相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる
相続財産清算人の選任は、管理義務から解放される最も確実な方法です。
相続財産清算人とは、被相続人の財産を管理・清算するために家庭裁判所が選ぶ弁護士等の専門家です。
- 役割:相続財産一式を引き継ぎ、管理・換価処分や債権者への支払いなど、一連の清算業務を行います。
- 期間:申立てから手続完了まで、通常は半年から1年以上かかります。
- 費用:申立て時に予納金を家庭裁判所に納める必要があります。一般に20万円~100万円程度とされています。
予納金は決して安くありませんが、一度清算人が選任され財産を引き渡せば、その後はあなたは管理義務から完全に解放されます。
4-2.【他に相続人がいる場合】次の相続人に財産を引き継ぐ
もしあなた以外に相続人が存在する場合、その次順位の相続人に相続財産を承継してもらうことで、あなた自身は管理義務を免れます。
ただし、あなたが放棄してから実際に次の相続人が財産を引き継ぐまでの間は、あなたに管理(保存)義務が残ります。
また、次の順位の相続人も全て相続放棄してしまった場合、この方法では解決しません。
4-3.【2023年新制度】相続土地国庫帰属制度の利用を検討する
2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」は、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。
【制度利用の主な要件】
- ・建物がない土地であること(更地であることが原則条件です。)
- ・担保権や使用収益権が設定されていないこと
- ・土壌汚染や埋設物がないこと
- ・境界に争いがないこと
- ・管理に過大な費用・労力を要しない土地であること(急傾斜地でないなど)
要件は非常に厳しいですが、満たせば不要な土地を処分できます。
費用として、審査手数料(土地1筆あたり14,000円)と、承認された場合に管理費用10年分相当の負担金(原則20万円)が必要です。
4-4.【最後の手段】専門業者への売却・自治体への寄付
相続放棄を選択する前に、空き家自体を手放す選択肢もあります。
空き家や古家専門の買取業者に売却すれば、迅速に現金化でき、以後の管理責任も完全になくなります。ただし、買取価格は期待できない場合が多いです。
また、自治体への寄付も考えられますが、自治体が利用目的のない不動産の寄付を受け入れることは極めてまれです。
「使い道がないから」という理由での寄付はほぼ不可能と考えてよいでしょう。
第5章:空き家の相続放棄|手続きの流れと失敗しないための全注意点
相続放棄の手続き自体を正しく理解しておく必要があります。期限や注意すべき行為など、知っておかないと取り返しのつかないポイントがあります。
5-1. 相続放棄手続きの基本フロー
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う「相続放棄申述」という手続きです。
- 必要書類の収集:被相続人の住民票除票や戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などを集めます。
- 申述書の作成:家庭裁判所のウェブサイト等から書式を入手し、必要事項を記入します。
- 家庭裁判所への申述:管轄の家庭裁判所に書類一式を提出します。費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手代です。
- 照会書への回答:後日、裁判所から相続放棄の意思などを確認するための照会書が届くので、回答して返送します。
- 受理通知書の受領:問題がなければ、相続放棄が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。
5-2.【重要】3ヶ月の期限(熟慮期間)を過ぎたらどうなる?
相続放棄には厳格な期限があります。民法915条1項により、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で申述をしなければなりません。
この3ヶ月間を「熟慮期間」と呼びます。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、単純承認(全て相続すること)をしたものとみなされます。
5-3. これをやると放棄できない!「単純承認」とみなされる禁止行為
熟慮期間内であっても、一定の行為をすると法律上、相続を承認したとみなされ、もう相続放棄ができなくなります。これを「法定単純承認」といいます(民法921条)。
典型的なNG行為
- 相続財産の処分:空き家を売却したり解体したり、価値のある家財を換金する。
- 相続財産の使用:被相続人の預貯金を引き出して自分の生活費に充てる。
- 相続財産の隠匿:借金から逃れる目的で価値のある財産を隠す。
相続放棄を考えているなら、相続財産に手を付けないことが鉄則です。
5-4. 次の順位の相続人への配慮は必要
あなたが相続放棄をすると、相続権は自動的に次の順位の相続人へ移ります。
法的な義務ではありませんが、次の順位の相続人への配慮が必要です。
第6章:【最終判断】相続放棄すべき?他の選択肢との比較
そもそも本当に相続放棄が最善の選択なのでしょうか。他の選択肢もあります。
6-1. あなたの状況はどれ?相続放棄を検討すべきケース
一般的に、以下のようなケースでは相続放棄を積極的に検討すべきと考えられます。
- 負債超過の相続:被相続人に多額の借金があり、資産を全て処分しても返済できない。
- 空き家が遠方で管理困難:物理的に管理ができず、管理義務を負うリスクを避けたい。
- 他の相続人と揉めたくない:遺産分割協議などで争いになることを避けたい。
6-2. 相続放棄「以外」の選択肢
- そのまま相続して自分で管理・活用する:リフォームして住む、賃貸に出すなど。
- 相続してすぐに売却する:不動産として市場価値があるなら、売却して現金化する。
- 相続して解体する:老朽化が激しい場合、更地にすれば管理の手間が減り、売却しやすくなる場合がある。
- 限定承認を利用する:プラスの財産の範囲内で負債を清算する手段。手続きが煩雑で相続人全員の合意が必要です。
6-3. 意思決定のための比較表
| 選択肢 | メリット | デメリット | 費用の目安 | 手間 |
|---|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 負債や管理義務から解放される | プラスの財産も全て失う | 裁判所費用数千円 | 少ない |
| 相続して売却 | 利益が出る可能性がある | 買い手探しや手続きが必要 | 仲介手数料、税金 | やや多い |
| 相続して活用 | 収益物件として活用可能 | 初期投資、継続的な管理が必要 | リフォーム代数十万~ | 多い |
| 相続して解体 | 管理が楽になる、売却しやすくなる | 解体費用が高額、固定資産税が上がる | 100万円~ | 中程度 |
| 限定承認 | 負債超過リスクを回避できる | 相続人全員での手続き、手続きが煩雑 | 予納金数十万円 | 多い |
第7章:【専門家が回答】相続放棄と空き家の管理義務に関するQ&A
Q1. 相続人全員が放棄したら、空き家は最終的にどうなりますか?
A1. 相続人が誰もいなくなった場合、その空き家は「相続人不存在」の状態となります。
利害関係人(債権者や自治体など)が家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人が選任されない限り、法律上は宙に浮いた状態で放置されます。清算人が選任されれば、財産は処分され、最終的に残った財産は国庫に帰属します。
Q2. 管理義務は、自分の子どもに引き継がれますか?
A2. いいえ、管理義務そのものが直接お子さんに引き継がれることはありません。
管理義務はあくまで「現に占有している相続放棄者」に課されるものです。
Q3. 市役所から「空き家を管理するように」と通知が来た場合、どう対応すべきですか?
A3. まず、通知を無視しないことが肝心です。
市役所の担当部署に連絡し、あなたが相続放棄をした事実と、2023年の民法改正により「現に占有」していない相続放棄者には管理義務がない旨を冷静に説明してください。
話がこじれる場合は、弁護士など専門家に相談し、自治体との対応を代理してもらうのが得策です。
Q4. 相談するなら弁護士と司法書士、どちらが最適ですか?
A4. 書類作成や手続き代行が中心なら司法書士でも対応可能です。
しかし、他の相続人との紛争や行政との交渉を含む場合は、弁護士にしか依頼できません。
迷ったら、弁護士の無料相談を利用し、自分のケースではどちらが適任かアドバイスをもらうと良いでしょう。
【まとめ】
2023年の民法改正で、相続放棄後の空き家の管理義務は「現に占有」していなければ原則負わなくなりました。
しかし、「現に占有」に当たるかの判断は簡単ではなく、自己判断で誤るリスクもあります。もし管理義務が残る場合にそれを放置すれば、損害賠償や行政処分といった深刻な事態に発展しかねません。
もし管理義務が残る場合に放置すると、損害賠償や行政処分のリスクがあります。義務から解放されるには、相続財産清算人の選任を申し立てる方法が確実です。
相続放棄には「知ってから3ヶ月」という厳格な期限があります。ご自身の状況を確認し、早めに専門家へ相談しましょう。
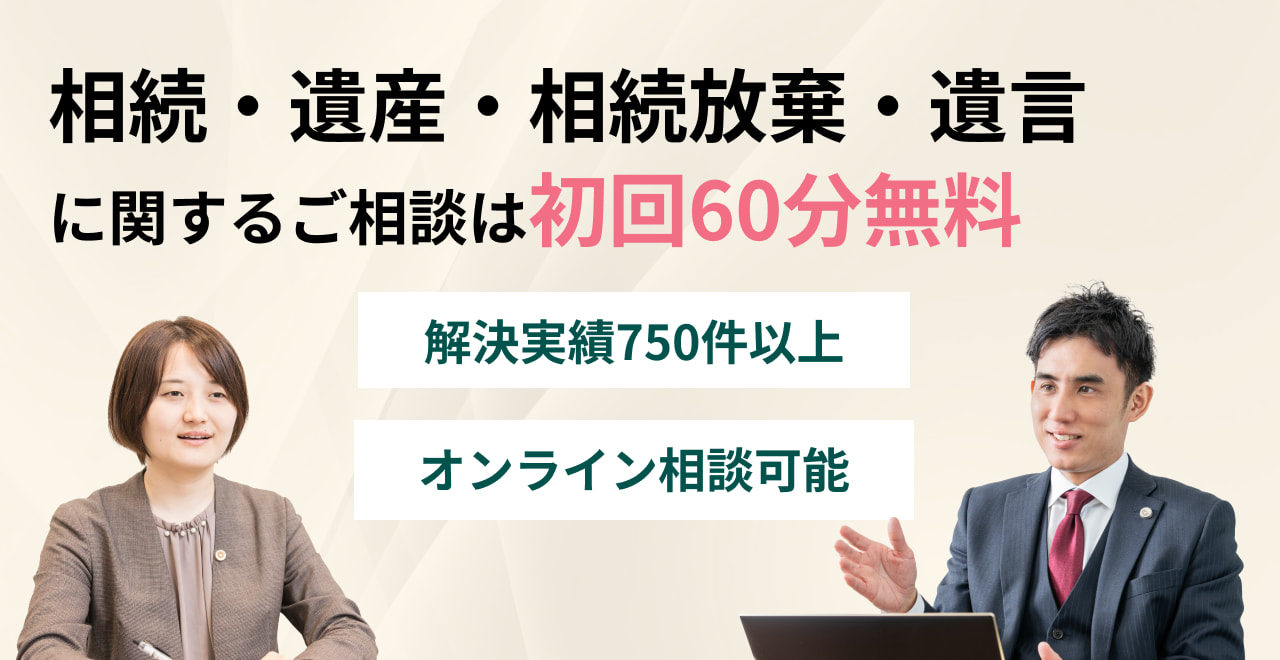
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。