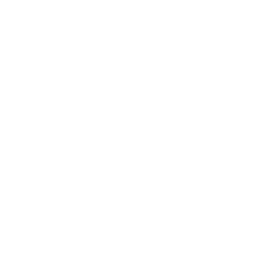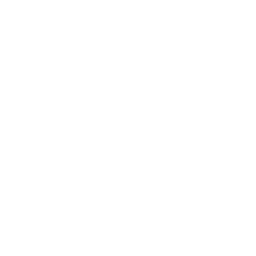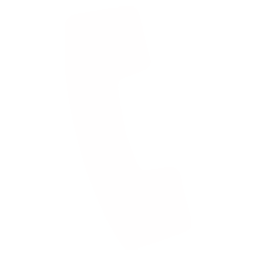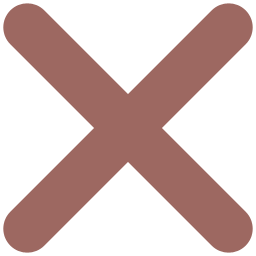遺言という制度
更新日:2022/10/17
遺言という制度

第1 遺言の自由と要式行為性
1 遺言とは
遺言とは、法律が定める方式に従い、自らの死後に、自らの財産や身分に関する事柄に関して行われた意思表示のことをいいます。世間一般には「ゆいごん」として知られることが多いですが、法律用語としては「いごん」と読みます。
2 遺言は「単独行為」であり且つ「要式行為」である。
(1)遺言は相手方のいない意思表示
遺言は、「単独行為」です。単独行為とは、単独の意思表示によって法的効果を生じさせる行為のことです。つまり、「契約」のように意思表示の相手方を必要とせず、遺言者が単独の意思表示によって法的効力を発生させることができます。事前に相続人の承諾を取っておく必要もありません。
(2)要式行為としての遺言
遺言は、「様式行為」とされています。「要式行為」とは、法律が定める一定の様式(方式)を備えた場合にのみ有効とされる法律行為(意思表示等)のことです。裏を返せば、法律が定める様式を備えていない意思表示は、一律に無効と扱われます。例えば、被相続人がビデオレターで遺産の分配を指示していたとしても、これは日本法の定める様式に適合しないため無効となります。そこで述べられていることが真実であるか否かを問題とせず、一定の様式を備えない限り一律に無効と扱われるのが重要なポイントです。
(3)遺言と条件
遺言には、条件を付すことができます。遺言に「停止条件」(法律行為の効果の発生が将来の不確実な事実の発生・不発生に掛る場合の条件)が付された場合、この遺言は、当該条件が成就した場合に初めて効果を生じます。
3 共同遺言の禁止
(1)共同遺言は無効
共同遺言とは、複数名で共同して遺言を行うことです。民法は、この共同遺言の効力を無効と定めています(民法975条)。これは、共同遺言を認める場合、本質的要求である遺言の自由や遺言撤回の自由について遺言者各人の権利の確保に支障を来すことが想定されるためです。
(2)共同遺言か否かの判断
では、「共同遺言」か否かはどのように判断されるのでしょうか。民法975条は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と定めていますが、これは、形式的に見て一つの遺言書に、複数の遺言者の氏名や遺言内容が記載されているだけで無効とするものではないと解されています。共同遺言と言えるためには、複数の遺言者の意思表示が遺言者ごとに峻別できない状態で1つの遺言書に記載されていることが必要です。つまり、一つの遺言書に複数人の遺言内容が記載された場合でも、各自の遺言事項が独立して記載され、内容的にも互いに関連し合わないものであれば共同遺言には当たらず有効となります。もっとも、現実問題として、一つの遺言書に複数の遺言が記載されている場合は、その多くが互いに関連し合っているケースが多く共同遺言に当たるでしょう。
無意味な争いを起こさないためにも、遺言は単独で行うべきと言えます。
4 遺言によって定めることのできる事項
先程説明しましたとおり、遺言は、単独行為であり、契約のように他者との合意を必要とすることなく、法的効果を発生させることができます。しかし、無制限にこれを認めてしまうと、その内容次第で利害関係人や社会公共の利益に好ましくない影響が及んでしまいます。そのため、法は、遺言によって定めることが事項を制限しています。一般に、遺言によって定めることのできる事項は、以下の15個と言われています。このうち、社会的に馴染みが深いのは、④・⑤・⑥・⑦・⑩・⑪のような財産に関する事項でしょう。
①認知
②未成年後見人・未成年後見監督人の指定
③相続人の廃除や排除の取消
④祭祀に関する権利承継者の指定
⑤相続分の指定や指定委託
⑥特別受益の持戻し免除
⑦遺産分割方法の指定や指定委託
⑧相続開始から5年を超えない機関での遺産分割の禁止
⑨相続人相互間での担保責任の分担
⑩相続財産の全部または一部の処分(遺贈)
⑪遺言執行者の指定や指定委託
⑬一般財団法人の設立
⑭一般財団法人への財産の拠出
⑮生命保険及び障害疾病定額保険における遺言による保険金受取人の変更
第2 遺言の解釈
1 遺言内容が不明確な場合
弁護士が関与することなく作成された遺言は、法的観点でみると内容が曖昧で解釈によって意味の捉え方が変わってしまうものがあります。
このような内容不明瞭な遺言をどのように取り扱うべきか(無効と判断すべきか、それとも裁判所が積極的に遺言者意思を判断すべきか)という点は、法律上重要な意味を持ちます。
2 最終意思の尊重
現在の家庭裁判所の実務では、このような内容不明瞭の遺言も簡単に無効とはせず、積極的に遺言者意思を判断することで可能な限り遺言を有効なものとして取り扱う傾向にあります。遺言書に記載されている複数の条項のうち一つの解釈が問題となった場合、裁判所は、他の条項も含めた遺言書全体の記載や、遺言書作成当時の事情や遺言者の置かれた状況まで加味して遺言者の意思を推認して判断するものとされています。
第3 遺言能力
1 遺言能力とは
「遺言能力」とは、遺言ができる能力(資格)のことです。遺言は誰でも行える訳ではなく、法律が認める者(遺言能力者)のみが行うことができます。遺言能力には2つの要素があると言われています。1つは意思能力者であること、もう1つは15歳以上であることです。
意思能力というのは、事理弁識能力といわれ、物事の是非や利害を認識・理解する能力とされています。目安としては7~10歳程度の理解力と言われていますが、実際には具体的な事情を顧慮した上で裁判所が判断します。意思能力の問題は、遺言に限った話ではありません。意思能力を欠く意思表示はいずれも無効とするのが民法一般の理解です。例えば、酒に酩酊して物事を正常に判断できない状態でした契約(意思表示)は無効とされます。
遺言に特筆した話で重要なのは、後者の方です。たとえ意思能力を備えていても、年齢が15歳未満の者が行った遺言は、遺言能力を欠く者が行った遺言として一律に無効とされます。
2 行為能力制限制度の不適用
我が国では、遺言に関しては行為能力制限制度が適用されません。「行為能力制限制度」とは、未成年者や、知的障害等によって物事の判断能力が不足ないし喪失している者のうち家庭裁判所の審判によって成年後見人・補佐人・補助人が就けられた者について、その者が法律行為の有効性を制限することで本人の権利を擁護する制度です(実際には、ノーマライゼーションという重要な理念も含む制度ですが、本論と離れるためここでは割愛します。)。
遺言については、15歳以上の年齢にあり意思能力を備えた者であれば、たとえ未成年者であっても親権者の同意を得ることなく有効に行うことができます。たとえ、その内容が親権者の希望に反するものであっても、親権者はその効力を否定することができません。
また、成年被後見人や被補佐人・被補助人についても同様です。もっとも、成年被後見人の場合は、意思能力の回復状況やその真意の推認が極めて困難となるため、法は、一定の制限を課しています。この点は、後述します。
3 遺言をするための能力が備わっている時期
遺言能力を備えておくべき時期は、遺言を行う時です。遺言作成時に遺言者が15歳未満であった場合、たとえ死亡時に遺言者が15歳以上になっていたとしても当該遺言は無効です。
逆に、遺言作成時に15歳以上でかつ意思能力を備えていれば、事後的に意思能力を失うに至ったとしても当該遺言は有効と扱われます。
4 成年被後見人が遺言を行うには
(1)成年被後見人の遺言についての制限-真意確保の目的
先程述べたとおり、成年被後見人であっても意思能力及び15歳以上である限り遺言能力が認められます。もっとも、成年被後見人はそもそも「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」と判断されてその地位に置かれているため、遺言時点において意思能力を備えているか(回復しているか)という判断には、慎重を期すことが求められます。また、遺言内容が遺言者の真意に基づいているかという点も常に疑いの余地が残ります(一部の利害関係人が自身に有利な内容の遺言をさせようと資産を有する成年被後見人に働きかける状況は容易に想像できます。)。
そのため、法は、成年被後見人が遺言を行う際は、真意確保の観点から、医師2人以上が立会った上、当該医師において「遺言者が遺言時に精神上の障害により事理弁識能力を書く状態になかった」旨を遺言書に付記して署名・押印させることを求め、これらの要件に反した遺言を無効としています。成年被後見人の遺言については、様式性の要件が付加されているのです。
(2)成年被後見人の遺言全般に関する制限-適正な後見事務遂行確保の目的-
成年被後見人、あるいは、未成年後見人が付された未成年者が行った遺言のうち、成年後見人による後見の計算が終了する前に行われたもので、且つ、後見人またはその親族(配偶者及び直系卑属)の利益となるものは無効とされます。
これは、成年被後見人が後見人の影響を受けやすいことを考慮して、後見業務の不正行為を事前に予防するために設けられたルールです。
ただし、後見人が被後見人の直系血族、配偶者、兄妹姉妹であるときは、例外的に有効とされます。
遺言についてご相談をされたい方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスにご連絡下さい。
初回相談は60分無料で、来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。まずはお電話でお問合せください。
0120-100-129
(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)