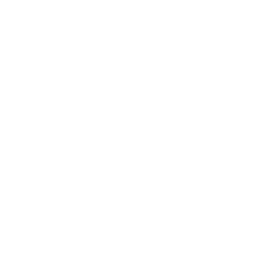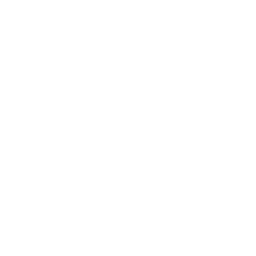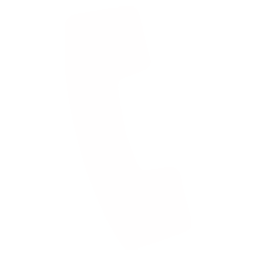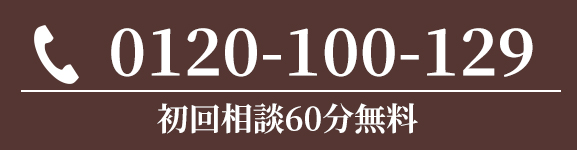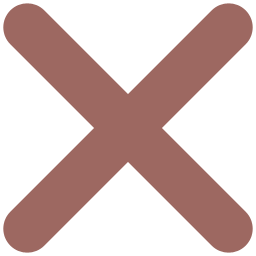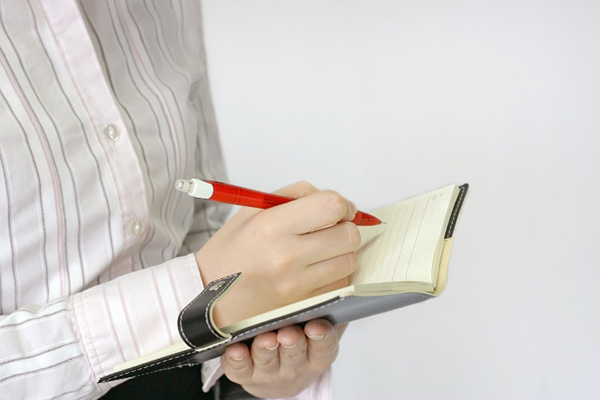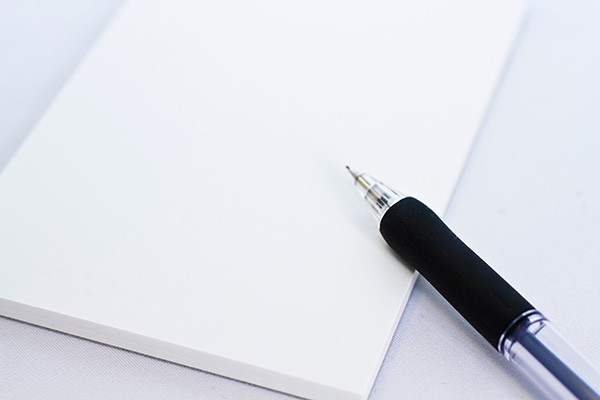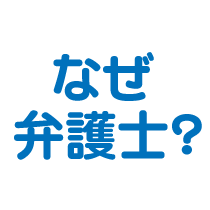成年後見人がいる相続はどうなる?手続きの流れから注意点まで
更新日:2025/11/11
成年後見人がいる相続はどうなる?手続きの流れから注意点まで
「親に成年後見人がついているけど、亡くなった後の相続手続きってどうなるの?」
「専門家の後見人が主導すると、知らないうちに不利な条件で話を進められないか心配…」
大切なご家族の相続だからこそ、悩みは尽きません。この記事では、成年後見人が関わる相続について、以下の3つのポイントを軸に解説します。
- 【ケース別】成年後見人が関わる相続手続きの全手順
- 相続で失敗しないための5つの注意点
- 揉め事を避けるための生前対策
結論をいうと、成年後見人が関わる相続を円満に進めるには、ご自身の状況に合った手続きの流れを理解し、注意点を押さえることがすべてです。
知識がないまま手続きを進めると、ご家族の関係に思わぬ亀裂が入ったり、受けとれるはずの財産が減ってしまったりします。
親を想うからこそ、ご自身の家庭も大切にしたいからこそ、何から手をつけていいかわからず不安になることもあると思います。
この記事を最後まで読むことで、成年後見人が関わる相続の全体像がわかり、あなたのケースで「次に何をすべきか」が明確になります。
さっそく、円満相続への第一歩を踏みだしましょう。
1. 成年後見制度と相続の基本|なぜ後見人が必要なのか?
成年後見制度と相続の基本から解説します。
なぜ相続手続きで成年後見人が必要になるのか、その理由と制度の役割を理解することで、ご自身の状況を正しく把握する第一歩になります。
1-1. 成年後見制度とは? 判断能力が不十分な方の財産を守る制度
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、ご自身の財産を管理したり、契約を結んだりすることが難しい方の権利と財産を守るための制度です。
判断能力が不十分になると、例えば以下のような場面で不利益を被る可能性があります。
- 悪徳商法による被害: 必要のない高額な商品を契約させられる。
- 不動産の管理不全: 自宅の修繕や固定資産税の支払いができなくなる。
- 介護サービスの契約: 自分に必要な介護サービスの内容を理解し、契約を結べない。
このような状況を防ぐために、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、ご本人に代わって財産の管理や必要な契約をおこないます。
成年後見人は、ご本人の意思を尊重しながら、その方の利益になるように法律面や生活面で支援する役割を担います。
つまり成年後見制度は、ご本人が安心して生活を送れるように、法的な権限をもった支援者(後見人)が財産と権利を守る仕組みです。
1-2. 相続で後見人が必要になる2つの立場
相続の場面で成年後見人が関わるケースは、大きくわけて2つの立場があります。
ご自身の状況がどちらに当てはまるかによって、後見人の役割や手続きの進め方が全く異なりますので、最初に確認しましょう。
| 立場 | 後見人の主な役割 | 手続きの概要 |
|---|---|---|
| 立場①:【被相続人】(亡くなった親など)に後見人がいた | 亡くなった方の財産を管理し、相続人へ正確に引き継ぐ | 後見人が財産目録を作成し、相続人に財産を引き渡して任務終了 |
| 立場②:【相続人】(兄弟など)に後見人がいる | 本人に代わり、他の相続人と遺産分割協議に参加する | 遺産分割協議がまとまれば、後見人が協議書に署名捺印する |
このように、亡くなった方に成年後見人がいたのか、それとも相続人の中に後見人が必要な方がいるかで、成年後見人がおこなう仕事の内容は大きく変わります。
まずは、ご自身の状況が「立場①」と「立場②」のどちらなのかをはっきりさせることが、今後の手続きをスムーズに進めるためのスタートラインです。
2. 【ケース別】成年後見人が関わる相続手続きの全手順
ここでは、成年後見人が関わる相続手続きの具体的な流れを、先ほどの2つのケースにわけて解説します。ご自身の状況に合わせて、必要な手順を確認してください。
2-1. ケース①:【被相続人】に後見人がいた場合の手続きの流れ
亡くなった親御さんなどに成年後見人がついていた場合、後見人の仕事はご本人の死亡によって原則として終了します。
後見人は相続人の代理人ではありません。そのため、後見人は遺産分割協議には参加せず、管理していた財産を相続人に引き継ぐまでが最後の仕事になります。
手続きは主に以下のステップで進みます。
ステップ1:後見人への死亡連絡了
ご本人が亡くなられたら、まず後見人(弁護士や司法書士、親族など)に速やかに連絡を入れます。
ステップ2:財産の調査・管理
後見人は、ご本人が亡くなった後も、相続人に財産を引き継ぐまでは財産を善良に管理する義務があります。
この間に発生した医療費や公共料金などの支払いも、後見人が管理財産から支払います。
ステップ3:家庭裁判所への報告
後見人は、ご本人が亡くなったことを家庭裁判所に報告します。
同時に、最後の仕事としておこなった財産管理の状況についても報告が必要です。
ステップ4:相続人への財産引き継ぎ
後見人は、管理していた全財産について「最終財産目録」と「収支計算書」を作成します。
相続人は、後見人からこれらの書類を受けとり、内容をしっかり確認してください。預金通帳のコピーなど、関連資料も一緒に提示を求めましょう。
内容に問題がなければ、相続人全員が「受領書」に署名・捺印し、後見人から預金通帳や不動産の権利証などの財産を引き継ぎます。この引き継ぎをもって、後見人の財産管理業務は完了です。
ステップ5:後見終了の登記
後見人は、法務局で「後見終了」の登記申請をおこないます。
2-2. ケース②:【相続人】に後見人がいる場合の手続きの流れ
兄弟姉妹など、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ無効になるからです。
そのため、判断能力が不十分な相続人の代理人として、成年後見人が遺産分割協議に参加します。手続きは主に以下のステップで進みます。
ステップ1:遺産分割協議の準備
成年後見人は、他の相続人から提示された遺産分割案を検討します。
後見人の最も重要な役割は、ご本人(被後見人)の権利を守ることです。そのため、少なくとも法律で定められた「法定相続分」を確保できるように交渉します。
ご本人にとって不利な内容(例えば、法定相続分を大きく下回る内容)の遺産分割案に、後見人が同意することはありません。
ステップ2:後見人が遺産分割協議に参加
相続人全員と成年後見人が集まり、遺産分割協議をおこないます。
後見人は、あくまでご本人の代理人として、その方の利益のために意見を述べます。感情的な話し合いになるのではなく、法的な観点から冷静に協議が進められます。
ステップ3:遺産分割協議書の作成・署名捺印
相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
成年後見人は、ご本人に代わって遺産分割協議書の内容を確認し、署名・捺印をおこないます。この署名・捺印により、協議内容は法的に有効なものになります。
ステップ4:協議内容に基づき相続手続きを実行
作成した遺産分割協議書にもとづき、不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約・分配などの具体的な相続手続きを進めます。
ステップ5:後見人が本人に代わり財産を取得・管理
遺産分割協議の結果、ご本人が取得することになった財産(不動産や預金など)は、成年後見人がご本人に代わって受けとり、管理します。
取得した財産は、ご本人の生活費や医療費、介護費用などのために使われます。
3. 成年後見人が関わる相続で失敗しないための5つの注意点
成年後見制度を利用して相続手続きを進める際には、知っておかないと「こんなはずではなかった」と後悔しかねない注意点があります。
ここでは、特に重要な5つのポイントに絞って解説します。
3-1. 注意点①:後見人の選任には数ヶ月かかる【相続税申告に注意】
まず注意すべきは、成年後見人の選任には時間がかかる、という点です。
相続が発生してから家庭裁判所に成年後見の申立てをした場合、選任されるまでに3〜4ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。
家庭裁判所が、ご本人の判断能力の程度を医学的に鑑定したり、後見人の候補者が適格かどうかを調査したりするのに時間がかかるからです。
ここで問題になるのが、相続税の申告期限です。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から「10ヶ月以内」におこなわなくてはなりません。
もし後見人の選任が長引き、遺産分割協議がまとまらないまま10ヶ月を過ぎてしまうと、以下のようなデメリットが生じます。
- 税金の優遇措置が使えない: 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった、相続税を減額できる制度が利用できず、本来より多くの税金を納める必要がでます。
- 延滞税が発生する: 期限までに申告・納税しないと、ペナルティとして延滞税が課されます。
相続財産が多く、相続税の申告が必要になりそうな場合は、後見人の選任手続きと並行して、税理士などの専門家に相談し、期限に間に合わせるための対策を検討しましょう。
3-2. 注意点②:親族が後見人になれるとは限らない
「親の面倒は自分たち子供が見てきたのだから、後見人も当然、自分がなるべきだ」と考える方は多いです。
しかし、ご自身(子供など)を後見人の候補者として申し立てても、必ず選任されるとは限りません。
家庭裁判所は、ご本人の財産状況や親族間の関係などを総合的にみて、候補者が適任かどうかを判断します。
特に、管理する財産が高額であったり、親族間で意見の対立があったりするケースでは、中立・公平な立場の専門家(弁護士や司法書士など)が選任される傾向にあります。
専門家が後見人になることは、一見すると他人行儀に感じるかもしれません。しかし、相続というデリケートな問題において、公平な立場で交通整理をしてくれる専門家の存在は、かえって家族の絆を守るための心強い味方になってくれる場合があります。
3-3. 注意点③:後見人と本人の利益がぶつかる「利益相反」に注意
「利益相反」とは、一方の利益になることが、もう一方の不利益になってしまう関係をいいます。相続の場面では、この利益相反がしばしば問題になります。
例えば、以下のようなケースを考えてみてください。
- 登場人物:
- 被相続人:父(死亡)
- 相続人:母、長男、次男
- 状況:
- 母は認知症で、長男が成年後見人になっている。
この状況で、母、長男、次男の3人で父の遺産分割協議をおこなうとします。
長男は、相続人として「自分の取り分を多くしたい」と考えます。
一方で、母の後見人としては「母の取り分(法定相続分)をしっかり確保しなくてはならない」という義務があります。
このように、長男自身の利益と、後見人として守るべき母の利益が、真っ向から衝突してしまいます。これを利益相反行為といいます。
このような場合、長男は母の後見人として遺産分割協議に参加できません。
解決策として、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人とは、利益相反が生じる特定の法律行為についてのみ、ご本人を代理する人のことです。特別代理人には、利害関係のない他の親族や、弁護士・司法書士などの専門家が選任されます。
このケースでは、特別代理人が母の代理人として遺産分割協議に参加し、長男と次男と話し合いを進めます。
利益相反に気づかずに進めてしまった遺産分割協議は、後から無効になる可能性がありますので、注意しましょう。
3-4. 注意点④:一度選任されると本人が亡くなるまで原則終わらない
最後に、これが最も重要な注意点かもしれません。
成年後見制度は、一度開始すると、ご本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで、原則としてやめることはできません。
「相続手続きが終わったら、後見人をやめたい」ということはできないのです。
相続のために成年後見人を申し立てた場合でも、遺産分割協議が終わった後も後見は続きます。
つまり、ご本人が亡くなるまで、後見人の仕事は続き、専門家が後見人であれば報酬も発生し続ける、ということです。
また、後見人が選任されると、ご本人の財産は家庭裁判所の監督下に置かれます。
預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産の処分には、家庭裁判所の許可が必要になる場合があり、家族がこれまでのように自由に財産を動かすことはできなくなります。
成年後見制度は、ご本人の財産を守る強力な制度である一方、このような制約も伴います。
相続手続きのためだけに安易に申し立てるのではなく、制度のメリットとデメリットを十分に理解した上で、慎重に検討しましょう。
4. 相続で揉めないための生前対策|後見制度以外の選択肢
ここまで、成年後見制度を利用した相続手続きについて解説してきました。
しかし、最も理想的なのは、そもそも成年後見制度を利用しなくてもスムーズに相続がおこなえるように、ご本人が元気なうちに対策を講じておくことです。
ここでは、代表的な3つの生前対策を紹介します。
4-1. 対策①:遺言書を作成しておく
最もシンプルで効果的な対策が、遺言書の作成です。
なぜなら、法的に有効な遺言書があれば、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要がなくなるからです。
相続人の中に判断能力が不十分な方がいたとしても、遺言書に「誰に」「どの財産を」「どれだけ渡すか」が明確に書かれていれば、その内容にそって手続きを進めるだけです。
成年後見人を選任する必要はありません。
例えば、「長男には自宅の土地建物を、長女には預貯金のすべてを相続させる」といった内容の遺言書があれば、相続発生後、そのとおりに名義変更や解約手続きを進められます。
遺言書には自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」がありますが、内容の不備で無効になるリスクを避けるためには、専門家が関与する「公正証書遺言」をおすすめします。
家族間の無用な争いを避け、ご自身の最後の意思を確実に実現するための、最も確実な方法といえます。
4-2. 対策②:任意後見契約を結んでおく
任意後見契約とは、ご本人がまだ元気で判断能力がしっかりしているうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)を選び、支援してもらう内容を契約で決めておく制度です。
法定後見制度との大きな違いは以下の2点です。
- 後見人を自分で選べる: 信頼する子供や兄弟、あるいは特定の弁護士など、自分がこの人になら任せられる、という人を選べます。
- 支援内容を自分で決められる: 財産管理の方法や、介護施設への入所手続きなど、どのような支援をしてほしいかを契約内容に盛り込めます。
この契約は公証役場で「公正証書」として作成する必要があります。
そして、実際に本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、契約の効力が発生します。
法定後見制度のように、家庭裁判所が知らない専門家を後見人に選任する、という事態を避けられるため、ご自身の意思を将来にわたって反映させたい場合に有効な選択肢です。
4-3. 対策③:家族信託を活用する
家族信託は、近年注目されている財産管理・承継の方法です。
元気なうちに、ご自身の財産(例えば、不動産や預金)の管理・処分権限を、信頼する家族(例えば、長男)に託す契約を結びます。
- 委託者: 財産を託す人(親など)
- 受託者: 財産を託される人(子供など)
- 受益者: 財産から利益を受ける人(親など)
例えば、父(委託者兼受益者)が長男(受託者)と信託契約を結び、自宅と預金5,000万円を信託財産とします。
契約後は、財産の名義は長男に変わりますが、長男はその財産を父のために管理・運用します。父の生活費や介護費用は、信託された預金から支払います。
成年後見制度との大きな違いは、家庭裁判所の監督を受けない点です。
契約内容の範囲内であれば、受託者である長男の判断で、不動産を売却したり、アパート経営を始めたりといった、柔軟な財産活用ができます。
さらに、契約内容に「父が亡くなった後の財産の承継先」まで指定できます。
「父が亡くなったら、残った信託財産のうち自宅は長男が取得し、預金は次男に渡す」と決めておけば、遺言書と同じ機能も果たせます。
成年後見制度よりも自由度が高く、数世代にわたる資産承継も設計できるため、ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの対策が可能です。
5. まとめ
今回は、成年後見人が関わる相続手続きについて、具体的な流れから注意点、そして生前の対策まで網羅的に解説しました。最後に、この記事の要点をまとめます。
- 後見人が関わる相続には2つの立場がある
- 亡くなった方に後見人がいたのか、相続人に後見人がいるのかで、手続きが全く異なる。
- 手続きを始める前に、必ず5つの注意点を確認する
- 後見人の選任には時間がかかることや、費用、利益相反など、知らずに進めると後悔する可能性がある。
- 揉め事を避けるには、遺言書などの生前対策が最も有効
- 元気なうちに対策を講じることで、成年後見制度を使わずに円満な相続を実現できる。
成年後見や相続の問題は、法律の専門知識が必要なだけでなく、ご家族の感情も絡みあう、非常にデリケートな問題です。
だからこそ、手続きに少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家に相談してください。
専門家に相談することは、あなたと、あなたの大切なご家族の未来を守るための、最も確実で、一番の近道です。
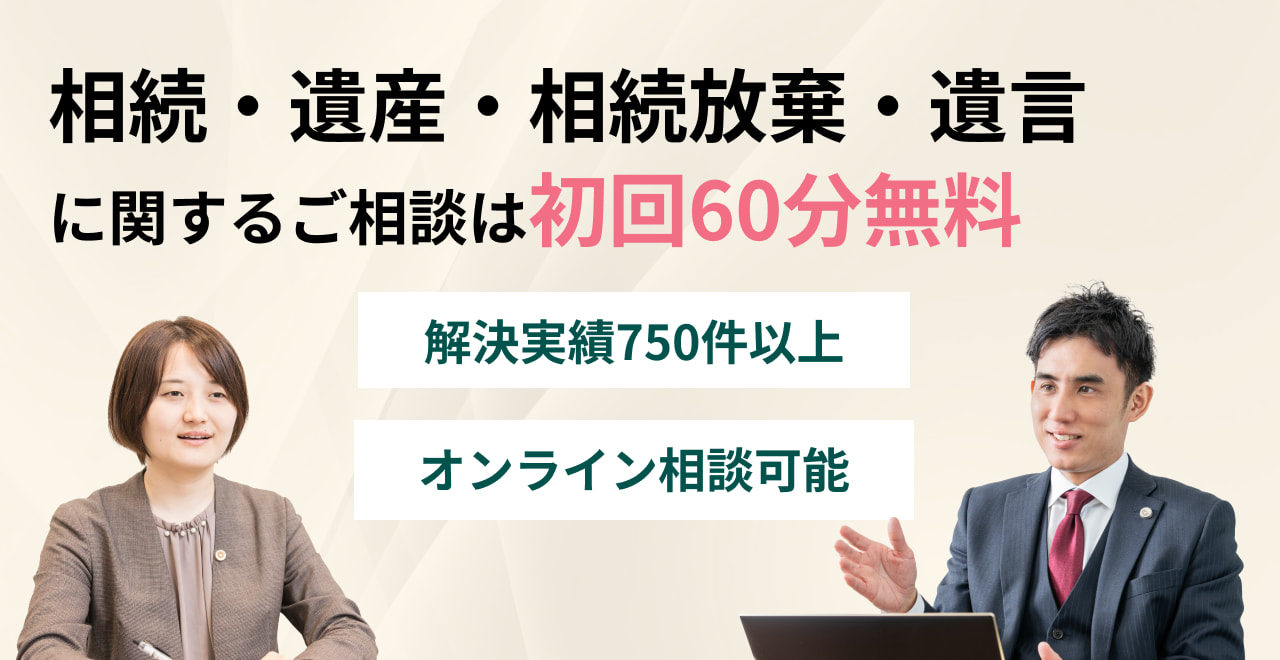
0120-100-129
お電話・相談フォームでのお問い合わせは24時間受付中!
平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。
関連するコラムはこちら
成年後見コラム(9)成年後見等の終了について
1. はじめに 今月号では成年後見等の終了についてご説明させていただきます。なお、今月号で成年後見コラムは最終回となります。 2. 成年後見等の終了事由について 成年後見が終了する事由は、大別すると、成年後見それ自体が終了する場合(これを「絶対的終了」といいます)と、成年後見自体は終了しないものの、当該後見人との関係では成年後見の法律関係が終了する場合(「相対的終了」といいます)とに分けられます。 ここで、絶対的終了事由としては、①本人の死亡、②後見等開始審判の取消しがあります。そして、絶対的終了の場合は、後見自体が終了するので、その後の手続きとして、管理財産の計算、終了登記、終了報告が必要となります。 一方、相対的終了としては、①後見人等の死亡、②選任審判の取消し、③辞任(民法844条)、④解任(民法846条)、⑤資格喪失(民法847条)があります。そして、相対的終了の場合は、まだ被後見人本人のために後見が継続するので、新たな後見人の選任が必要になり、新たな後見人が手続きを行うことになります。 なお、保佐や補助の終了についても、平成11年改正法により、成年後見の終了事由が準用されることになったので成年後見の場合と同様です(民法876条の2第2項、876条の5第2項・3項、876条の7第2項、876条の10第2項)。 3. 開始審判の取消しについて 絶対的終了事由の②後見等開始審判の取消しとは何かについてご説明すると、後見等開始審判の取消しとは、後見等開始の原因が消滅したとき、すなわち、本人の判断能力がそれぞれ成年後見、保佐、補助の制度による保護を要しない状態に回復した場合に、開始審判を取り消すことを指します。これは、成年後見等の制度による保護を要しない状態まで回復した場合には、わざわざ後見等を維持しておく必要がないためです。 4. 資格の喪失について 相対的終了事由の⑤資格喪失とはいかなる場合かについてご説明いたします。 後見人等は、被後見人等の身上に配慮し、財産を管理する義務を負うものです。そのため、後見人等は適正に職務を行うことが期待できる者である必要があります。そこで、このような適格がない者をあらかじめ除外しておくために、欠格事由が定められています。 欠格事由としては、(1)未成年者、(2)成年後見人等を解任された人、(3)破産者で復権していない人、(4)本人に対して訴訟をしたことがある人とその配偶者又は親子、(5)行方不明である人(民法847条、876の2条第2項、876条の7第2項)があります。 そして、後見人等になった後に欠格事由が生じた場合でも、当然にその人は後見人等の地位を失います。したがって、裁判所は後見人等を選任することになり、その結果新たな後見人等が引き継ぐことになります。
2017.11.25
new
成年後見コラム(8)成年後見人(保佐人、補助人)の 職務について
1. はじめに 今月号では成年後見人(保佐人、補助人)の職務についてご説明させていただきます。 2. 職務の始まり 成年後見人に選任された場合(保佐人、補助人に選任されてかつ財産管理に関する代理権のある場合)には、まず財産目録を作成して家庭裁判所に提出するとともに、年間の収支予定を立てなければなりません。 特に後見人は、この財産目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為しか出来ないことが法律で定められていますので、注意が必要です(民法第854条)。 3. 成年後見人、保佐人、補助人に共通すること 成年後見人等は、本人を法的に保護しなければなりません。具体的には、本人の利益に反して本人の財産を処分(売却や贈与等)してはいけません。したがって、成年後見人等、本人とその配偶者や子、孫、親族が経営する会社等に対する贈与や貸し付け等も原則としては認められない事になります。 本人の財産から支出できる主なものは、本人自身の生活費の他に、本人の債務の弁済金、成年後見人等がその職務を遂行するために必要な経費、本人が扶養義務を負っている配偶者や未成年の子等の生活費等です。それ以外のものについては、支出の必要性、相当性につきより一層慎重な判断が課されることになります。 また、成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには、家庭裁判所によって解任されることがあります。更に、これとは別に、不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりませんし、悪質な場合には、業務上横領罪(刑法第253条)等の刑事責任を問われることになります。 4. 成年後見人の主な職務について 成年後見人は、本人の財産の全般的な管理権とともに代理権を有します。すなわち、成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら(身上配慮義務)、財産を適正に管理し(財産管理義務)、必要な代理行為を行う必要があります。そして、それらの内容がわかるように記録しておくとともに、定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません(報告義務)。 具体的には、本人の財産が他人のものと混ざらないようにする、通帳や証書類を保管する、収支計画を立てる等の財産管理をするとともに、本人に代わって預金に関する取引、治療や介護に関する契約の締結等、必要な法律行為を行います。 5. 保佐人の主な職務について 保佐人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら(身上配慮義務)、本人に対し適切に同意を与えたり、本人に不利益な行為を取り消すことです。特定の行為について、代理権を行使する場合もあります。そして、これらの内容について定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません(報告義務)。 6. 補助人の主な職務について 補助人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら(身上配慮義務)、本人に対し適切に同意を与え、本人の行為の取消権又は代理権を行使することです。また、それらの内容について定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません(報告義務)。そして、代理権付与の申立てが認められれば、認められた範囲内で代理権を有し、これに対応した限度で本人の財産の管理権を有することになります(財産管理義務)。
2017.10.25
new
成年後見コラム(7)申立後の手続の流れについて
1. はじめに 今月号では申立後の手続の流れについてご説明させていただきます。 2. 面接 申立に特に問題がなければ、基本的に申立人及び後見人等候補者は、詳しい事情を裁判所に対して説明するために裁判所において面接を受けることになります。具体的には、申立人は申立時に提出した「申立事情説明書」に基づいて、申立に至る事情や本人の生活状況、判断能力及び財産状況、本人の親族らの意向等について聞かれます。 他方、成年後見人等候補者は、申立時に提出した「後見人等候補者事情説明書」に基づいて、欠格事由の有無やその適格性に関する事情について聞かれます。 なお、もし裁判所がより確認をする必要があると判断した場合には、後日改めて裁判所に行くことになるか、資料の追加提出をすることになります。 3. 本人調査 成年後見制度では、本人の意思を尊重するために、申立の内容等について本人から意見を直接聞くことがあります。これを本人調査といいます。 本人調査は、本人が直接家庭裁判所に行くか、本人が入院していたり体調が良くない等により家庭裁判所に行くことが難しい場合には家庭裁判所の担当者が入院先等に直接来て調査をされます。なお、補助開始の場合や、保佐開始で代理権を付ける場合には、本人の同意が必要になるため、本人調査の手続の中で同意確認も行われます。 4. 親族への意向照会 本人の親族に対して、書面等により、申立の概要や成年後見人等候補者に関する意向を照会されることがあります。 5. 鑑定 鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続です。申立時に提出する診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。ただし、親族からの情報や診断書の内容等を総合的に考慮して本人の判断能力を判断できる場合は、鑑定が省略されることもあります。 鑑定を行う場合は、通常、本人の病状や実情をよく把握している主治医に鑑定をお願いすることが多いです。もっとも、事案によっては、主治医に鑑定をお願いすることが出来ない場合や鑑定を引き受けてもらえない場合もあります。そのような場合には、主治医から他の医師を紹介してもらう等して、鑑定をお願いすることができる医師を探さなければなりません。 鑑定費用は、鑑定人の意向や鑑定のために要した労力等を踏まえて決められます。具体的には、主治医に鑑定を依頼する場合であれば、通常、診断書付票に記載されている金額になります。 なお、あらかじめ鑑定費用を納付しない限り鑑定は行われないので、裁判所の定めた納付期限内に納付をしてください。 6. 審理・審判 鑑定や調査が終了した後、家庭裁判所により、後見等の開始の審判が行われて、併せて最も適任と思われる人が成年後見人等に選任されます。複数の後見人等が選任されることもありますし、監督人が選任されることもあります。 また、保佐開始や補助開始の場合には、必要な同意(取消)権や代理権についても定められることになります。
2017.09.25
new
成年後見コラム(6)申立ての仕方について
1.はじめに 今月号では申立ての仕方についてご説明させていただきます。 2.申立てをする裁判所について 成年後見等の申立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所において行います。 例えば、鹿児島市に住民登録をしているAさんの成年後見申立てをしようとする場合には、鹿児島家庭裁判所において行うことになり、出水市に住民登録をしているBさんの成年後見申立てをしようとする場合には、鹿児島家庭裁判所川内支部において行うことになります。 3.申立てができる人について 成年後見等の申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。 ここで、「4親等内の親族」とはどこまでの範囲かあまりピンとこない方もいらっしゃるかと思いますので、説明させていただきますと、子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おば等となります。 4.申立てに必要な書類について 申立てに必要な書類については、裁判所のホームページをご覧になっていただければと思いますが、ここで簡単に説明させていただきますと、①申立書、②申立事情説明書、③親族関係図、④本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本(全部事項証明書)、預貯金通帳のコピー等)、⑤本人の収支状況報告書及びその資料、⑥後見人等候補者事情説明書、⑦親族の同意書、⑧本人及び後見人等候補者の戸籍謄本、⑨本人及び後見人等候補者の住民票(世帯全部、省略のないもの)、⑩本人の登記されていないことの証明書、⑪診断書、診断書付票、⑫愛の手帳の写しになります。 5.申立ての取下げについて 申立てをした後になって、申立ての取下げをしようとしても簡単に取下げが認められる訳ではないので、注意が必要です。 申立ての取下げをするには家庭裁判所の許可が必要になります。これは、公益性の見地からも本人保護の見地からも、後見等開始の審判をすべきであるにもかかわらず申立ての取下げにより事件が終了してしまうことが相当ではない場合があるからです。 例えば、Cさんが自身が後見人に選任されるつもりで申立てをしたはいいものの、自分が選任されないと判明した途端、それを不満として申立てを取下げる場合は、家庭裁判所から取下げの許可がされない可能性が高いと考えられます。 6.まとめ 以上のとおり、成年後見等の申立ては多くの書類の準備等が必要になりますので、お一人で申立てや手続きを進めていくことに不安を感じる場合には、ぜひ弊所にご相談してください。
2017.08.25
new
成年後見コラム(5)「任意後見」とは
1.はじめに 今月号では任意後見制度についてご説明させていただきます。 2.任意後見制度とは 任意後見制度とは、本人が契約締結に必要な判断能力を有している時点で、将来の判断能力低下後の保護のあり方と保護をする者(任意後見人)を、本人自らが事前の任意の契約によって決めておく制度のことをいいます(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。 すなわち、まず、本人の判断能力が低下する前に、本人と任意後見人にする予定の人とが任意後見契約を締結します。ここでいう「任意後見契約」とは、本人が、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況になったときに、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権を任意後見人に付与する委任契約です。 そして、本人の判断能力が不十分になった後、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時から「任意後見契約」の効力が生じることになります。 なお、任意後見契約は、公証人の作成する公正証書により締結しなければなりません(任意後見3条)。これは、公証人が関与することによって適法かつ有効な契約が締結されることを担保するためです。任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がなされます。そのため、本人や任意後見受任者等関係者が登記の手続きをする必要はありません。 3.援助者(任意後見人)の権限について 任意後見人は、同意権・取消権はなく、任意後見契約に基づく代理権のみが付与されます。 4.任意後見監督人の職務等 任意後見監督人は、その名前のとおり、①任意後見人の事務を監督します(任意後見7条1項1号)。 その上で、②任意後見監督人は、任意後見人に対し事務の報告を求め、または任意後見人の事務もしくは本人の財産の状況を調査して(任意後見7条2項)、家庭裁判所に対して定期的に報告しなければなりません(任意後見7条1項2号)。他にも、任意後見監督人には、③急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分をすること(任意後見7条1項3号)や、④任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること等の職務があります(任意後見7条1項4号)。 5.任意後見契約の解除について (1)任意後見監督人選任前の場合 本人または任意後見人受任者は、いつでも、公証人の認証(公証58条以下)を受けた書面により、任意後見契約を解除することができます(任意後見9条1項)。必ずしも公正証書による必要はないものの、当事者の真意による解除であることを担保する趣旨で、公証人の関与が必要とされています。 (2)任意後見監督人選任後の場合 本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます(任意後見9条2項)。このように家庭裁判所の関与を必要としたのは、本人の保護を図るためです。
2017.07.25
new
成年後見コラム(4)「補助」とは
1.はじめに 今月号では法定後見の3類型のうちの「補助」について詳細にご説明させていただきます。 2.保佐とは 補助とは、正確に申し上げるならば、①精神上の障害により②事理を弁識する能力が不十分である者を対象とする制度のことをいいます(民法第15条)。 先月号でご説明させていただいた保佐制度が、①精神上の障害により②事理を弁識する能力が著しく不十分である者を対象とする制度であることと比較すると、保佐制度よりも判断能力が認められる者を対象としていることがわかっていただけるかと思います。 補助の制度は、成年後見制度ができる以前は保護の対象とされていなかった軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある者を対象としたものであり、本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうが良いと思われる人を対象にしています。 3.援助者(補助人)の権限について 援助者(補助人)は、本人が望む一定の事項についてのみ(同意権や取消権は民法第13条1項記載の行為の一部に限る)、保佐人と同様に同意や取り消しや代理をして、本人を援助します。 ここで、注意していただきたいこととしては、二点あります。 まず、一点目は、補助開始の場合には、その申立てと一緒に、必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければならないことです。 次に、二点目は、補助開始の審判をすることにも、補助人に同意権又は代理権を与えることにも、本人の同意が必要ということです。 4.まとめ 今までご説明させていただいた法定後見の3類型(後見、保佐、補助)を開始する審判手続の違いや成年後見人、保佐人、補助人に与えられる権限の違いをまとめると、以下のとおりとなります。 対象となる人(本人) 後見 判断能力が全くない人 保佐 判断能力が著しく不十分な人 補助 判断能力が不十分な人 申立てができる人(申立人) 後見 保佐 補助 本人、配偶者、親や子や孫等直系の親族、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹等 申立てについての本人の同意 後見 不要 保佐 不要 補助 必要 医師による鑑定 後見 原則として必要 保佐 原則として必要 補助 原則として不要 成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 後見 日常の買い物等の生活に関する行為以外の行為 保佐 重要な財産関係の権利を得喪する行為等 *1 補助 申立ての範囲内で裁判所が定める行為 *2 *3 成年後見人等に与えられる代理権 後見 財産に関する全ての法律行為 保佐 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為 *3 補助 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為 *3 民法第13条1項記載の行為 民法第13条1項記載の行為の一部に限る 本人の同意が必要
2017.06.25
new
成年後見コラム(3)「保佐」とは
1.はじめに 今月号では法定後見の3類型のうちの「保佐」について詳細にご説明させていただきます。 2.保佐とは 保佐とは、正確に申し上げるならば、①精神上の障害により②事理を弁識する能力が著しく不十分である者を対象とする制度のことをいいます(民法第11条)。 3月号でご説明させていただいた後見制度が、①精神上の障害により②事理を弁識する能力を欠く③常況にある者を対象とする制度であることと比較すると、後見制度よりも判断能力が認められる者を対象としていることがわかっていただけるかと思います。 では、保佐制度で対象となる人はどの程度の判断能力を有しているのかというと、「日常の買い物くらいはできるが、民法13条1項に列挙されているような法律行為(例:訴訟行為をすること、借財又は保証をすること、贈与、和解又は仲裁合意をすること等)を単独ではできない」程度になります。 したがって、保佐の制度では、基本的に保佐を受ける人(被保佐人)は自ら法律行為を行いますが、本人保護の観点から、民法13条1項で列挙された法律行為については、援助者(保佐人)が保佐する、ということになります。 3.援助者(保佐人)の権限について 援助者(保佐人)には、民法13条1項に列挙されている法律行為について同意権(同意なき行為についての取消権・追認権)及び代理権が付与されています(民法13条、120条、876条の4)。 ここで、注意していただきたい点が、二点あります。 まず、一点目は、援助者(保佐人)は、民法13条1項に列挙されている法律行為以外の行為についても、保佐人の同意を必要とするものがある場合には、一定の要件を満たした者からの家庭裁判所への申立てにより、同意権の範囲を拡張することができるということです(民法13条2項、11条)。 次に、二点目は、援助者(保佐人)には代理権が当然には付与されていないということです。援助者(保佐人)が保佐を受ける人(被保佐人)に代わって代理で法律行為をしようと思った場合には、家庭裁判所において代理で行いたい法律行為について代理権を付与される手続きを行う必要があります。これは、保佐を受ける人(被保佐人)の意思を尊重して、なるべく自分でできることは自分でしてもらうという自己決定権尊重の観点と、代理権は本人に代わって法律行為ができるものであり、本人の利害に大きな影響力をもつため、権限濫用されて本人が不利益を被らないようにという本人保護の観点から、このような定めになっています。 4.まとめ 以上のように、保佐を受ける人(被保佐人)は、後見を受ける人(被後見人)よりも判断能力が認められることから、保佐を受ける人(被保佐人)自らが法律行為を行う場面が多くなります。 そのため、保佐人になる人は、後見の場合以上に保佐を受ける人(被保佐人)との意思疎通を十分に行い、保佐を受ける人(被保佐人)の状況の変化に対応し、適宜保佐の範囲を拡張しつつ、保佐を受ける人(被保佐人)の意思を尊重しながら保佐事務を行う配慮が求められることになります。
2017.05.25
new
成年後見コラム(2)「後見」とは
1.はじめに 先月号のコラムにて、法定後見はさらに判断能力の不十分の程度によって、後見、保佐及び補助の3類型に分類されるとご説明させていただきましたが、今月号ではこの3類型のうちの「後見」について詳細にご説明させていただきます。 2.後見とは 後見とは、正確に申し上げるならば、①精神上の障害により②事理を弁識する能力を欠く③常況にある者を対象とする制度のことをいいます(民法第7条)。 堅苦しい言葉の羅列で、わかりにくいと思いますので、一つ一つの言葉を簡単に説明させていただきますと、まず①「精神上の障害」とは、身体上の障害を除いた全ての精神的障害を意味します。具体的には、認知症、知的障害、精神障害、疾病・事故等による脳機能障害を原因とする精神的障害等を指します。次に、②「事理を弁識する能力」とは、法律行為(例えば物の売買や、住居の賃貸借等)をするに際して、自分にとって利益になるか不利益になるかを判断する能力をいいます。さらに、③「常況」とは、一時的に事理を弁識する能力を回復することはあっても、大部分の時間はその能力を欠いている状態が継続していることをいいます。 すなわち、後見制度は、精神障害により、法律行為をする際に自分にとって有利か不利かを判断する能力がほぼ常に欠けている人を対象とする制度、ということになります。 3.後見制度を使うためには ご家族の方で、精神障害により、法律行為をする際に自分にとって有利か不利かを判断する能力がほぼ常に欠けていると思われる人がいて後見制度を使いたい場合には、そのご家族につき後見開始の審判の申立てを裁判所に行うことになります。そして、裁判所が、後見にあたると判断して初めてそのご家族は「成年被後見人」、すなわち後見制度の対象者になることができることになります。 ここで、後見にあたるかどうかの判断はどのようにされるのか疑問に思われたかと思いますが、後見にあたるかどうかは、明らかな場合を除き、基本的には鑑定、すなわち裁判所の命令によって鑑定人という専門家が医学的に判定する手続によって判断されることになります(家事事件手続法第119条1項)。 4.援助者(成年後見人)について ご家族の方が後見制度の対象者である「成年被後見人」にあたることになった場合には、裁判所がその成年被後見人のために「成年後見人」、すなわち成年被後見人の援助者を選任します(民法第8条、第843条)。 この選任は、成年被後見人の心身の状態並びに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他諸々の事情を考慮してなされますが、現在では、法人を選任することも複数人を選任することも可能になりました(民法第843条4項)。 5.援助者(成年後見人)の権限について 成年後見人は、包括的な代理権及びこれに対応する財産管理権と、日常生活に必要な範囲の行為以外の法律行為に関する取消権が付与されています(民法第120条1項)。 すなわち、成年後見人には、遺言や婚姻等の一身専属的な行為(本人が行わなければ意味がないもの)以外の本人の財産に関する法律行為について成年被後見人に代わって行う権利と、成年被後見人の日常生活に必要な範囲以外の行為を後から取り消す権利が認められており、非常に重要な権限を付与されることになります。
2017.03.25
new
成年後見コラム(1)成年後見制度の概要
1.はじめに 今月号より、最近話題になっている成年後見の分野について、連載で執筆させていただきます。成年後見は誰にとっても自分の問題になり得るものですので、少しでも皆様に関心を持っていただいて、また理解の一助となることができればと考えております。 今回は初回ですので、成年後見がどういった制度なのか、制度の変遷と制度の大枠についてご説明させていただきます。 2.成年後見制度の変遷 今までの民法では、成年後見制度に該当するものとして、「禁治産・準禁治産制度」がありました。この禁治産・準禁治産制度は、判断能力が不十分な人の個々の状況に合わせることが難しいばかりか、戸籍に記載されること、手続きに時間や費用がかかる等の問題点が指摘され、近年はあまり利用されることはありませんでした。 しかし、高齢化社会になっていく中で、判断能力が不十分になった高齢者の財産を悪徳商法や他の犯罪行為から守ることや、介護保険制度をはじめとする福祉サービスが措置から契約に基づく利用へと移行し、契約に必要な判断能力に欠ける人への支援が必要になったこと、障害者福祉の充実といった観点等から、実情に即した利用しやすい制度が必要になりました。そこで、2000(平成12)年4月から現在の成年後見制度が施行されることになりました。 3.成年後見制度とは そもそも、成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な成年者を保護するための制度です。そして、現在の成年後見制度は、これまでの「禁治産・準禁治産制度」と比較して、後述するように補助類型や任意後見制度が新設されたことにより、より判断能力の不十分な人の個々の状況に合わせることができるようになり、また戸籍への記載が廃止され、登記制度が導入されたことが大きな特色です。 ここで、成年後見制度は、大きく分けて法定後見と任意後見に分類されます。 まず、法定後見は、申立権者が家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てをして、家庭裁判所が適任者を選任する形で行われます。そして、法定後見はさらに判断能力の不十分の程度によって、後見、保佐及び補助の3類型に分類されます(詳しくは次回ご説明させていただきます)。 一方の任意後見は、本人と任意後見受任者との間であらかじめ決めた任意後見契約の内容に従って、任意後見契約発効後に任意後見人が本人の財産管理を行う制度です。 4.任意後見と法定後見の関係 任意後見と法定後見はどのような関係にあるのか疑問に思われたかと思いますが、基本的には、任意後見契約が登記されている場合には、本人の意思を尊重するということで、任意後見が法定後見に優先します。ただし、例外的に、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めた場合には、法定後見開始が任意後見に優先することになります。 要は、よっぽどのことがない限りは、本人の意思を尊重しようということで、任意後見制度が優先されると理解していただければと存じます。
2017.02.25
new