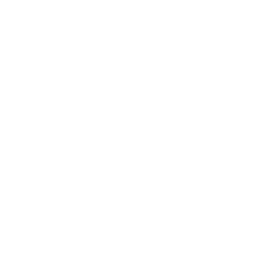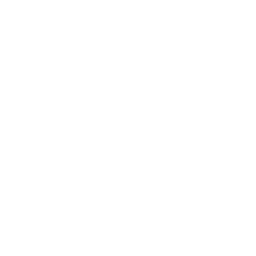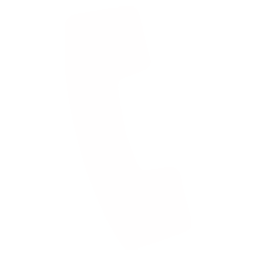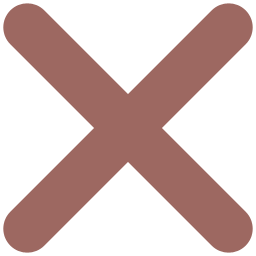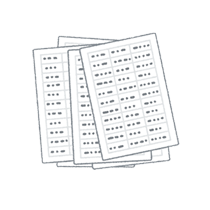遺留分って具体的にいくらですか ~遺留分算定の考え方~
更新日:2022/10/06
遺留分って具体的にいくらですか ~遺留分算定の考え方~

遺留分の割合
遺留分の具体的な金額を算定するに当たっては、まず各人に認められる遺留分の割合を求める必要があります。
遺留分の割合は、まず①総体的遺留分(遺留分率)を確認し、次にこの総体的遺留分を基に②個別的遺留分(具体的遺留分)を確認することとなります。
①の「総体的遺留分」(遺留分率)とは、遺産全体における遺留分の割合のことです。民法では、総体的遺留分を2つの場合に分けて定めています。(ⅰ)直系尊属のみが相続人の場合と、(ⅱ)それ以外の場合(つまり、配偶者や子がいる場合)です。前者の場合、総体的遺留分は遺産全体に対する3分の1(残り3分の2は自由分)であり、後者の場合の総体的遺留分は2分の1(残り2分の1は自由分)とされています。
たとえば、被相続人が亡くなった時点で被相続人に配偶者や子はいないものの実母が生存していた場合、直系尊属のみが相続人のケースに当たりますので、総体的遺留分は遺産全体に対する3分の1の割合となります。一方、相続開始時点で被相続人に子はいないものの妻と実母が存命だった場合、直系尊属のみが相続人となるケースではありませんので、総体的遺留分は遺産全体に対する2分の1の割合となります。
こうして算出した総体的遺留分をもとに、次は②個別的遺留分(具体的遺留分)を確認します。個別的遺留分とは、遺留分権利者 個々人に認められる遺留分の割合のことです。総体的遺留分は、遺産全体に対して遺留分が何割かという問題であり、個別的遺留分は、その総体的遺留分に対して遺留分権利者各人が何割ずつ遺留分を得られるかという問題です。
遺留分権利者が1人しかいない場合は、総体的遺留分の割合がそのまま個別的遺留分になります。たとえば、被相続人の相続人が実母のみの場合、すなわち遺留分権利者も実母のみとなります。この場合、先ほどの説明のとおり総体的遺留分は遺産全体に対する3分の1の割合ですが、この3分の1の権利は実母の他に分け合う遺留分権利者がいないため、そのまま3分の1が実母の個別的遺留分となります。同様に、相続人が妻だけの場合、総体的遺留分である2分の1がそのまま妻の個別的遺留分となります。
一方、遺留分権利者が複数いる場合、各人の個別的遺留分は、総体的遺留分に各人の法定相続分を乗じた割合となります。例えば、被相続人の相続人の地位に実父母が立つ場合、総体的遺留分は遺産全体に対して3分の1の割合となりますが、遺留分権利者は実父・実母の2名がいるため、この3分の1に実父・実母の法定相続分(この場合は双方2分の1ずつ)を乗じた値として各人6分の1ずつの個別的遺留分を取得することとなります。相続人が配偶者と実母の場合、総体的遺留分は遺産全体に対して2分の1となります。この場合、妻・実母の各人の個別的遺留分は、総体的遺留分に各人の法定相続分の割合(妻:3分の2、実母:3分の1)を乗じた割合となります。具体的に計算すると、妻の個別的遺留分は、2分の1に3分の2を乗じた「3分の1」となり、実母の個別的遺留分は、2分の1に3分の1を乗じた「6分の1」となります。
遺留分権利者である子が死亡した場合、代襲相続が起こりますので、その子(被相続人から見た孫)が子の個別的遺留分も承継します。なお、被相続人の兄弟姉妹に関しては、相続資格の問題と遺留分の問題について概念的にやや紛らわしいところがあります。被相続人の相続人の地位に兄弟姉妹が立つ場合(相続開始時に被相続人の子や直系尊属が存命していない場合)、その兄弟姉妹が死亡していれば、その子が相続人の地位を代襲相続します。一方で、遺留分に関しては、そもそも兄弟姉妹にはこれが認められていないため、代襲相続という問題は起こらないのです。
また、遺留分の割合を、遺言によって被相続人が指定することは法律で禁じられています。これは、相続分と異なる点です。相続分の割合は、被相続人が遺言によって自由に指定することができますが、遺留分ではこのような指定が認められません。被相続人の意思によって自由に処分できるのは、被相続人の遺産全体のうち「自由分」に限られ、「遺留分」は誰も害することのできない権利(割合)だからです。なお、民法の規定と異なる遺留分の割合を定めた遺言は、当該部分に限って無効となります。
遺留分の割合を算定する際に、寄与分は関係がありません。寄与分というのは、遺産分割に関するものであり、遺留分の問題とは別だからです。遺産分割は家庭裁判所の審判事項であり、寄与分も家庭裁判所の審判によって初めて認められる権利です。他方、遺留分は、訴訟事項であり、別制度、別手続に従う概念です。ですので、相続人のうちの1人が遺産の増殖にどれほど寄与しても、あるいは、自身の経済的利益を投げうって献身的に被相続人の生活を介護していたとしても、そのことによって遺留分の割合が増えることはないのです。
遺留分算定における基礎財産に算入される要素
個別的遺留分を乗じることで各自の遺留分を算定する際の基礎となる被相続人由来の財産を「基礎財産」と呼びます(割とそのままの名称ですね。)。
この「基礎財産」は、被相続人が亡くなった時点で被相続人名義のまま存在している財産とイコールの関係にありません。そのような考え方を取ると、例えば、妻子を捨てて愛人に走った夫が始期を悟った時点でその愛人にすべての財産を生前贈与してしまった場合、遺留分の対象財産がなくなり、遺留分制度が有名無実となってしまうからです。
では、どう異なるのでしょうか。「基礎財産」は、被相続人の死亡時(相続開始時)に被相続人名義で存在している財産そのものを利用せず、そこに一定の調整を加え、相続人間だけでなく他の第三者(受遺者・受贈者)までを含めた相続の公平性を図るように設計されています。結論から言えば、遺留分算定の「基礎財産」は、以下の公式に従って導きます。
基礎財産 =①被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺贈財産を含む)
+ ②贈与財産 – ③相続債務全額
この「基礎財産」の算定式が、遺産分割における「みなし相続財産」及び「具体的相続分」の算定と異なる点は以下のとおりです。
【1】寄与分が考慮されない ※上述のとおりです。
【2】組み込まれる贈与財産の対象が広い(②)
【3】受贈者(贈与を受ける者)が、共同相続人に限られない(②)
【4】相続債務が控除される(③)
上の公式の要素をひとつずつ見て行きます。まず、「①被相続人が相続開始時点で有していた財産」とは、相続人が承継した積極財産(財産的価値のある財産。対立概念である「消極財産」は被相続人が負っていた債務を意味します。)のことです。お墓や遺骨、位牌などは「祭祀承継財産」と呼ばれ、そもそも相続の対象とされず、遺留分算定の場面でも関係しません。別の民法の規定によって承継者が決められます。この①には、現金や預金といった分かりやすい財産だけでなく観念的な権利も含まれます。その際、条件が付された権利や存続期間が不確定な権利は、相続開始時点において実際どれだけの価値が認められるべきものなのか一義的に明らかではありません。このような価値の判断が難しい権利について民法は、家庭裁判所が選定した鑑定人に評価させることでその結果を遺留分算定の基礎財産の算定に用いると定めています。また、①の積極財産には遺贈の対象となる財産も含めます。「遺贈」とは、遺言によって行う贈与のことで、遺贈を行う者(遺言者)を遺贈者、遺言を受ける者を「受遺者」と呼びます。遺贈は、相続開始時点の被相続人の財産から受遺者に権利が移転するものです。死亡時財産から離脱する財産を指すため、この離脱を考慮しないという扱いだけで足りるのです。なお、死因贈与も、遺留分に関する「基礎財産」の算定過程では遺贈と同様に扱われます。「死因贈与」とは、生前に被相続人が第三者(推定相続人以外の者を含む)との間で自身の死亡時に効力が生じることを内容として結んだ贈与契約のことです。遺贈と非常に似た概念ですが、「遺言によらない」という様式性の点や、「契約」であるという点で異なる法律行為とされます(遺贈は契約ではなく「単独行為」です。)。もっとも、民法では、死因贈与契約については遺贈に関する規定を準用するという条文があるため(民法554条)、遺留分の分野でも遺贈と同様の扱いがされるのです。
次に、②について説明します。被相続人が生前に行っている「贈与」行為は、一定の条件に該当する限り、遺産に組み入れられた上で、遺留分算定の「基礎財産」とされます。ここでいう「贈与」という言葉を説明しますと、まず、「死因贈与」が含まれない点は、先ほどの遺贈の説明で述べたとおりです(死因贈与は②ではなく遺贈に準じて①の問題として処理されます。)。②の「贈与」は、被相続人の生前に契約され、相続開始時までに現実に履行されているもの、つまり、相続開始時に既に財産が遺産から離脱済みのもののみを指します。そして、ここでの「贈与」は、いわゆる「贈与契約」に限られず、一切の無償処分を含みます。例えば、無償での債務免除や無償での担保供与(他人の借入を担保するために被相続人所有の不動産に抵当権を設定する場合等)、信託の供与や一般財団法人への財産の拠出に至るまで、そこに無償性が認められる限り、全てが②の「贈与」に当たります。
②の贈与の対象は、遺産分割における「みなし相続財産」の場合と異なり、相続人への贈与に限りません。相続人以外の第三者に対する贈与もこれに当たります。例えば、被相続人が愛人に生前贈与を行っていた場合、当該贈与財産は遺産分割の局面で「みなし相続財産」への持ち戻しの対象となりませんが、遺留分算定の際の「基礎財産」には組み入れられます。
②の贈与では、各種の要件によって「基礎財産」に組み入れられるか否かが異なるのですが、受贈者が相続人である場合とそうでない場合(愛人や宗教法人、相続人でない親族等)とで効果が大きく異なります。まず後者の場合、つまり、相続人以外の者が受贈者となる場合、相続開始前「1年」以内に為された贈与に限って「基礎財産」に組み入れられるのが原則です。このように期間が1年間に区切られているのは取引の安全(とりわけ受贈者の法的安定性の保護)に法が配慮したためです。この「1年間」というのは、贈与契約などの法律行為(契約)が1年以内に行われていることが必要です。例えば、相続開始の1年1月前に贈与契約が結ばれ、贈与契約上の債務の履行(たとえば、不動産の移転登記や預金の振込など)が1年以内にされたというケースでは、「基礎財産」に算入されないこととなります。また、1年という期間には例外があり、被相続人と受贈者(贈与を受ける者)の双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与」(悪意の贈与)は、期間の制限なくどこまでも遡って基礎財産に組み入れることができます。この「損害を加えることを知って」とは、遺留分権利者に損害を与えることを客観的に認識していれば足り、ことさらに遺留分権利者に損害を与えてやりたいといった加害の意思は不要とされています。また、法律の知識がないことや誰が遺留分権利者となるか認識していなかったという点も関係がありません。では、贈与契約締結された時点で、贈与財産の価額が贈与者の総財産の過半を占めていた場合に、この贈与が「遺留分権利者に損害を加えることを知ってした」贈与と言えるでしょうか。判例によれば、「損害を加えることを知ってした」と言えるためには、贈与当時に贈与財産の価額が残存財産の価額を超えることを知っていただけでは足りず、将来において相続開始までの間におよそ自己の財産が増加しないことを被相続人が認識し、そのことを受贈者も知っていたことが必要とされています(予見必要説)。この判例に従えば、贈与時点で当該財産が被相続人の財産の大半を占めているだけでは「遺留分権利者に損害を加えることを知ってした」とまでは認められず、将来に渡って被相続人の財産が増える見通しがなかったことまで必要になるということです。
一方で、受贈者が相続人の場合、「基礎財産」に組み入れられる贈与は、相続開始より「10年」以内のもので、且つ、「特別受益」と評価される場合となります。「特別受益」とは、「婚姻」もしくは「養子縁組」あるいは「生計の資本」として行われた贈与のことをいいます。結婚や養子縁組のお祝いとして親が子に家を建ててあげるといった事例は「婚姻」もしくは「養子縁組」のための贈与に当たります。一方、「生計の資本」としての贈与とは、広く生計の基礎として有用な財産上の給付(財産的な利益を与えること)をいうとされますが、夫婦間の扶養義務や、親子の扶養義務の範囲に含まれるものは当たりません。よく問題になるのは、大学の学費や入学金を親が支払った場合にこれが「生計の資本」としての贈与として特別受益に当たるかという点ですが、現在の大学進学率に照らすと、これは親の子に対する扶養義務の範囲に納まるものとして、特別受益に該当しないと判断される例が多いです。もっとも、長男を医者にさせるため家財の全てを投げうって私立大学の医学部に進学させ他の兄妹たちは本人の希望に反して高校卒業と同時に家業を手伝わされた(あるいは就職させられた)といった事例では、それはもはや扶養義務の範囲を超えた兄弟間の公平に反する贈与(「生計の資本」としての贈与)に当たり、特別受益に該当するでしょう。このような特別受益が存在する場合、相続開始から10年間まで遡って遺留分算定の「基礎財産」に組み入れることが可能となります。
なお、この「10年間」という期間制限は、2018年(平成30年)の民法改正によって初めて定められたものであり、それ以前は、特別受益に関しては、無制限に遡って遺留分算定の基礎財産に含めることができました。したがって、改正相続法のうち遺留分制度に関する新法の施行日である2019年(令和元年)7月1日より以前に相続が開始された事件では、旧法が適用されるため、特別受益については「10年」という期間制限にかからず、無制限に遡って「基礎財産」に組み入れることができます。
また、改正民法においても、遺産分割の「みなし相続財産」の計算に際しては、特別受益は無制限に遡って持ち戻すことが可能とされ、期間制限のある遺留分算定の局面とは扱いを異にします。遺産分割における「みなし相続財産」と遺留分算定における「基礎財産」とは概念的に異なるものですが、同じ「相続」の問題として混同されがちです。よく分からないようであれば、当事務所の法律相談をご利用いただければ詳細なご説明を差し上げます。
なお、「特別受益」といえるには、受贈者(贈与を受ける者)が相続人であることが必要です。従って、例えば、被相続人の生前に、同人から特別受益に該当する多額の贈与を受け取っていた子が相続開始後に相続放棄をした場合、その子は最初から相続人ではなかったことと扱われるため、もはや特別受益による「基礎財産」への組み入れはできません。この場合には、被相続人と受贈者(贈与を受ける者)の双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与」であったか否かという基準のみで「基礎財産」への組み入れの是非が判断されることとなります。
その他、②の贈与に関しては、生命保険金の処理が問題となります。これは、第三者(被相続人以外の者という意味)を受取人した生命保険金請求権(あるいは受取り済みの生命保険金そのもの)が、贈与類似の無償処分行為に基づく財産として「基礎財産」への組み入れを行う必要があるのではないのかという問題です。この点、最高裁の判例によれば、原則として、第三者を生命保険金受取人に指定する行為は「贈与」やそれに準ずるものとは言えず、遺留分の算定でも「基礎財産」には組み入れられません。もっとも、保険金受取人として指定された者が共同相続人の一人であった場合、保険金受取人である相続人と他の相続人との不公平が到底是認できないほど著しいものと評価できる特段の事情があれば、これを「特別受益」と評価して「基礎財産」に組み入れる余地は残ります。生前の財産全てを生命保険の保険料に費やし、相続開始時にほとんど何も財産が残っていない一方で共同相続人のうちの1人だけが莫大な保険金を受け取るといった極端な事例では、相続人間の公平の観点から、当該保険金を「基礎財産」に組み入れることが肯定されるでしょう。
その他、死亡退職金の取扱いについて質問を受けることがあります。死亡退職金制度は、遺留分と同様に遺族の生活保障を目的としたものでありますが、遺留分制度を前提とした上でさらに死亡退職金の受給権者への交付が認められている以上、死亡退職金を遺留分によって割り引くことは合理的でありません。法の明文や判例はありませんが、学説上も、死亡退職金は、遺留分算定の「基礎財産」に含めるべきでないという見解が有力とされています。
「負担付き贈与」や「不相当な対価でされた有償行為」についても触れます。「負担付き贈与」というのは、一定の負担を条件としてなされる贈与のことです。この場合は、贈与の価値から負担部分の価値を割り引いた残余部分を実際の無償贈与部分と見て、この部分に限って「基礎財産」への組み入れが認められます。「不相当な対価でされた有償行為」も同様です。1000万円相当の車を100万円で誰かに譲っていた場合、差額の900万円部分が無償贈与に当たると判断され、この部分に限り遺留分算定の「基礎財産」に組み入れることとなります。
「基礎財産」の算定式の最後の要素である③の相続債務の控除について説明します。まず、遺産分割での「みなし相続財産」では債務は控除しませんが、遺留分算定の「基礎財産」では債務が控除されます。これは、遺留分という制度自体が、現実に相続人が取得する財産を基礎として遺留分権利者に一定の保護を与えることを目的としているため、保護される範囲を確定するためには債務を控除したプラスの財産(積極財産)のみを対象とする必要があるからです。
この「債務」には借金のような私法上の債務だけではなく、税金の滞納や刑事罰としての罰金等も含まれます。一方で、保証債務、つまり被相続人が保証人となっている債務については、原則として含まれません。保証債務が基礎財産から控除されるべき例外は、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人(被相続人)がその債務を履行しなければならず、且つ、その支出額を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存在するといった、かなり限定的な場面に限られます。
遺留分算定における基礎財産の評価基準時と評価方法
遺留分算定の「基礎財産」の算定基準時は、相続開始時点です。ですので、「基礎財産」に組み入れられる財産もすべて相続開始時点の価値で評価されます。
たとえば、相続開始の3年前に被相続人が推定相続人の一人に当時5000万円の価値の不動産を贈与し、その後、不動産の時価が急騰し、相続開始時点ではその不動産が6000万円の価値になっていたという場合、特別受益として「基礎財産」に組み入れられるべき当該贈与額は贈与時点での5000万円ではなく、相続開始時点での6000万円となります。このような不動産だけでなく、贈与された時点と相続された時点で貨幣価値が異なる際も相続開始時点での貨幣価値で評価されます(この問題は、特に為替などで大きく影響を与えます。)。
逆に相続開始後に生じた価値の増減も考慮されません。あくまでも相続開始時点の「原状」(元の状態)で評価されます。たとえば、遺産を構成する建物を相続開始後に修理し、その不動産価値が高まったり、逆に何の手入れもせずに朽ちて不動産価値が減少したりしても、遺留分算定の「基礎財産」の算定においては、あくまでも相続開始時点での原状での価格で評価されます。
話は変わりますが、遺産の中に「債権」が含まれている場合があります。「債権」とは、他人に対して何かを請求できる権利一切のことを指しますが、実際の取引社会では金銭の支払いを求める権利を指すことが多いです。たとえば、貸金がある場合に、貸していた人が借りていた人に対してそのお金を返してくれと求める権利が典型です。もっとも、この債権というものは、たとえ額面上が1億円の権利であっても、借りた相手が無一文であれば、実際にはほとんど価値がありません。債権の価値は、額面上の金額だけでなく債務者側の資力によって価値が大きくことなるのです。そのため、遺留分の「基礎財産」の算定に当たって債権を評価する際も、債権の名目額によらず、債務者の資力や担保の有無を考慮した取引価額(その債権を他者に譲渡する場合に付くであろう売却価額)で算定するのが判例の考え方です。
最後に、③の債務が膨大で、これを控除した場合、「基礎財産」がマイナスとなるケースはどうなるのでしょうか。この場合の取扱いについては、実は法律上の明文や確立した裁判例はありません。学説では、大きく2つの見解に分かれておりますが、どちらが適切かは未だ決着がついていません。
2つの学説を説明するために、①の積極財産2000万円、②の贈与財産1000万円、③の債務3500万円という事例を想定します。この場合、①+②-③=-500万円となります。
一つ目の学説は、このようなケースでは「基礎財産」はゼロであり、遺留分は認められないとします。結果的に被相続人が自由に処分できる自由分は3000万円、遺留分は0となり、自由分の拡大に寄与する見解となります(被相続人の意思や受遺者・受益者の利益を尊重する考え方といえます。)。もう一つの学説は、このような債務超過のケースでは、「被相続人は自由分を有しない」という発想から出発し、先の事例では、自由分を持たない以上、本来的に被相続人は他者に生前贈与することは許されなかったにもかかわらずこれを行ったことになり、その限度で遺留分が侵害されたと考えます。つまり、②の1000万円が遺留分侵害部分と扱われます。これは、被相続人の意思や受遺者・受贈者の利益よりも遺留分権利者の利益を重視する見解と言えます。
ここでは、債務超過事例の遺留分の考え方を巡る2つの学説について簡単な説明を行いましたが、実際にこのようなケースに当たった場合にどのような判断がなされるかは、事件を担当した裁判官個々人の考え方次第となります。法律の世界では、最高裁判例や通説的見解が存在しない論点が多く存在し、そのような問題ではしばしばこうした現象が生じてしまうのです。
以上、遺留分の算定方法を取り上げて参りました。少々混み入った話もあり、理解するのもなかなか難しかったのではないかと思います。重要な問題であり、遺留分には短期の消滅時効も存在するため、分からない点があれば、迷わず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。次は、遺留分が侵害された際のアクションについて説明を行います。
遺留分についてご相談をされたい方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスにご連絡下さい。初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。まずはお電話でお問合せください。
0120-100-129
(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)