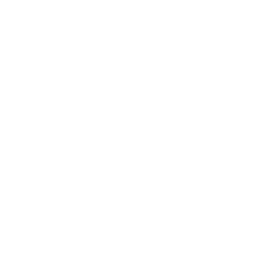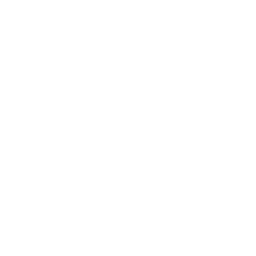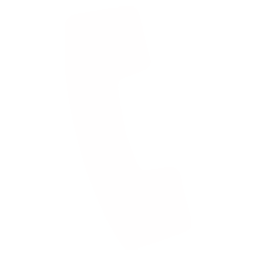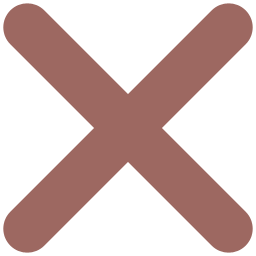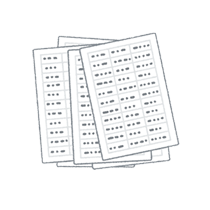遺留分侵害額請求って何ですか ~遺留分侵害額請求権の法的性質と請求金額の算定~
更新日:2022/10/06
遺留分侵害額請求って何ですか ~遺留分侵害額請求権の法的性質と請求金額の算定~
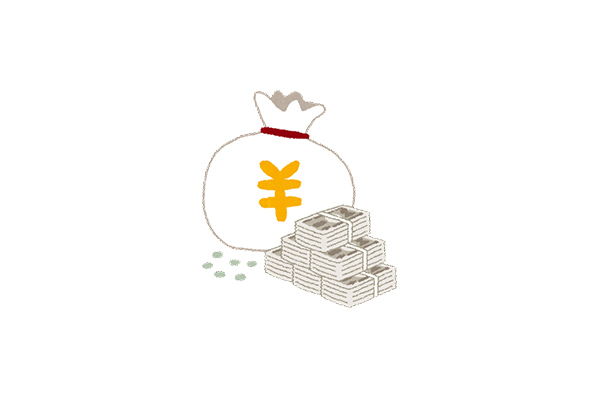
遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い
ここでは、遺留分が侵害された際の法的効果を説明します。簡単に言うと、個別的遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は侵害者に対して該当部分の利益を回復することを求めることができるのですが、その詳細は少々込み入っています。
ここで説明する内容は、少し難しく、お客様向けというよりは、法律家の方や法律を学ぼうとされている方向けのものが含まれます。
まず、遺留分権利者の個別的遺留分が生前贈与・死因贈与・遺贈等の各種手段によって侵害された場合、遺留分権利者は侵害者(受贈者・受遺者等)に対し、自身が持っている遺留分に基づき、「遺留分侵害額請求権」という権利を取得します。この遺留分侵害額請求権というのは、当該遺留分侵害行為を有効とした上で侵害額に相当する金銭の支払いを求めることのできる権利(金銭債権)とされています。重要なのは、この「侵害行為を有効とした上で」という点です。つまり、遺留分を侵害するような贈与や遺贈も法的には有効です。したがって、被相続人が保有する不動産を愛人に生前贈与して所有権移転登記がされた場合、遺留分権利者は、その愛人(受遺者)に対して、「その生前贈与は無効なので所有権の登記を抹消しなさい」とは言えません。あくまで贈与は有効であり、当該愛人を所有者と認めた上で、その愛人に対して遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができるだけなのです。これが、「遺留分侵害額請求権」という、現在の民法が定める遺留分権利者が、遺留分の侵害を受けた際に行使できる権利の性質とされています。
なお、この「遺留分侵害額請求権」は、2018年(平成30年)の相続法改正によって認められたものであり、新法の施行日である2019年(令和元年7月1日)以後に開始された相続にのみ適用される概念(効果)です。それ以前に開始されている相続に関しては、遺留分についても依然として旧法が適用されます。では、旧法では、遺留分が侵害された場合の法的効果としてどのようなものが認められていたのでしょうか。旧法では、現在の「遺留分侵害額請求権」とは効果を異にする「遺留分減殺請求権」というものを認めていました。「遺留分減殺請求権」とは、遺留分を侵害する贈与や遺贈の効力を、遺留分の侵害範囲において失効させるという強力な権利でした。遺留分減殺請求権の行使によって失効させられた贈与・遺贈のうち失効した部分(遺留分減殺請求権者の個別的遺留分に該当する部分)の権利は当然に遺留分減殺請求権者に帰属し、受贈者・受遺者と遺留分減殺請求権者との間で共有関係に立ち、贈与・遺贈すべてが遺留分減殺請求権者の個別的遺留分を侵害する場合は、贈与・遺贈の対象物のすべての権利を遺留分減殺請求権者が取得し、物の現物返還を求めることができました。これに対し、受贈者・受遺者には現物返還の代わりに金銭で賠償することを求めることが認められていましたが(価格弁償の抗弁)、第三者と通謀して贈与・遺贈の対象物の所有権を当該第三者に移したような場合(悪意)には、遺留分減殺請求権者は、なお当該第三者に対して目的物の返還を求めることが許されていました。
このように、旧法の「遺留分減殺請求権」は、現在の「遺留分侵害額請求権」と異なり、贈与や遺贈の目的となった物や権利そのものを支配する効果が認められていたため、しばしば取引の安定を害し、また、共有関係を多く生み出すことでさらなる紛争を発生させる原因となっておりました。このような複雑な法律関係や連鎖的な紛争の勃発を回避するため、2018年の相続法改正では、遺留分の侵害に対する法的効果を「遺留分減殺請求権」という物権的権利の発生から「遺留分侵害額請求権」という債権的権利の発生に改め、贈与・遺贈の法的有効性を認めた上で、単に受贈者・受遺者に対して侵害された部分の金銭を求め得るに止まると定めたのです。
遺留分侵害額請求権の特徴
先程の遺留分減殺請求権との違いでも記載しましたが、「遺留分侵害額請求権」の特徴は、①金銭を請求できる債権に過ぎず、贈与や遺贈の目的物(権利)を支配する効果は認められていないという点です。また、②遺留分侵害額請求を受けた受贈者・受遺者は、管轄の裁判所に申し出ることにより侵害額相当の金銭の支払いつき、相当の期限を許与してもらうことができます。これにより、裁判所から許与された期限の利益が残存する限り、受贈者・受遺者は債務不履行(履行遅滞)に陥ることはなくなります。その結果、遅延損害金の発生や強制執行のリスクを回避することができます。
遺留分侵害額請求権はどのように行使すればよいですか
まず、遺留分侵害請求ができるのは、個別的遺留分の侵害を受けた遺留分権利者だけです。その遺留分権利者が死亡した場合、その侵害額請求権が相続財産となり、相続人が行使することができます。また、遺留分侵害額請求権は単純な金銭債権ですので、これを第三者に債権譲渡することも可能です。
遺留分侵害額請求権は、「形成権」(権利行使することを意思表示することで初めて効果が発生する権利)ですので、受贈者・受遺者に対して意思表示することで初めて行使できます。その意思表示に際しては、単に遺留分侵害額請求権を行使する旨のみを内容として表示してあれば足り、具体的な金額等を特定している必要はありません。また、訴え(訴訟)による必要もありません。口頭で表示することでも法律的には有効です。ただし、この場合、意思表示を行ったことが証拠として残りません。後の時効の問題と絡んで致命的なミスになりかねないため、遺留分侵害額請求の意思表示は、できれば内容証明郵便、最低でもLINE等の記録に残る方法によって行うことが望ましいでしょう。なお、意思表示は、相手の支配領域に到達した時点で初めて為されたものと認められます(到達主義)。内容証明郵便は書留であるため、相手方が不在を装って受領しなければ送り主のもとに戻ってきてしまいます。このような場面では、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
実際上問題となるのは、遺産分割協議の申入れを遺留分侵害請求の意思表示とみなせるかというものです。原則として、これはみなされません。遺産分割協議と遺留分侵害請求は全く別の法的根拠、別の制度であるからです。もっとも、たとえば、「遺産はすべて〇〇に譲る」といった遺言が為されていた場合、〇〇以外の相続人にはもとより相続分がありません。この場合には、そもそもこの相続人には相続分が存在しない、つまり遺産の取り分が認められないにもかかわらずその分割を申し入れていることになりますので、その者の本意は遺留分の権利を主張する点にあると推測されます。このような場合には、当該遺産分割協議の申入れは、実質的には遺留分の主張を意味するものと判断され、遺留分侵害額請求の意思表示が為されたものとみなされます。
遺留分侵害額請求権の代位行使は認められない。
民法の世界では、債権者代位権という権利があります。これは、債務者が無資力の場合、債権者は、債務者が第三者(「第三債務者」と呼ばれます。)に対して有する債権を、債務者に代わって行使して取り立てを行い、自身の債権の弁済に当てることができるという制度です(民法423条)。
遺留分との関係では、遺留分侵害額請求権を有する債務者が無資力の場合、その債権者は、債務者に代わって遺留分侵害額請求権を行使できるのか、という問題が重要となります。この問題につき、旧法(2019年7月1日以前に適用される相続法)の判例ではありますが、最高裁判所は、代位行使を否定しました。理由としては、債務者である相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無、あるいは、相続放棄の有無等によって左右される極めて不確実な事柄であるから相続人の債権者は、遺産を債権の担保として期待すべきでないということを挙げています。先ほども説明しましたとおり、遺留侵害額請求権は、形成権であり、それを行使することを意思表示して初めて効果が認められる権利であり、そのような意思表示を行うか否かは遺留分権利者の内心に委ねられています。こうした遺留分権利者の内心の自由に加え、そもそも債権者の側も遺産による弁済を期待すべき立場にないという考えからも、遺留分侵害額請求権の代位行使は認められないという結論になります。
遺留分侵害額の算定式
遺留分侵害額は、以下の算定式で表されます。これは、遺留分の「基礎財産」を基にして、当該遺留分権利者自身が贈与・遺贈を受けているか否かなど請求者側の事情を加味した式になっています。
①遺留分権利者の個別的遺留分の額 – (②当該遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益に当たる贈与の額 + ③残された遺産から当該遺留分権利者が相続分によって得る遺産の価額) + ④相続債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額
①の個別的遺留分の額の算定式は、以前既に説明しましたので、こちらをご参照下さい。
次に、遺留分侵害額の算定では、①遺留分権利者の個別的遺留分の額から②・③の要素を控除します。②は、当該遺留分権利者自身が遺贈や生前贈与を受けている際は、これを控除することになります。遺留分権利者本人が受遺・受贈を得ている以上、その額を控除しなければ公平でないからです。③は残された遺産について相続分に応じて遺留分権利者に割り当てられる財産がある際は、その受益相当額について遺留分侵害額は減少するという当然の話となります。最後に、④ですが、相続債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額は加算されます。負債のみ負わされて遺留分算定おいてこれが考慮されないことは相当とは言えません(被相続人の愛人が多額の贈与を受けて、他方で相続人である妻は多額の相続債務を負担している局面を考えるとイメージできるかと思います。)。このような状況の公平を図るためにも、遺留分侵害額を算定するに当たっては、遺留分権利者が負担する相続債務の額を加算することとなります。
受遺者・受贈者が遺留分権利者の負担する相続債務を消滅させた場合
遺留分を侵害する遺贈や贈与の受遺者・受贈者が第三者弁済や免責的債務引き受けなどの行為によって遺留分権利者の相続債務を消滅させた場合、この受遺者・受贈者は、当該債務を負っていた遺留分権利者に対して、その対等額(消滅させた相続債務の額)を上限として、遺留分侵害額請求権の消滅請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求の相手方
【受遺者と受贈者がいる場合】
遺留分侵害額請求の相手方は、遺留分を害するような遺贈を受けた者(受遺者)、あるいは、遺留分を害するような贈与を受けた者(受贈者)となります。
では、受遺者と受贈者の両方がいる場合、遺留分侵害額請求はどちらに対して行うべきでしょうか。この点について、民法は、受遺者から先に請求すべきとしています。そして、受遺者がうけた遺贈の額では、遺留分侵害額のすべてを回復しきれない際に初めて受贈者が残りを負担する関係に立ちます。これは、民法の中でも「強行法規」とよばれ、被相続人の遺言によっても変更できない事項とされています。したがって、遺言の中で「遺留分侵害額の弁済はまず受贈者が行い、次いで受遺者がこれを負担する。」といったような記載を行ったとしても、当該遺言は無効となります(遺言全体が無効となるわけではなく、当該部分だけが部分的に無効となります。)。
なお、「死因贈与」、つまり、生前に結ばれた贈与契約のうち死亡時点に効力は発すると定められた贈与については、「遺贈」に準じて取り扱われます。その結果、遺贈・死因贈与・生前贈与のすべてが行われているケースでは、遺留分侵害額請求の相手方は、まずもって受遺者の遺贈対象財産の価額から弁済し、それでも賄いきれなければ次いで死因贈与の受贈者が贈与対象財産の価格から弁済に当たり、それでも侵害額の回復が実現されなければ、最後に生前贈与の受贈者が生前贈与の対象財産の価額から弁済を行うこととなります。
なお、先順位者の無資力者がある場合、無資力による債権回収のリスクは、遺留分侵害額請求者が負います。その結果、受遺者と受贈者がいる場合、本来的に受贈額で遺留分侵害額請求の弁済が賄えるにもかかわらず受遺者が受贈された財産すべてを受け取ってすぐにカジノで使い切り、手元に何も残っていないという場合、これに伴う回収リスクは遺留分権利者が負担し、受遺者の無資力を理由に受贈者に対して請求することはできなくなります(受贈者に対して請求できるのは、遺贈財産だけでは額面的に遺留分侵害額に満たない場合のみです。)。
【受遺者や受贈者が複数いる場合】
受遺者が複数いる場合、あるいは複数の贈与が同時に行われていた場合、これらの対等な関係にある者たちは、遺贈・贈与の目的の価額の割合に応じて遺留分侵害額を按分して負担します。例えば、遺言においてAに3000万円、Bに5000万円の遺贈がなされた場合、受遺者Aと受遺者Bは、3:5の割合に応じて遺留分侵害額請求に対して弁済の義務を負います(連帯はしません。)。
もっとも、これは「任意法規」と呼ばれ、遺言によって別段のルールを定めることが可能な規定です。
なお、複数の贈与が存在し、且つ、その贈与が時間的に前後している場合、後にある贈与(相続開始の時点から遡って近い方の贈与)から順次、侵害額請求への弁済を負担することとなります。たとえば、相続開始の3年前にAが3000万円の生前贈与を受け、相続開始の5年前にBが5000万円の生前贈与を受けている場合、原則的にAが受贈した3000万円から侵害額請求の弁済に当たり、侵害額がAの受贈額3000万円を上回る場合に初めて、Bが受贈額5000万円から侵害額請求の弁済に当たることになります。贈与の前後は実際に財産が移動した時期ではなく、贈与契約が成立した時期で判断されます。なお、これは「強行法規」であり、これと異なるルールを被相続人が遺言で定めたとしても、当該遺言は無効となります。
遺留分侵害額請求の相手方の利益の保護
遺留分侵害額請求は時として莫大な金額となることがあります。他方、受遺者や受贈者が受け取った財産が現金や預金ではなく不動産や事業財産である等、すぐに現金化できないケースが存在します。
一方、遺留分侵害額請求では、即時の弁済が原則であるところ、何の手当もなければ、遺留分侵害額請求を受けた受遺者・受贈者は、債務不履行に伴う多額の遅延損害金リスクや、事業財産の差押えや競売により事業継続を危険に晒す倒産リスクまで背負いかねない状況に陥ります。
そのため、民法は、遺留分侵害額請求の相手方が裁判所に請求した場合、裁判所が金銭債務の全部または一部の支払いについて相当の期限を許与することができることにしました。その結果、その期間内であれば、受遺者・受贈者は遺留分侵害額請求に対して債務不履行に陥ることなく、遅延損害金の発生や差押え等保全・強制執行のリスクを逃れることができます。
遺留分侵害額請求の相対性
遺留分というのは、遺留分権利者各人に認められた個別的な権利です。遺留分兼を行使したい遺留分権利者は単独で自身の個別的遺留分を主張し、これが侵害されている際は侵害額請求を行うことができます。他の遺留分権利者が権利を行使するしないに関わらず、自身の権利を単独の者として行使することができます。法は、遺留分権利者の共同の行使を予定しておらず、あくまでも各人の個別的権利として定め、それを行使するか否かも権利者各人に委ねています。
遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間
遺留分侵害額請求権には、消滅時効があります。期間は非常に短く、①相続の開始、及び、②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年とされています。
このうち、よく問題となるのは、②です。ここでは「遺留分を侵害する」という点が特に重要で、遺贈や贈与の事実は知っているものの、相続財産の全額が不明であるため自身の遺留分が侵害されていることを知らなかったような場合には、1年間の起算はされません。あくまでも、自分の遺留分が侵害される贈与・遺贈があったことを知った時から1年間が起算されるのです。
また、よく間違えられるポイントなのですが、1年間の消滅時効が適用されるのは、遺留分侵害額請求権そのもの、すなわち、遺留分侵害を理由とする侵害額請求の意思表示をすることができる権利であり、遺留分侵害額請求の結果として得られる金銭債権(侵害相当額の金銭の支払いを求める権利)ではありません。1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示さえしておけば、その結果生じる金銭債権は通常の消滅時効期間として5年間は行使可能となります。
また、遺留分侵害額請求権は、1年の消滅時効とは別に5年の除斥期間にかかります。除斥期間というのは、権利者本人の事情(①・②の事実を知った知らないといった事情)とは関係なく、一定期間の経過によって権利者から権利を剥奪するという制度です。遺留分侵害額請求権の場合の除斥期間は10年間であり、相続開始時という客観的な基準から起算されます。この場合、遺留分権利者が相続開始の事実を知っていたかどうかも関係がありません。
以上、遺留分侵害額請求の請求方法を取り上げて参りました。なかなか難しい点が多かったと思いますが、分からない点があれば遠慮なく当事務所にご相談下さい。次は、遺留分の放棄について説明いたします。
遺留分についてご相談をされたい方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスにご連絡下さい。初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。まずはお電話でお問合せください。
0120-100-129
(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)