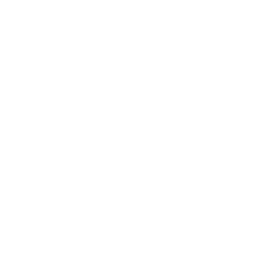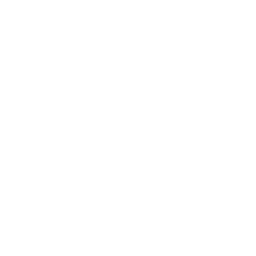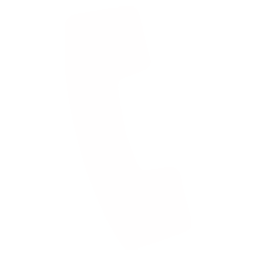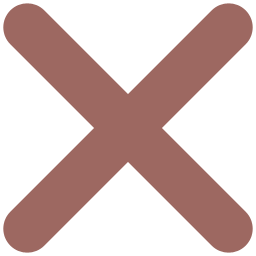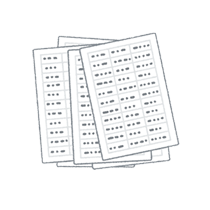中小企業の事業承継のための遺留分の特則
更新日:2022/10/06
中小企業の事業承継のための遺留分の特則

遺留分という権利は、被相続人から見て特に近しい関係にある相続人の最低限の利益を維持するため必要な制度と言えます。もっとも、その一方で、中小企業の事業承継の局面ではこの遺留分制度が非常に大きな問題となることがあります。
中小企業の多くは、個人事業の延長のような状況にあり、主要株主と経営者が同一であるケースが多く、このような場合、経営者(株主でもある)の財産は、その大半が事業に関するものであることが少なくありません。例えば、被相続人の財産の大変が経営する会社の株式であったり、会社の工場の敷地であったりというケースです。このような場合、経営者としては、自身の事業の後継者に対して自身が有する事業関連資産を承継したいと考え、これらを生前に贈与したり、あるいは遺贈したりすることが通常です。もっとも、そうすると、被相続人の財産の過半を単一者(しかも、場合によっては相続人以外の第三者)に集中して承継させることになり、他の相続人の遺留分が侵害され、しかもその額が極めて高額に上ることがあります。そうすると、事業の後継者は、遺留分権利者から高額な遺留分侵害額請求を受けることとなりますが、事業資産の内容が会社株式であったり生産設備となる不動産であったりした場合、これを譲渡して現金化することはできず、事業の存続自体が困難になりかねません。日本の2018年改正民法(2019年7月1日施行)では、このような場合に備えて裁判所に申し出ることによって遺留分侵害額請求への弁済について相当の期間の猶予を得ることができますが、それだけでは事業後継者の保護に欠け、高齢化が進む我が国の中小企業経営者からの円滑な事業の承継という国策を十分に実現できません。
そこで、日本では、民法が定める相続法とは別に、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」という法律を別に定めました。この法律では、事業承継を円滑にするため、「除外特例」と「合意特例」という制度を定めてあります。これらの特例を受けるためには、先代経営者の後継者(相続人に限らない)と非後継者相続人の全員で合意書面を作成し、その合意をした日から1月以内に後継者が経済産業大臣に対して合意に関する確認申請を行い、この確認が得られた後やはり1月以内に後継者が管轄家庭裁判所(旧代表者の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して許可申立てを行いその許可を得る必要があります。
このような手続を経た場合、先ほど挙げた2つの特例のいずれかの法的効果を得ることができます。まず、「除外特例」について説明しますと、ここでいう「除外」とは、旧代表者から後継者が承継する自社株式等については、遺留分算定の基礎財産に参入しないということを意味します。この場合、たとえば、旧代表者が個人財産はほとんど持たず、その財産のほとんどを会社名義としており、その会社株式を通じて財産を保有していたとしますと、その自社株式こそが主要な相続財産となりますが、遺留分算定当たってこの自社株式の価値が遺留分算定の「基礎財産」に組み込まれないこととなり、遺留分の額が少なくなります。その結果、事業の後継者としては、遺留分侵害請求のリスクをかなり小さくすることができます。もちろん、遺留分権利者となる相続人の承諾(合意)があって初めて実現できるものですが、後継者による事業の円滑な継承や存続を非後継者相続人たちも強く希望しているような場合には、有効なスキームとなります。次に、「固定合意」について説明しますが、ここでいう「固定」とは、自社株式等の評価基準日を相続法の原則である相続開始時ではなく合意時点に固定するということです。相続開始とは、旧代表者の死亡時を意味しますが、人の生命がいつ尽きるかは事前には容易に判断できないところ、その死亡時点次第で自社株式等の価値が大きく変動し、それによって遺留分侵害請求のリスクが増大します。その結果、後継者が事業の承継に手を挙げづらく事態を回避するため、自社株式等については、例外的に評価基準日を合意時点と定め、遺留分算定の「基礎財産」には合意時点での自社株式の価額を組み入れることとすることで、遺留分侵害額請求の経済的なリスクを事前に明らかにし、予測可能性を高めることで事業承継を円滑にすることができます。
以上、遺留分権利者の相続開始前の法的地位がどのようなものかを説明いたしました。こここまでで、遺留分に関する一通りの説明は終わりとなります。
遺留分についてご相談をされたい方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスにご連絡下さい。初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。まずはお電話でお問合せください。
0120-100-129
(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)